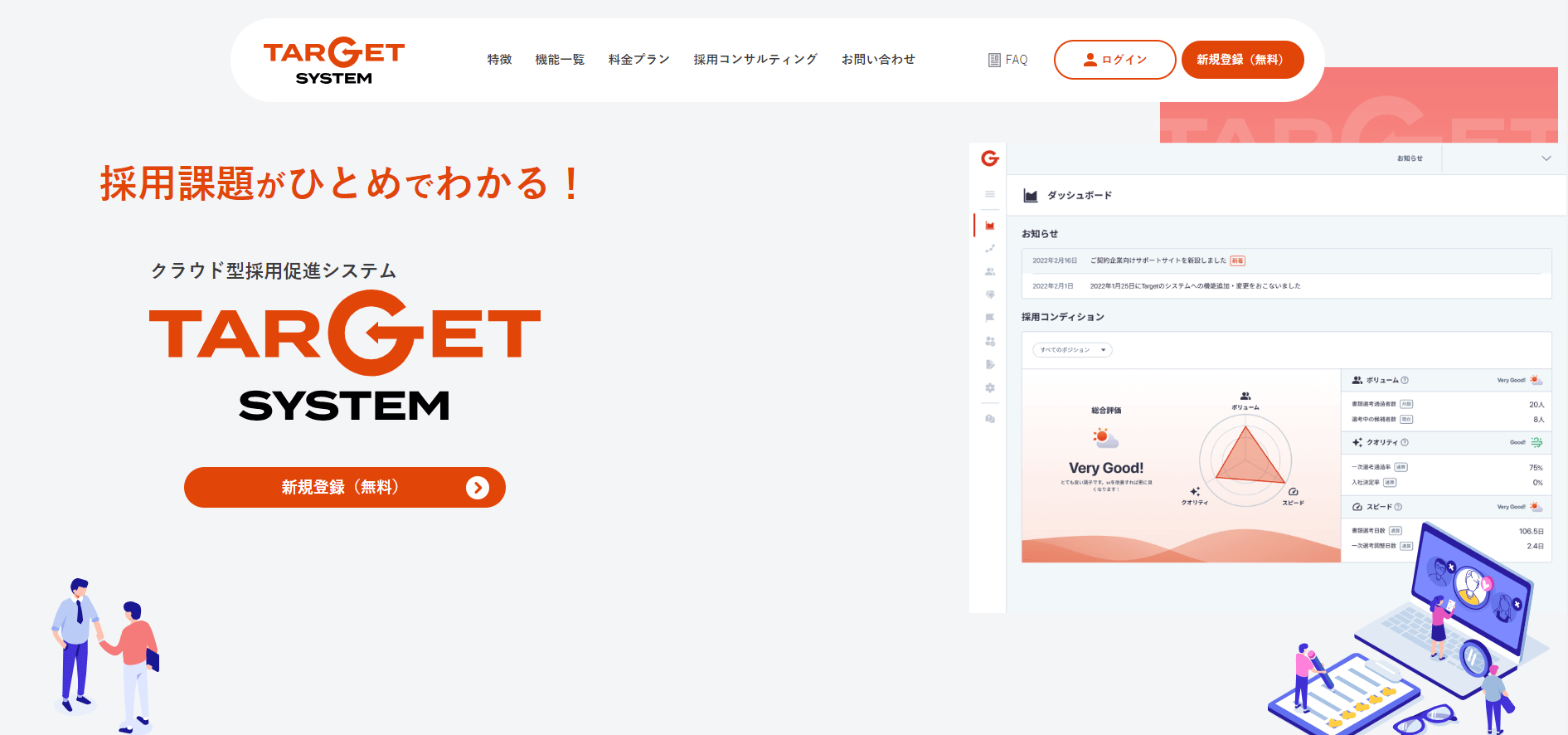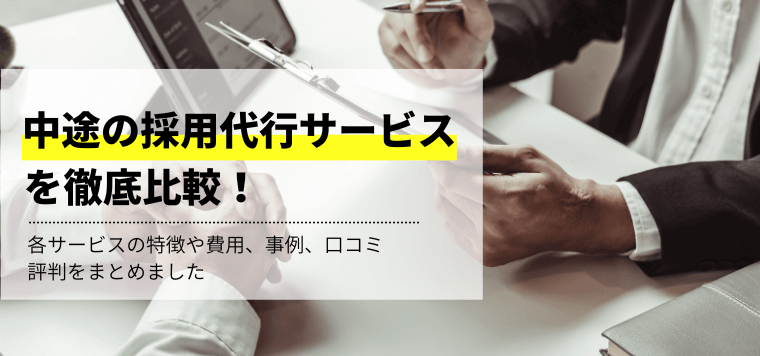内定者フォローツールは、企業と内定者、または内定者同士のコミュニケーションを促進することを目的としたツールです。内定者の不安を和らげ内定辞退の防止や、社員とコミュニケーションを取ることで入社意欲を向上させたりといった、内定者フォロー業務の効率化が期待できます。
この記事では、内定者フォローツールを提供する各社の特徴や費用、口コミなどを紹介します。また、内定者フォローツールを利用するメリット・デメリットや使いこなす方法についても解説しますので、ツールの導入を検討する際の参考にしてください。
内定者フォローツールの一覧表
ここでは、各社が提供する内定者フォローツールを一覧で紹介しています。内定者フォローツールは自社の業務や社員との相性も重要なため、システムごとに異なる機能性や料金プランを比較して、自社にぴったりのサービスを見つけましょう。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
内定者パルスサーベイPEPS |
内定者の辞退リスクを数値化!コンディションを把握し内定辞退の問題を解決へ
|
Chaku2 NEXT |
入社までの不安な期間をアプリのコミュニケーションでフォロー |
エブリONE |
スマホで簡単ログインOK!プッシュ機能で更新情報も素早く通知 |
バヅクリ |
導入企業数700社以上!辞退率30%改善に導くツール |
エアリーフレッシャーズクラウド |
98.6%が内定辞退防止に効果ありと回答!累計利用者数5,479社のツール |
内定者パック |
導入実績2,800社以上・年額5,000円〜設定が魅力! |
Any See |
人事担当者の業務と内定者の不安の両方を解決に導く |
MOCHICA |
企業と応募者を”もっとちかく”にする採用管理ツール |
miryo+ |
採用活動の質を高める企業の魅力付け強化をサポート |
採用一括かんりくん |
圧倒的なコストパフォーマンスで工数削減と歩留まり向上を支援 |
i-web |
業界唯一!大手就職情報サイト&適性検査とシームレス連動 |
内定者フォローツールのメリット・デメリット
ここでは、内定者フォローツールを活用する際のメリットとデメリットについて紹介します。
メリット
採用業務の効率化はもちろん、ツールを通して、企業と内定者のコミュニケーションの構築が図れるため、内定辞退防止につながると考えられます。企業側からは、社内の様子や先輩社員の紹介ができ、内定者は、プライベートな趣味や特技などの自己アピールができる点が魅力です。
入社前には不安を抱える内定者も少なくありません。ツールを活用すれば、内定者同士のつながりが持てる上に入社前の準備もできるので、モチベーション低下の心配なく入社式が迎えられます。
デメリット
内定者との距離感を間違えると、お互いに気分を害する可能性があります。業務に不慣れでサポートしたい気持ちが強くなるために、手取り足取りの指導をしてしまうとかえって逆効果です。
また、内定者とのコミュニケーションは、できれば同世代の若手社員に任せましょう。同じ言葉でも、年長者が発すると威圧的に感じてしまう内定者も少なくありません。受け取り側の気持ち1つで、思いがけずパワハラに繋がらないような配慮が必要です。
内定者フォローツールの種類
ここでは、内定者フォローツールの種類別に特徴を紹介します。
内定者の不安を緩和する
内定を得ても、内定者は時に企業に対して不安や悩みを抱くケースも少なくありません。一般的に「内定者ブルー」といわれる状況で、解消するには、採用担当者や内定者同士の交流が重要です。
内定者フォローツールを選ぶ際は、コミュニティ機能やトーク機能を備えているものが有効です。
研修や業務フローを効率化
入社前の業務は、通知メールや電話での確認などで採用担当者に負担が大きくなります。内定者フォローツールは、採用業務を効率化するサービスを提供。
担当者は業務の効率化と、より重要な採用業務に集中できます。
内定辞退を減らすフォロー
内定者フォローツールは、エントリー率や内定辞退率の改善にも役立ちます。採用前から内定後までをトータルでサポートする機能を持ち、内定者向けの情報提供やコミュニティ構築を行い、不安な気持ちを和らげる効果が期待できます。
内定者フォローツールを使いこなす方法
自社の人に合った内定者フォローツールは、効率的に使いこなさなければなりません。内定者フォローツールの使いこなし方について紹介します。
定期的なコンテンツ配信
内定者フォローとして、定期的なコンテンツ配信は必要です。暇な時間ができた時やアイディアを思いついた時など、不定期での配信は、内定者フォローの効果が弱くなる可能性があります。
設定したスケジュールをもとに内定者の関心を引くコンテンツを制作し、定期的な情報発信ができれば、内定辞退のリスクも避けられるかもしれません。
採用担当者間で操作方法を共有
働き方改革で、在宅ワークを導入している企業も多いのではないでしょうか。しかし、対面でコミュニケーションを取る機会が少なくなったとはいえ、採用担当は内定者に対して、常時デフォルトの対応が求められます。
そのため、内定者フォローツールの操作方法は、導入と同時に全員で共有しておきましょう。
採用担当者以外の社員も操作方法を習得
内定者ツールは、採用担当者だけが使用するものではありません。コンテンツ配信用に社員インタビューを実施したり、社内の様子を撮影したりと他部署の社員の協力も必須です。
同時に、内定者フォローツールの操作法も習得しておけば、協力を依頼する際もスムーズです。内定者ツールを使いこなすためには、他部署の社員とも連携体制を構築してください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年11月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。