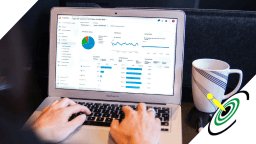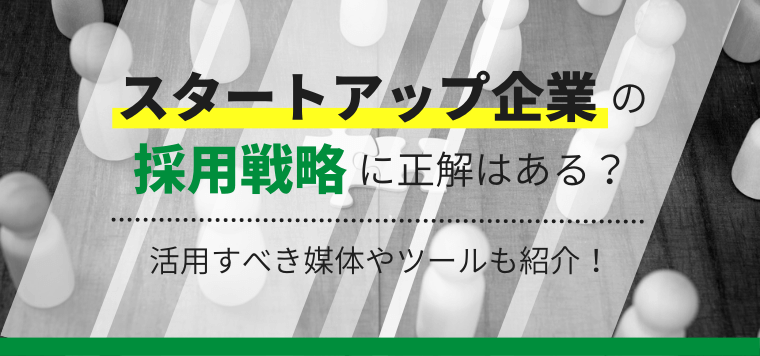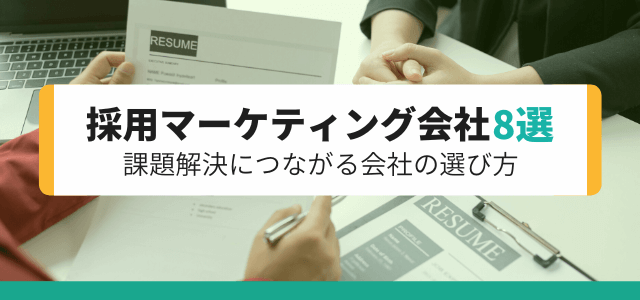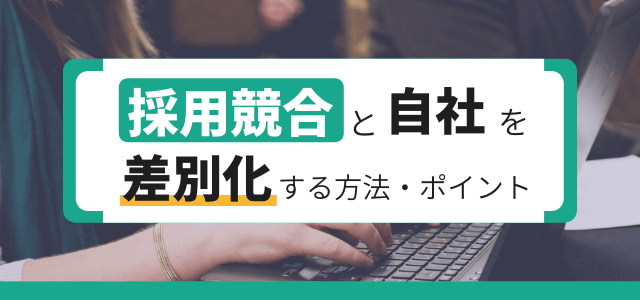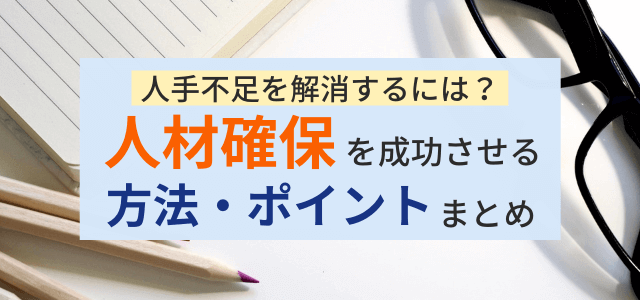事業は成長しているものの、社員の早期退職や業務効率が気になっていて、さらなる会社の成長のためにも、会社の現状を把握したいと考えていませんか?
本記事では、会社が抱えている課題や問題を可視化できる組織診断ツールを紹介しています。
それぞれの強みや特徴、料金も詳しく解説しているので、会社の現状を把握したい方や課題を解決していきたいと考えている担当者の方は必見です。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
BUSINESS DRIVE組織 |
経営理念から人材採用まで!AIが解決策を提案する組織診断ツール
|
ラフールサーベイ |
カスタマーサクセスによる手厚いサポートが充実 |
Wevox |
企業の状態を多角的に見ることで問題や課題を可視化 |
CYDAS PEOPLE |
「働きがい」を作ることに重点を置いた組織診断ツール |
LLax forest |
サーベイ・フィードバック・ソリューションの3つサービスを提供 |
Geppo |
個人と会社の両方の課題を可視化できる |
A&Iエンゲージメント標準調査 |
個人の働きがいと会社への思いが明確に把握可能 |
モチベーションクラウド |
診断と変革のサイクルを活用して組織の課題を解決 |
ハタラクカルテ |
人材の定着やエンゲージメントに基づく15項目のサーベイを実施 |
EX Intelligence |
入社から定着までの課題を定量的に把握できる |
PULSE AI |
組織改善や離職率を低下させることに役立つツール |
wellday |
リアルタイムで社員の状態を可視化 |
組織診断ツールとは?
組織診断ツールとは、アンケートを行い会社や社員が抱える問題を可視化できるツールで、生産性の向上や離職率の改善を図ることに役立ちます。具体的には、社員の会社に対する満足度やエンゲージメント、ストレスなどを可視化することができます。
組織診断ツールを活用することで、社員の人間関係やモチベーションを調査でき、具体的に組織の状況を把握することが可能です。例えばアンケートの結果から、精神面で負担がかかっている社員を見つけ出し、メンタルヘルスケアを行い、突然の離職を防ぐことができます。
また、会社や社員が抱えている問題を把握できるため、どのように問題を改善するかを考えることが可能となり、解決すれば会社にとって大きなメリットとなります。
さらに多くの会社はストレスチェックの実施が義務付けられた後から、社員のメンタルヘルスを重視し、職場改善に努めています。そのため、組織診断ツールを導入している会社は、増加傾向にあります。
組織診断ツールを利用するメリット
組織診断ツールを利用するメリットは、以下の4点です。
- 組織の現状が把握できる
- 従業員の満足度が高められる
- 生産性の向上が実現できる
- 早期離職が防止できる
自社の問題を明確に把握するため、しっかりとメリットを理解した上で導入する組織診断ツールを選ぶことをおすすめします。
組織の現状が把握できる
組織診断ツールでは、会社や社員が抱えている問題だけでなく、実際の会社の状況を把握することができます。問題点だけでなく、優れている点も可視化できるため、問題点を改善し、優れている点は伸ばすように働きかけることが可能です。
また他の会社にはない自社だけの強み見つけ出すことができるため、他社との差別化を図れます。
これまで問題を解決しようと様々な施策を講じてきたにも関わらず、結果がうまくいかなかった場合には、会社の現状をしっかりと把握できていなかったことが原因の可能性があります。そのため、組織診断ツールを駆使し、会社の現状を正しく把握することが大切になっています。
従業員の満足度が高められる
組織診断ツールを活用することで、社員の不満や悩みを調査し、改善することが可能です。上司が直接聞き取りを行ったとしても、正直に話をしてくれる社員は少なく、本当の悩みを聞き出すことが難しくなっています。
しかし組織診断ツールを活用すれば、社員が抱えている不満や悩みを可視化することが可能。一人ひとりの満足度を高めることで、仕事に対する意欲を向上させることができます。
組織全体のパフォーマンスが低下してきていると感じている会社は、一度組織診断ツールで社員が抱えている問題を可視化し、効果的な対策を講じることで、社員の満足度の向上を図れます。
生産性の向上が実現できる
組織診断ツールで把握した問題点の改善を図ることで、会社全体の生産性の向上を図れます。その結果、商品やサービスがこれまでよりも良いものが作れたり、販売実績が伸びたりして会社の成長に繋げることができます。
また現在行っている事業だけでなく、新規事業の立ち上げの際にも組織診断を活用することで、大きなメリットを得られます。具体的には、あらかじめ組織診断ツールで問題点を可視化させておき、その問題点を解決していく過程で新事業を成長させることができます。
的確な対策を行うことで、社員のモチベーションを向上させ、チーム力を強めることができます。
早期離職が防止できる
組織診断ツールの結果をもとに、社内の制度や環境を整えていくと、社員にとって働きやすい職場をつくることができ、早期離職を防止することが可能です。そのため、離職率が高い会社にとっては、組織診断ツールを導入することがとても大切なことと言えます。
また、日本では優秀な人材の確保が難しくなってきています。優秀な人材を逃さないためにも、早急に会社の構成を整え、社員にとって働きやすい環境を作ることが重要です。
社員にとって働く環境がより良くなることで、「この会社で頑張りたい」という社員が増え、自然と離職率を低下させることができます。
組織診断ツールのデメリット
組織診断ツールにおけるデメリットは、実施するにあたって会社にとって手間とコストがかかってしまうことです。まず組織診断を行う際には、あらかじめ社員に周知しておく必要があります。
急に調査を始めてしまうと、何のための調査かわからず、逆に社員の不満を生み出しかねません。そのため、社員には丁寧に組織診断ツールを行うにあたっての目的や意図を伝えることが大切です。
また、通常の業務に加えて、調査の実施や結果の回収といった業務が増えてしまいます。そのため、担当者に負荷がかかってしまう恐れがあります。
さらに、組織診断を行う前にどのような課題を見据えて実施するかを明確にすることが必要です。やみくもに診断を行っても、結果だけで満足してしまって、行動に移さなければせっかくの効果が得られないからです。
まずは一歩前進し、行動に移すことで、自社の抱える課題解決へと進んでいくことができます。
組織診断ツールの費用相場は?
組織診断ツールを導入する際にかかる費用相場は、一人あたり167円から導入できるツールもあれば、人数によれば約30万円かかるツールもあります。
会社の規模やプランによって費用は変動してくるため、詳しい費用が知りたい方は、直接問い合わせをすることをおすすめします。
組織診断ツールを選ぶ際の注意点は?
組織診断ツールを選ぶ際に注意するべき点は以下の3点です。
- 診断後の行動を明確にしておく
- できるだけ社員の負担にならないようにする
- 結果だけに囚われすぎないようにする
診断後の行動を明確にしておく
組織診断を行うだけで満足していては、会社が抱えている課題の解決をすることが難しくなってしまいます。組織診断は課題を可視化して終わりではなく、その課題をどう解決していくかを考えていくことがとても大切になっています。
そのため分析した後は、結果から具体的な解決策を考え、実際に行動して検証していくことが重要です。そして、長期的なスパンで継続していくことで、より良い会社の職場環境や社員の満足度向上に繋げることができます。
できるだけ社員の負担にならないようにする
組織診断ツールは、社員一人ひとりにアンケートに答えてもらう必要があります。社員はアンケートに答える時間は、業務中や休憩中なことが多いため、質問数が多すぎたりアンケート期間が短かったりしてしまうと、社員の負担になってしまう恐れがあります。
社員が負担と感じてしまうと、アンケートの答えを適当に済ましてしまうことに繋がりかねないので、できるだけ社員の負担とならないよう組織診断を行うことが重要です。
質問数を社員が答えられる範囲に設定したり、期間を長めにしたりすることで、社員一人ひとりに配慮しながら診断を行うことができます。
結果だけに囚われすぎないようにする
組織診断ツールで得られるデータは、会社の状況です。しかし社員の中には、正直に答えていない人や悩みを隠している人がいる可能性もあり、結果が全て正しいと断言するのが難しくなっています。
そのため、組織診断ツールで得たデータを鵜呑みにするのではなく、会社の状況を改善する上での参考程度に捉えておいた方が無難です。診断結果を加味し、実際には働いている中での雰囲気や状況から、会社の課題解決に向けての解決案を考案することが大切です。
組織サーベイの種類
従業員サーベイ
従業員が会社に対して満足しているかを調査するため、または会社が就業規則や人事制度を改定する際に従業員の実情を調査するために行われるのが従業員サーベイです。質問項目として、社内の人間関係や環境、満足している・不満を抱いているポイントなどがあります。従業員満足度調査と重なる部分もありますが、従業員サーベイは満足度調査と比べて調査の幅が広いのが特徴です。満足度調査は従業員の満足度にフォーカスした調査ですが、従業員サーベイは「新しい人事制度の効果」と目的を定めて実施できます。
従業員サーベイの目的
人事に対する従業員のニーズを聞く
普段の業務内では聞くことが出来ない、従業員の社内環境へ満足している点・不満がある点が分かります。人事が従業員を思って働きやすくなる施策を考えても、従業員のニーズからズレてしまえば意味がありません。従業員サーベイで従業員のリアルな声を聞くことで、適切な人事施策が可能です。また、サーベイを受ける従業員としても意識していなかった社内環境に対する印象を表出させることができるでしょう。社内で制度に対してFBしないタイプの人たちからも、サーベイを実施することで意見が貰えるのが良いところです。
曖昧な情報を数値化して判断材料に
現在の人事制度に対しての評価は、従業員からの評判が良い・悪いという印象の話になってしまいがちです。これでは具体的な課題が掴めず、解決に向けて動きづらいといった問題が生じます。しかし、従業員サーベイならば賛成が何%、反対が何%と数値で表現されることになります。制度を変えたい、と経営陣に伝達する際にも判断材料として提示できるでしょう。
調査結果を人事に活用する
現在の人事制度に対してサーベイを行う場合、人事を管理する側は従業員サイドの認識をサーベイによって把握することが可能です。収集した情報から、今の人事制度には不足している・超過している箇所を分析。人事制度の改定・改善に活かすことができます。従業員サーベイは実施することよりも、実施した結果が人事に活かされることで効果を発揮するでしょう。
従業員サーベイが実施される理由
サーベイツールの普及によって調査がしやすくなった
従業員サーベイはツールが普及する以前、紙のアンケートを作って集計する必要があり、従業員の声を集めることは負担が大きく、企業としても簡単に実施できるものではありませんでした。しかしサーベイツールの普及以降、WEBを利用したサーベイが可能になり、労力が減りました。サーベイツールの普及によって積極的に従業員の意見を取り入れる機会ができたのです。
従業員全体に調査できる
従業員サーベイは、従業員全体に実施するので大量のデータが得られます。制度への印象が曖昧なものから、数値化されることで。サーベイを実施する人事側が課題の規模感を把握でき、改善するための取り組みを考案・実行しやすくなりました。
モラールサーベイ
従業員のモラールを測定するために、年に1回〜数ヶ月に1度実施されるのがモラールサーベイです。モラールとはフランス語で「士気」「意欲」を意味する言葉で、組織として目的を達成しようとする意欲・態度を意味します。企業の経営目標を達成するには、従業員のパフォーマンスを維持・向上する必要があります。モラールサーベイは、従業員のパフォーマンスをプラスにする要素が何か、マイナスになる要素が何かなど具体的な情報を集めるために使用されます。
モラールサーベイの目的
従業員に経営への関心を持ってもらう
自分は単なる従業員だから企業としての動きや経営に対して無関心でいいや。別に気にしない。自分に関係ない。というスタンスを変えるのも、モラールサーベイの目的の一つです。サーベイを通して従業員に企業の一員として求める意欲・態度が共有されます。経営や組織運営に従業員からの意見を反映させたい、という姿勢を示すことが可能です。モラールサーベイによって、従業員は経営に関心を持つようになり、組織力を高めることが出来るでしょう。
回答から最適な人材配置と役職登用が可能
モラールサーベイの回答によって、その従業員が持っている業務に対する認識や課題感を知ることができます。今の部署やポジションに対する熱量、組織運営に抱いている思いも把握できるでしょう。その情報から適切な部署への配置や管理職に登用するなどの人事的な手配が可能です。以前よりも適した環境に人材を配置でき、企業全体の強化を図ることができます。
組織の問題点を把握できる
経営目標を達成するために、組織として今何がネックになっているのか、どのくらいの従業員がそれを問題点と認識しているのかがサーベイで数値として上がってきます。人事や経営陣サイドが把握している課題は従業員のレイヤーになるとどのような受け止め方になっているのか。または従業員サイドで問題視されているポイントが何かを把握できるでしょう。企業はサーベイで把握した問題点を改善するための施策に取り組むことが出来ます。
モラールサーベイ実施の注意点
回答内容のプライバシーを守る
誰がどんな回答をしたか分からないように、プライバシー保護の観点から匿名方式での回答にしたり、個人の回答内容が社内の誰にも知られないように社外のサービスを利用したりすることを考えておきましょう。
回答の取り扱いを事前に検討する
サーベイを実施する前に、調査した情報の運用と管理はあらかじめ決めておく必要があります。回答を閲覧できる役職を限定する、サーベイの回答項目から誰が回答したか分からないようにするなどの対応が必要です。
従業員に前もって説明する
急にサーベイに回答してくださいと言われても、従業員の本音を引き出すのは難しいでしょう。サーベイの目的を説明して、得られた情報の運用と管理に関して伝える必要があります。実施する目的についてサーベイを出す側・サーベイに回答する側で認識統一されている状態がベストです。お互いに有意義なサーベイを目指しましょう。
モラールサーベイの種類
NRK方式モラールサーベイ
1955年(昭和30)に社団法人日本労務研究会が開発した、日本で最初のモラールサーベイ方式。組織で働く従業員の働く意欲になっている要因を分析するのがNRK方式モラールサーベイです。従業員が300人以上の企業を対象に、労働条件・人間関係・管理・行動・自我の5分野、合計95問で構成。企業の経営状況に応じて、質問項目の追加も可能です。回答方式は匿名制のマークシートかWEBの2種類。NRK方式モラールサーベイの費用相場は約50~90万円(従業員300人~1000人)です。
参照元:NRK方式モラールサーベイ(http://www.nichiroken.or.jp/morale_survey/nrk-fee.htm)
厚生労働省方式・社員意識調査(NRCS)
従業員の企業に対する所属意識や業務への認識を分析するのが厚生労働省方式・社員意識調査(NRCS)です。分析結果を元に企業としての意識レベルを世間水準と比較します。社団法人日本労務研究会が1957に開発しました。
従業員が300人未満の企業を対象に行います。内容がサービス業と他業種で異なっており、サービス業では経営への信頼・上司への信頼・顧客満足・労働条件・職場生活満足の5分野、合計40問。他業種では経営方針・組織命令系統・コミュニケーション・労働条件・仕事のやりがいの5つの分野、合計39問で構成されています。回答方式は匿名制のマークシートとWEBの2種類。厚生労働省方式・社員意識調査(NRCS)の費用相場は、約16~41万円(WEB回答・従業員数50人~300人)になります。
参照元:厚生労働省方式・社員意識調査(NRCS)(http://www.nichiroken.or.jp/morale_survey/nrcs-resarch.htm)
パルスサーベイ
従業員に簡易的な質問を短期間に繰り返し実施するのがパルスサーベイの特徴です。英語で「脈拍」と「調査」を組み合わせた言葉になっています。パルスサーベイは人間の脈拍を調査するように、従業員の現在の状態を調査することを指します。調査方式は1〜5分程度で簡単に回答できる質問を、毎日・週1・月1と定期的に実施。調査項目に対して従業員の持っている認識をリアルタイムでチェックできる点がメリットです。定期的に繰り返し調査をする方式なので、時間と手間がかかります。回答する従業員の負担になりやすい面もありますが、従業員満足度の向上に効果が期待できるサーベイとして大企業・中小企業どちらからも支持されています。
モラールサーベイ・社内アンケートとの違い
どちらも従業員に対する調査であることは変わりませんが、調査を実施する頻度・項目が異なります。モラールサーベイは頻度が年に1回〜数ヶ月に1度。従業員ごとに企業・業務に対する意欲や姿勢を測るものです。社内アンケートの調査頻度は年に1回〜数ヶ月に1度で、企業によって異なるでしょう。調査項目は多岐に渡り、エンゲージメント・ストレスチェック・従業員の要望などが挙げられます。
パルスサーベイの目的
社内の課題を素早く対応できる
パルスサーベイの特性上、リアルタイムで不満がある点や困っていることの把握が可能です。モラールサーベイや社内アンケートでは項目が多く、実施頻度が少なくて拾いきれない課題もフォローできます。不満や困りごとへの対応が遅れると、場合によっては重大なインシデントを引き起こしたり、従業員の退職を招いたりといったことに繫がってることも。その点、パルスサーベイでは調査から問題の発覚までが早く、対応もスピーディーになります。従業員がパルスサーベイで問題を報告する、問題が把握される、問題の原因が調査され、対策が行われるというサイクルが完成すると組織が健全化され、課題解決のノウハウも蓄積されるという好循環になります。
従業員から愛される組織や上司になれる
パルスサーベイで報告した課題に改善や対策が為されると、従業員はパルスサーベイで報告すると組織や上司が動いてくれるのだな、と好感を抱くでしょう。それは企業に対しての信頼になり、ひいては従業員と企業の強いエンゲージメントの構築が目指せます。従業員の定着率が向上することも想像に難くありません。組織や上司としても従業員がリアルタイムで何に悩んでいるのかを把握することができ、迅速なフォローアップが可能です。
最小限のコストで調査できる
パルスサーベイは、1回あたりの調査コストが少なくて済むところが特徴です。短い期間で何度も実施するために、従業員満足度や社内アンケートと比べて質問数や回答数を削るからです。年に1回もしくは数ヶ月に1回行われるアンケートは質問する項目の範囲も問題数も多くなり、回答だけでなく集計やフィードバックにも大きく工数を割く必要があります。外部に委託する場合でも調査費用がかかり、調査結果が出るまでに時間を要します。従業員がアンケートで答えた課題や不満が対策されるまでに大きな時間差が生まれるでしょう。パルスサーベイならば、短いスパンで繰り返し実施されることによって、従業員からの報告・課題の把握・適切な対策の流れが習慣化されます。最小限のコストで働く環境の改善が行えるでしょう。
パルスサーベイを実施するためには
パルスサーベイの動機・目的を共有する
「生産性の向上」「定着率を上げたい」といった明確な動機・目的を提示してパルスサーベイを実施するのが望ましいです。今、企業として不足している部分や強みとして押していきたい部分を深掘りしましょう。従業員に目的を表明して納得してもらうことが出来れば、企業全体で目指す方向が明確になります。従業員サイドが腑に落ちないままパルスサーベイが開始されると、運営する側としても有意義な情報が得られず、従業員サイドからしてもただただ面倒事が増えたと思われかねません。パルスサーベイの動機・目的を共有して、理解を得られるようにしましょう。
パルスサーベイの質問項目の決定
目的に沿った質問項目を決定し、調査を実施しましょう。パルスサーベイは短い期間で何度も実施できる手軽さがポイントです。質問項目は厳選したうえで調査を行うようにしましょう。目的ごとの質問例を確認しましょう。
生産性の向上
- 今の仕事内容に満足しているか
- チャレンジしたい職種があるか
定着率を上げたい
- 企業ビジョンに共感できるか
- 待遇面に満足しているか
良好なメンタルヘルスを維持したい
- 働く事にやりがいを感じているか
- しっかり休息を取れているか
調査結果の分析とその後の動き
従業員からの回答が集計できたら、経営者やマネジメント層と認識のすり合わせや課題の抽出を実施。従業員からの評価が高い施策については継続したり、さらにコスト投下したりしても良いでしょう。ネガティブな意見があった事項に関しては対策が必要です。しかしパルスサーベイそのものの回答率が悪い場合、従業員全体に質問することで確保していた数による信頼性が失われます。回答していない従業員の状態が分からない状態かつ回答している従業員の意見に偏ってしまう恐れも。回答率を下げる要因として考えられるのは「質問文が難しい」「質問が多い」「匿名じゃないので自分の発言だとバレる」などがあります。従業員が安心して回答できるように、パルスサーベイ自体の見直しとブラッシュアップが欠かせません。パルスサーベイでは、雰囲気や評判ではなく、賛成・反対が数値として見える化されます。調査結果から従業員が感じている課題を分析して抽出することが可能です。適切な分析を行うためにも、充分な調査結果を回収できるように心がけましょう。
パルスサーベイの活用方法
オンボーディングでの活用
オンボーディングとは新人研修や部署異動によって新しいチームに入った従業員をフォローする動きのことです。特に年間の新規採用者や異動する人が多い会社では、オンボーディングをいかに成功させるかが企業課題の1つといえるでしょう。パルスサーベイは、短期間で繰り返し従業員のいまの状態を調査するものです。新しい組織に入った従業員の早期戦力化や離職防止が見込めます。なぜならパルスサーベイの結果をオンボーディングの改善に活用し、環境・目標設定・人間関係などの中で困ったポイントを改善できるからです。また調査結果を受けて質の高いオンボーディングに向けて進めることができます。研修する従業員からもパルスサーベイでフィードバックが受けられるとなお良いでしょう。
メンタルヘルスチェックでの活用
厚生労働省の「『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」によると、従業員が1,000人以上の企業のうち、メンタルヘルスの不調で連続1ヶ月以上休業又は退職した従業員数が10人以上だったのは53.5%。大勢の従業員を抱える企業だからこそ、従業員のメンタルヘルスを守ることは力を入れるべき課題でしょう。パルスサーベイは、メンタルヘルスのチェックに使うことができます。移ろいやすい人間の心理状況を短い期間で何度も実施する性質上、キャッチしやすいのです。「休息が取れている」と回答していた従業員が「ぜんぜん眠れない」というような回答をするようになったら、メンタルケアが必要なサインだと分かるでしょう。しかし、パルスサーベイはあくまで従業員個人の主観。慌ててメンタルケアのための手配をするのは早計です。従業員の働きぶりを見る評価する人材がパルスサーベイ以外のフォローを行うのが良いでしょう。シリコンバレーの有名企業では「1on1ミーティング」が従業員のフォロー方法として使われています。
参照元:平成30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h30-46-50_gaikyo.pdf)
人事評価や人事施策への印象を測れる
パルスサーベイへの回答で、新しい人事評価や制度が従業員にどう受け取られているかが分かります。上下関係が強いタイプの会社では、新しい制度に関して率直な感想が言えない・聞けない環境が出来上がっている可能性も。そうすると制度の問題点や課題が解決されないまま放置されてしまうこともあるでしょう。その悪循環を打破できるのがパルスサーベイです。従業員一人ひとりの意見を汲み取って、悪い箇所を検知。改善してリリースまでをスピーディーに実行可能です。独善的な人事施策を防ぎ、制度や施策の検証ができます。
エンゲージメントサーベイ
従業員が持っている「会社とのつながりの強さ」を把握・改善するための調査が、エンゲージメントサーベイです。従業員が会社や仕事に対してどれだけポジティブな感情を持っているのかを数値化して測定できます。サーベイツールを提供する企業は多種多様です。それぞれに異なる尺度や測定方法を採用しています。今までは組織調査として従業員満足度調査(ESサーベイ)が人事部門主導で実施されてきました。従業員満足度調査(ESサーベイ)は、主に従業員の職場環境への感想や人間関係への満足度を調査するものです。しかし、近年の雇用流動性の高まりによって、離職防止・定着率向上の取り組みが重視されるようになりました。それに伴い、従業員と会社の関係性に焦点を当てた「エンゲージメントサーベイ」が使用されるようになってきたのです。
「エンゲージメント」とは?
英語で「契約」「約束」「関与」を意味する言葉で、特定の対象との「関係性」を意味する言葉です。ビジネスシーンでは、会社と従業員との「関係性とつながりの強さ」「組織に対する共感や愛着」というニュアンスで使われています。学術的には、オランダのユトレヒト大学教授のシャウフェリが「ワーク・エンゲージメント」の概念の提唱者です。
ワーク・エンゲージメントとは「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」と定義され「仕事から活力を得ていきいきとしている(活力)」「仕事に誇りとやりがいを感じている(熱意)」「仕事に熱心に取り組んでいる(没頭)」の3要素で定義されている概念です。
日本のワーク・エンゲージメント研究者である、慶應大学の島津教授によると「エンゲイジメントは、特定の対象、出来事、個人、行動などに向けられた一時的な状態ではなく、仕事に向けられた持続的かつ全般的な感情と認知」と定義されています。このように、エンゲージメントは、企業活動の中でも特に従業員の仕事や会社に対する意欲を示す概念です。エンゲージメントを高めることで離職の防止や優秀な人材の確保、生産性の向上が見込めます。
エンゲージメントサーベイを実施する目的とは?
組織課題を明確にする
エンゲージメントサーベイを実施することで従業員が企業に対してどのような想いがあるのか、心の距離が離れていないかなどの曖昧な部分を数値やグラフで表現できます。定期的にエンゲージメントサーベイが実施できれば、前回の数値との比較が可能です。従業員のモチベーションや企業への帰属意識などの変化を情報として取得できます。前回と今回の間で変更があった制度へのフィードバックとしても機能するでしょう。また、組織課題を明確にするには従業員からの率直な意見が不可欠です。エンゲージメントサーベイに回答してもらう前に目的の説明や回答しやすい環境を整える必要があります。回答者のプライバシー保護を考えるならば、匿名のサーベイとして回答してもらうのも一つの手です。
従業員と企業との課題感のギャップを把握する
エンゲージメントサーベイを実施することで、企業・組織が従業員に期待することが浸透しているかが分かります。逆に、従業員が企業・組織に要求したいことも明らかになるでしょう。この2つが判明することで、企業・組織と従業員の間にあるギャップを認識できます。例えば企業が高い離職率に悩んでいる場合、エンゲージメントサーベイを実施すると、自分から積極的に経営陣への相談ができる従業員だけでなく、普段は不満を言えずにいる従業員からも離職率が高い原因について意見がもらえるかもしれません。企業側が疑問に思っていたことや離職率が高い要因と考えられていたものが、本当に従業員サイドでも問題になっているのかという課題感の答え合わせがサーベイによって出来るでしょう。経営サイドと従業員サイドのギャップが把握でき、そのギャップに対策するための土台が出来るのがポイントです。
集計結果を人事・人間関係の改善に活かす
エンゲージメントサーベイで得られた結果は、人事施策を改善する鍵です。現在、従業員の「モチベーション」「コミュニケーション」「マネジメント」など、どこに不満や疑問があるのかが数値・グラフで分かります。これらの結果を管理職に共有し、管理職が自分のチームに情報共有すること、チームはいかに改善するかの議論を開始。議論される中で従業員は上がってきた問題について企業・組織だけが改善する問題ではないと気づきます。自分たち一人ひとりが解決すべき課題として認識して、対策や改善案を考え始めることでしょう。組織としては調査結果から「1on1ミーティング」「評価制度の見直し・改善」「組織開発」「環境整備」など状況に合わせた施策を打ち出すことが可能です。
エンゲージメントサーベイの注意点
実施目的を明確にする
ツールの導入や実施することが手段ではなく目的にすり替わってしまわないように注意しましょう。改善したい事項があり、サーベイを実施して対策や改善策を立てる流れだったはずが、サーベイの実施までで終わってしまうケースが多々あります。サーベイを実施したことに満足してしまっては、サーベイを実施した意味がありません。エンゲージメントサーベイを実施する前に、実施目的を明確にしましょう。
目的に合わせた質問項目
エンゲージメントサーベイで従業員から何のデータが欲しいのかを明確にしましょう。目的を離職防止とする場合「職場の設備に対する満足度」「所属チームの人間関係」などを質問項目にすると良いでしょう。生産性向上なら「仕事が自分に合っているか」「残業時間・内容は妥当か」「同僚・上司との関係は良好か」などが、確認すべき主なポイントです。目的に応じて質問項目を変えて、エンゲージメントサーベイを実施しましょう。
調査結果を鵜呑みにしない
エンゲージメントサーベイの調査結果はあくまで組織の中で出たものということを忘れないようにしましょう。調査結果をそのまま鵜呑みにして行動すると、実態とズレた対策をしてしまう可能性もあります。離職防止を目的としていた場合、賃金に関して世間や業界の水準も見て対策を考えるべきでしょう。残業時間や人事評価制度に関連しそうなデータを参照し、エンゲージメントサーベイで得られた情報を裏取りすることが大切です。サーベイの調査結果に、関連するデータを合わせることでより効果的な対策や改善を実施できるでしょう。
従業員へのフィードバックを欠かさない
従業員から「エンゲージメントサーベイに答えた意味はあったのか?」と思われると次のサーベイに協力する気が失せてしまうでしょう。サーベイを実施した企業・組織側に不信感を抱くこともありえます。そうならないように、従業員にエンゲージメントサーベイのフィードバックを欠かさず行いましょう。調査結果が出たら従業員に分析結果を分かりやすい形で伝達。企業・組織として問題・課題をどのように改善していくのかというビジョンを共有しましょう。調査結果を社内報に掲載するのもおすすめです。サーベイの結果発表を社内の一体感をつくる材料として活用できるのがベストです。
エンゲージメントサーベイの「質問項目」参考例
Q12(キュートゥエルブ)
米ギャラップ社がアメリカの心理学者フランク・L・シュミット博士と共同で開発したエンゲージメントサーベイの一種です。全世界1,300万人を調査して導き出された「12の質問」を従業員に対して行い、エンゲージメントを測定します。「12の質問」に対して、回答は5つの選択肢「完全にあてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「やや当てはまらない」「完全に当てはまらない」から行います。上から5・4・3・2・1と配点されます。また、「12の質問」への回答の点数を合計して、平均スコアを計算してみましょう。平均点として提示されている得点は「3.6点」です。「3.8点以上」はエンゲージメントが高い、「3.2以下」は要注意と判断されます。
「12の質問」
- Q01.職場で自分が何を期待されているのかを知っている
- Q02.仕事をうまく行うために必要な材料や道具を与えられている
- Q03.職場で最も得意なことをする機会を毎日与えられている
- Q04.この1週間のうちに、よい仕事をしたと認められたり、褒められたりした
- Q05.上司または職場の誰かが、自分をひとりの人間として気にかけてくれている
- Q06.職場の誰かが自分の成長を促してくれる
- Q07.職場で自分の意見が尊重されているようだ
- Q08.会社の使命や目的が、自分の仕事は重要だと感じさせてくれる
- Q09.職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている
- Q10.職場に親友がいる
- Q11.この6カ月のうちに、職場の誰かが自分の進歩について話してくれた
- Q12.この1年のうちに、仕事について学び、成長する機会があった
また、「12の質問」の質問内容は、大きく4つに分類することができます。
- Q01~Q02:仕事をするための基本事項である、動機や環境が整っているか
- Q03~Q06:仕事への貢献度や、周囲にどう評価されているか
- Q07~Q10:「職場」への帰属意識と、同僚への信頼感
- Q11~Q12:「職場」での自身の成長性や、発展への意識
参照元:Q12(キュートゥエルブ)(https://www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx)
参照元:Q12(キュートゥエルブ)の翻訳(https://www.hrbrain.jp/media/human-resources-management/engagesurvey)
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)
エンゲージメント尺度の一つで、国際的に信頼性と妥当性が検証されています。日本では、慶應大学の島津明人教授によって日本へもたらされました。ワーク・エンゲージメントとは「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」のことです。また、ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、ワーク・エンゲージメントの3要素である「活力」「熱意」「没頭」を17問の設問に集約させています。回答することで「仕事に対するエンゲージメント」を測ることが可能です。
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)の設問には、日本語版で17項目と、短縮版の9項目、3項目の3種類があります。商用利用は原著者である、ユトレヒト大学のシャウフェリ教授に許可を得る必要がありますが、研究目的であれば無料で使用可能です。ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、エンゲージメントの考え方の基本です。関連する論文を読めば、エンゲージメントサーベイで質問項目を設定する際の参考として役立つでしょう。
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)の設問例
- 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる
- 自分の仕事に、意義や価値を大いに感じる
- 仕事をしていると、時間がたつのが速い
参照元:島津明人研究室慶應義塾大学総合政策学部(https://web.archive.org/web/20211204054736/https://hp3.jp/tool/uwes)
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)
「自己効力感」を測定する尺度として最も一般的なのが一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)です。自己効力感とは、特定の課題に対して「自分はできる」と感じられる力のこと。GSESではこの「できる」という感覚がどこまで保持されるか測定します。GSESスコアが高い人はポジティブで自信に満ちており、スコアが低い人は自己効力感が低く、劣等感を抱くようになりパフォーマンスが低下している可能性があります。GSESは、元を辿ると精神的なうつ状態を判断することを想定して作られました。そのためスコアが10点未満の被験者には、何らかの抑うつ傾向がみられる可能性があります。組織全体のパフォーマンスを調べるとともに、メンタルに不調を抱えている従業員を見つけることができるエンゲージメントサーベイの測定尺度です。
参照元:一般性セルフ・エフィカシー尺度作成の試み(https://cir.nii.ac.jp/crid/1390564238098775296)
組織診断ツールまとめ
会社や、社員の抱えている課題を可視化できる組織診断ツールを紹介しました。組織診断ツールを活用することで、社員や会社の課題を把握でき、その課題解決に向けて効果的な施策を考えることができます。
課題を解決することで、エンゲージメントの向上を図れたり、離職率を低下させたりすることが可能です。そのため、生産性を向上させることに繋げることができ、会社の成長を促すことができます。
また組織診断ツールの中には、カスタマーサクセスやフォロー体制が整っているツールがあり、サーベイを行うだけでなく、その後のアクションをサポートしてくれます。
自社内だけで課題の解決のための施策を考えることが不安な方でも、安心して導入することができます。
- 免責事項
- 本記事は、2023年6月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。