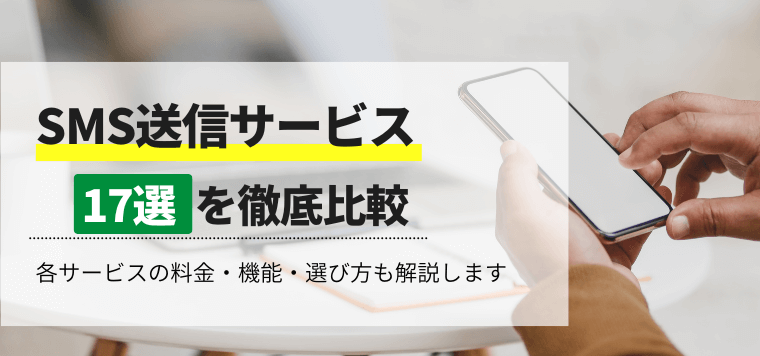物品・備品・資産の管理は企業の必須業務です。備品が行方不明になったり余計な買い物をしたり、棚卸し作業に時間がかかったりという悩みを抱える企業もあるのではないでしょうか?そんな悩みを解決するのが物品管理システムです。
この記事では、備品・物品管理システムの機能や活用方法、選び方を解説します。備品・物品管理システムをピックアップして特徴や料金比較もまとめました。ぜひ自社で導入すべき備品・物品管理システム選びにお役立てください。
備品・物品管理システムの一覧表
ここでは、備品・物品管理に役立つシステムをまとめて紹介します。システム選定は、自社に合うかどうかが大切です。特徴や機能、費用などを調査しましたのでシステム選びにご活用ください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
Colorkrew Biz(カラクルビス)※旧Mamoru Biz |
アプリとQRコードを活用したカンタン管理!外部ツールとの連携もスムーズ
|
MONISTOR(モニスター) |
記録媒体とメディカル資産に特化したバージョンも用意されている |
資産・物品管理システム(吉川システック) |
RFIDによる資産管理。対象物が重なっていたり裏に隠れていたりしてもOK |
OPTiM Asset(オプティムアセット) |
棚卸し計画などをスマホでも簡単に作れる操作性の高いUI |
備品管理クラウド(アストロラボ) |
専任のスタッフによる備品の登録の「丸投げ」代行も依頼可能 |
備品管理システムDX |
市販のデジタルカメラなどで撮影しての管理にも対応 |
ファインアセット |
物品の管理点数で月額費用が決まるシンプルな価格設定 |
Assetment Neo(アセットメントネオ) |
最後までしっかり管理!廃棄業務専用の機能も搭載可能 |
Convi.BASE(コンビベース) |
カスタム管理画面の作成や任意の組み合わせ管理が可能 |
備品・物品管理システムとは?
備品・物品管理システムは、ICタグやバーコード、QRコードなどを物品に貼り付け、一つひとつを管理する仕組みです。物品の位置確認、管理担当者、使用履歴など詳細なデータをシステムで管理できます。
モノが今、どこにどのような状態であるかをリアルタイムで把握可能。物品の利用を最適化でき、無駄を減らすことに役立つシステムです。棚卸し作業では、現物をチェックすることなく簡単に完了できるシステムがたくさんあります。
また、備品の使用ルールが明確になり、私物化がなくなります。内部統制にも役立ちます。
備品・物品管理システムを利用する目的
備品・物品管理システムを利用する目的には、企業や組織が使用する備品・物品の効率的な管理を実現することです。システムを利用することで、現在の在庫状況、必要な数量をリアルタイムで把握できます。これにより、必要な時に必要な量の備品を確保することができ、在庫切れや過剰在庫の問題を防ぎます。
他にも、「誰が」「いつ」「どの備品」を借りているのかを一元管理でき、備品の貸出管理がスムーズに行えます。紛失や返却のトラブルを防ぐこともできます。
さらに、備品や物品の消耗品の管理も効率化され、消耗品の数量や使用状況を追跡することで、必要な時に適切なタイミングで発注や補充を行うことができます。
備品・物品管理システムの種類
備品・物品管理システムにはさまざまな種類があります。以下に代表的な種類を3つ紹介します。
RFID対応型
RFID対応型は、非接触で情報を識別し管理するタイプで、作業効率の向上に役立ちます。RFIDタグを使えば、複数のタグを一括で読み取り、商品の検品や在庫チェックなどの作業がスムーズに行えます。また、出入り口に設置すれば、自動的に読み取ることも可能で、スマホやハンディターミナルを使わずに効率化が図れます。
QR/バーコード対応型
QR/バーコード対応型は、備品や物品の数が多くない場合に適しているシステム。、簡単にラベルを作成できるため、RFID対応型よりも導入費用を抑えられるメリットがあります。読み取る際には、ハンディターミナルやスマホが使用できますので、わざわざ専用端末を用意する必要もありません。
業界業種特化型
業界業種特化型は、その業界に合わせた開発されたシステム。その一例に医療業界向けシステムがあります。通常の物品管理とは違い、医療用品の場合、使用期限、履歴、欠品情報を正確に管理しなければなりません。医療業界向けの代表的なシステムの一つに「MedicalStream」があります。使用した特定診療材料が電子カルテシステムや医事会計システムに登録されているかをチェックする機能などを搭載しています。
備品・物品管理システムの導入メリット
備品データが理解しやすい
備品・物品管理システムを導入すると、備品データが見やすくなります。これまでは、エクセルなどで一覧表を作成して管理する方法が一般的でした。
エクセルは手入力が必要なため、管理が面倒で、データもいい加減なものになりがちです。システムを導入すれば、タグなどを読み取るだけで簡単に管理でき、詳細な情報が紐づきます。必要に応じて、整理されたデータを確認できるため、誰が使っても見やすいのが特徴です。
使用状況や使用履歴がわかる
現在の使用状況や、使用履歴が瞬時に把握できます。タグやバーコードなどを読み取るだけで管理できるため、決算時期の作業を大幅に削減可能です。備品確認のために日常の業務が滞ることがありません。ユーザーの使い勝手を考えて作られているので、棚卸しだけでなく、備品を使うあらゆるシーンで作業の手間を減らせます。
簡単に管理できるため、使い方のルールが守られるのもメリットのひとつ。システムで管理することで、返却忘れなどがなく、使っていないのに一人の社員のところにずっとあるような事態を防げます。
紛失や盗難が防げる
紛失や盗難、許可のない持出を防ぐことにも役立つでしょう。物品使用を適切なルールで運用すれば、効率的に使用できてコスト削減にも繋がります。また、会計ソフトなど、外部のシステムとの連携ができるシステムも少なくありません。備品データと連携すれば、減価償却の反映も簡単。備品の購入・廃棄の際の支払い管理も連携できます。
備品・物品管理システムが活かせるシーン
棚卸し
大きな活用シーンのひとつが棚卸しです。現物と資料の付け合わせ作業が必要ありません。物品に貼り付けたタグなどを読み込ませるだけで、棚卸しが終わります。離れた場所でも一括で読み取れる仕組みのシステムなら、より簡単に作業が完了。専任の担当者を置く必要もありません。
貸出・返却の管理
レンタル業者もシステムで管理することで業務の工数を大幅に削減できます。貸出と返却を一括管理できるのはもちろん、返却遅延が起きた場合はメールでの通知が可能です。図書館でも活用しやすいでしょう。
医療機器の管理
病院も緊急事態に備えた医療機器の厳密な管理が求められます。薬剤などは使用期限があるため、システムで適切な管理をすればコスト削減にも効果的です。
備品・物品管理システムに搭載されている主な機能
備品・物品管理システムの主な機能には、
- 現品管理
- 貸出管理
- 入出庫管理
- 在庫管理
- 点検管理
などがあります。
現品管理機能
物品をデータ化して管理します。台帳を作成し一元管理が可能。確認したい物品を呼び出せば、リアルタイムで状況が把握できる機能です。使い方は、バーコードやタグを読み取る方法が一般的。写真画像を取り込めるシステムもあります。
貸出管理機能
物品の貸出やリース商材の管理が可能。いつ、誰に、何を貸したのかが瞬時に確認できます。また、返却期日のアラート機能が搭載されているシステムもあり、返却忘れの予防に効果的です。使用履歴の確認をすれば、備品の購入を最適化して無駄なコストを削減できます。
入出庫管理
店頭や倉庫の商品管理機能です。入庫・出庫の際に、バーコードなどをハンディターミナルで読み込み、データベースに登録して管理します。
在庫管理
商品が入庫されてから出庫されるまでの管理を行います。データベース上で在庫が確認できるため、商品の仕入れがスムーズになるでしょう。過去のデータを元に、仕入れ計画を作成できます。
点検管理
物品管理をする際に意外と見落としがちなのは、点検と廃棄です。備品の整備もシステムで管理可能。安全な設備の維持ができます。修理記録が残るので、報告書作成も簡単。廃棄管理機能を活用すれば、消耗品や生鮮食品などの管理がスムーズです。
備品・物品管理システムの料金目安
備品・物品管理システムの料金相場は、月額料金500円~30,000円程度です。初期費用は無料~100,000円程度が相場と考えておくといいでしょう。管理する物品の数によって価格が決まるシステムもあります。
パッケージソフトを購入する場合は小規模なものなら数万円程度です。一方、オーダーメイドソフトを開発してもらうとなれば、開発内容によって高額になります。
オーダーメイドソフトは、自社に合わせて無駄のない機能が搭載されるので、導入後の作業効率は上がるでしょう。費用対効果を考えて導入するシステムを選びたいです。
備品・物品管理システムを導入する際の選び方
- 導入しやすいシステムか
- 既存システムと連携できるか
- 導入後のサポートは充実しているか
導入しやすいシステムか
新しくシステムを導入する際は、導入時の混乱も考えられます。導入がスムーズにいかないと、結局使わず既存の方法で継続することになりかねません。導入しやすいシステムかどうかは、最初にチェックするべき事項と言えます。
たとえば、業種ごとにテンプレートが用意されていると、導入してすぐに使いやすい状態が構築できるでしょう。テンプレートを自社フローに合わせてカスタマイズできるシステムが導入しやすいです。
また、物品管理システムには、クラウド型とインストール型があります。
- クラウド型…ネット環境さえあれば、PCやスマホを使ってどこからでもアクセス可能。
- インストール型…オフラインで使用でき、ネット回線の影響を受けることがない。ランニングコストも抑えられる。
システムを導入する際には、導入シミュレーションした上で「クラウド型」か「インストール型」かを選択しましょう。
既存システムと連携できるか
自社で使用している会計システムなど、既存システムとの連携も確認してください。物品管理システムだけが孤立してしまうと、せっかくシステムを導入しても、データの移動に手間がかかってしまいます。
たとえば、会計システムと連携させられると、物品管理システムからの財務管理や必要書類作成が可能です。そのデータが会計システムとも共有されるので、データを手入力する手間が省け、ヒューマンエラーも軽減できます。
既存システムと連携できると、一気に業務負担が削減できるでしょう。どんなシステムと連携できるか確認してください。
導入後のサポートは充実しているか
備品管理システムは、導入してからが本番。実際に使い始めて気づくことも少なくありません。使い方の疑問も生じるでしょう。
こうした疑問に自力で解決する必要があると、業務が滞ってしまいます。結局活用できないということにもなりかねません。
- 研修をしてくれるか
- 分からないことが発生したときにすぐに対応してくれるか
- カスタマイズの相談に乗ってくれるか
など、システム導入後のサポート体制はチェックしておきましょう。
備品・物品管理システム運用する際の注意点
備品・物品管理システムを導入すれば、全ての管理業務が効率化できるわけではありません。システム運用で注意しなければならない点もいくつかあります。
管理する対象物品を決める
所有する全ての機器や備品を管理しようとすると、多大な時間と労力がかかり、管理者に大きな負担を与えます。システムへの物品登録もスムーズに進められません。
まずは、管理する物品を象を絞り、小規模な管理運用に慣れてから対象を広げることをおすすめします。物品をジャンルごとに分類し、1ジャンルずつ絞り込んで管理すると効果的です。
運用ルールをスタッフに周知させる
備品・物品管理システムの導入で、これまでの管理業務のフローが変更される可能性があり、現行のルールでは対応できない場合が想定されます。そのため、新たな管理のルールやシステム運用に関するマニュアルを作成することが重要です。
マニュアルは、備品管理業務の担当者や物品管理システムの管理者だけでなく、全社員に対して周知する必要があります。
備品・物品管理システムでよくある質問
Q1.備品・物品管理システムを導入する際の選び方について教えてください
「導入しやすいシステムか」「既存システムと連携できるか」「導入後のサポートは充実しているか」の観点で選びましょう。また、システムにはクラウド型とインストール型があります。現在の業務内容と照らし合わせながら、導入シミュレーションした上で選択してください。その他、詳しくは「備品・物品管理システムを導入する際の選び方」をご覧ください。
Q2.備品・物品管理システムにはどんな機能が備わっていますか?
備品・物品管理システムの主な機能には、備品や物品をデータで管理できる「現品管理」や、いつ・誰に・何を貸したのかが瞬時に把握できる「貸出管理」などがあります。その他にも、入出庫管理や在庫管理」といった機能も搭載されています。より詳しくは「備品・物品管理システムに搭載されている主な機能」をご一読ください。
本記事のまとめ
備品・物品管理システムについて紹介してきました。一言でいっても提供できるサービスが異なりますので、自社が必要とするシステムはどこかを吟味した上で判断しましょう。
- 免責事項
- 本記事は、2022年12月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。