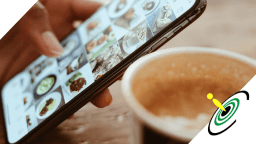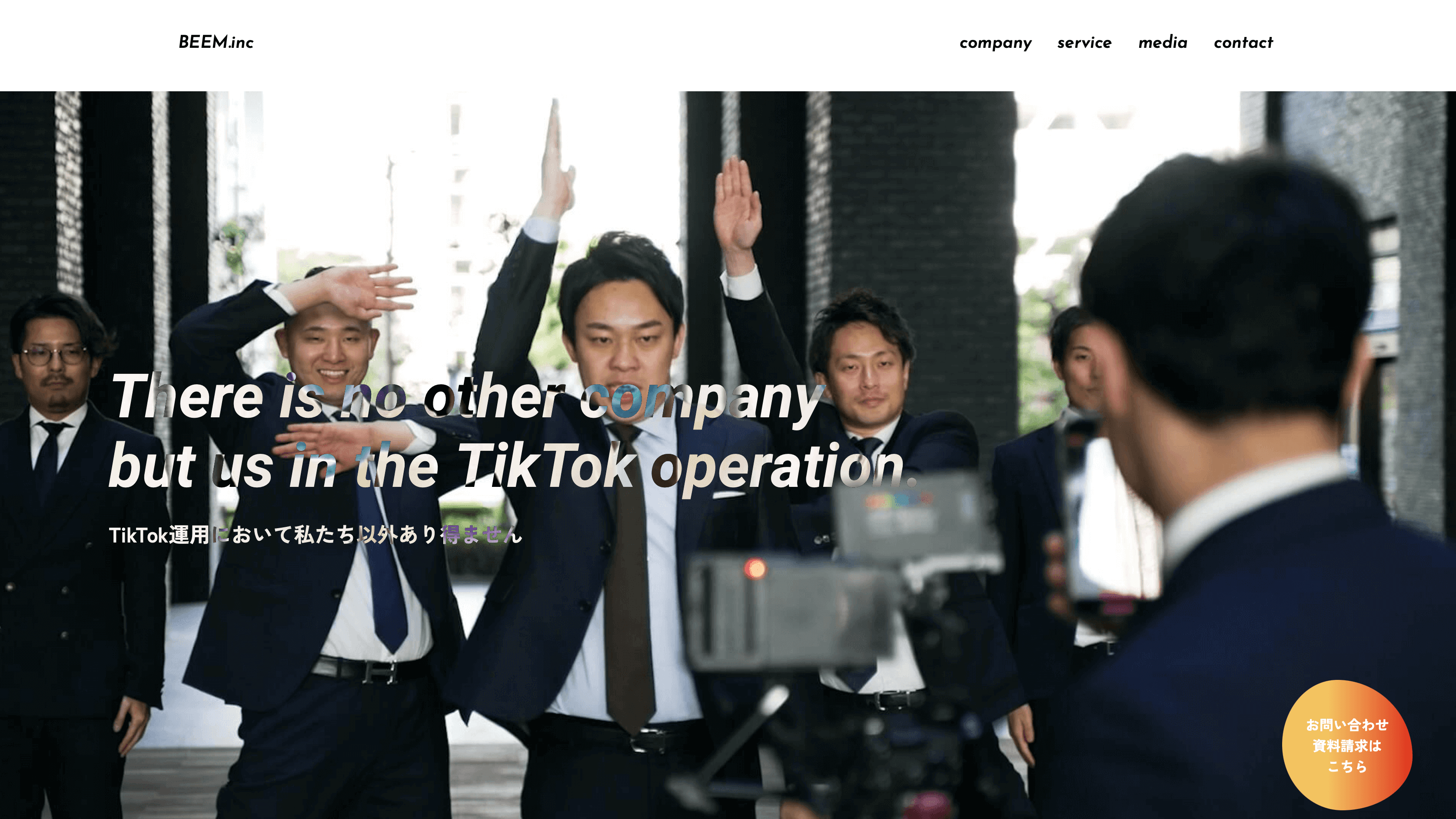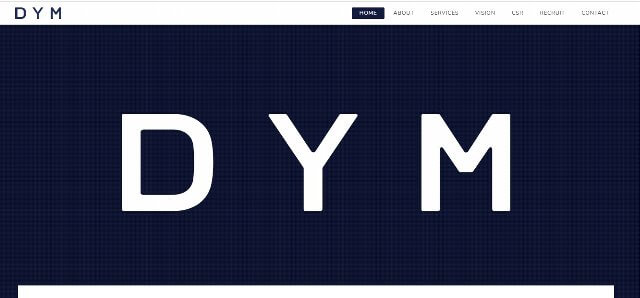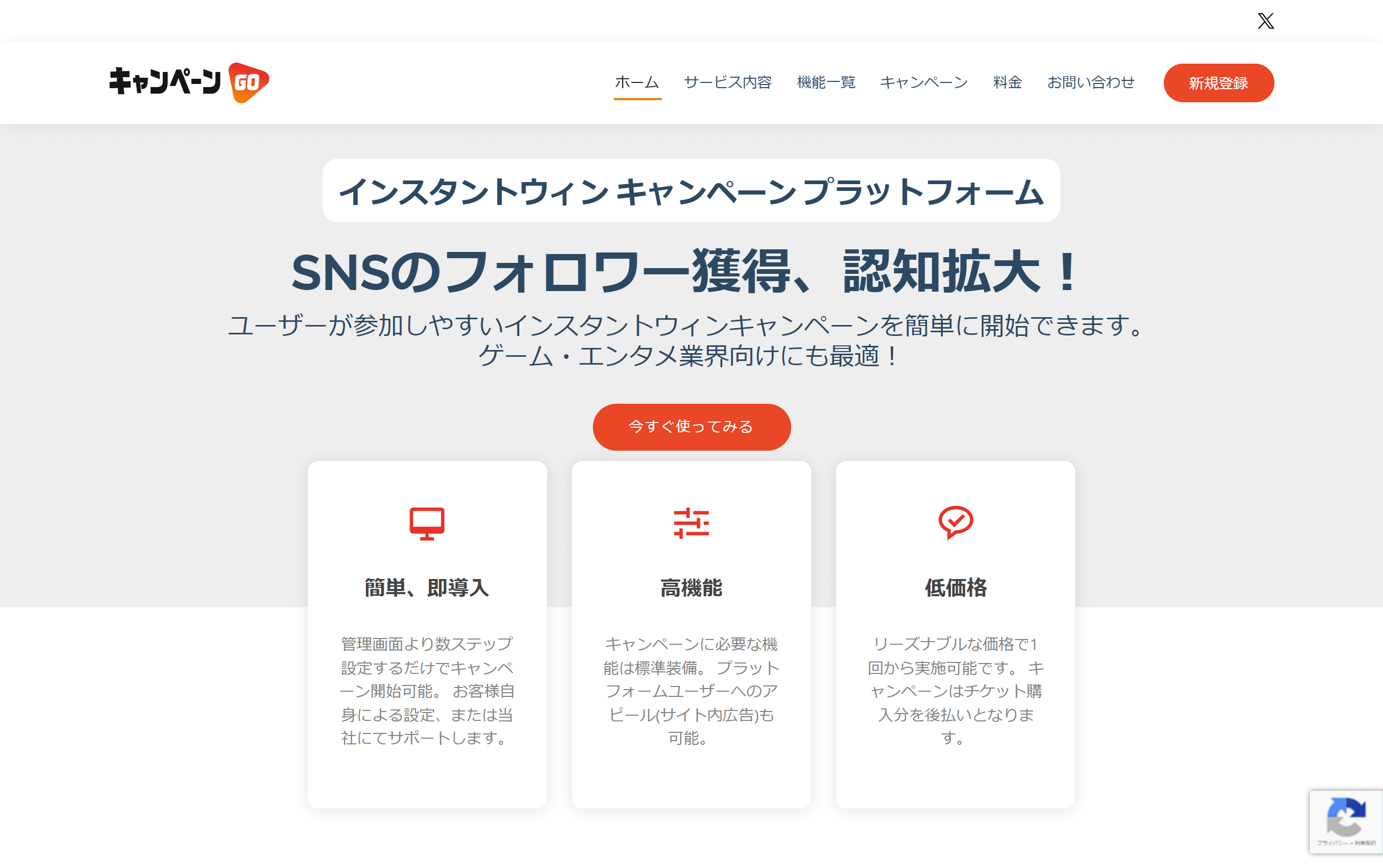誰でも気軽にはじめられるうえ、拡散力を持つSNSは、認知度アップや集客のために企業でアカウントを運用するケースも多く見られます。一方で、不適切な表現を発信してしまうと、それが「炎上」してしまうことも少なくありません。
この記事では、企業におけるSNS炎上の原因や背景、実際の炎上事例を学びながら、SNSの炎上リスクを減らす対策や炎上対策を専門で行っている炎上対策会社を紹介いたします。
企業のSNSアカウントを運用している方やこれから運用される方は、万が一の炎上に備えるためにも、しっかりと知識を身につけておきましょう。
SNSで炎上した場合に対策してくれる企業一覧表
ここでは、SNSで炎上した場合に対策してくれるおすすめの企業を紹介します。大手上場企業や官公庁の実績が高い会社もあれば、金融に関わる企業や福祉業界において実績多数な企業もあり、その特徴もさまざまです。自社が依頼したい内容を検討しながら適切な企業選びにお役立てください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
ミマモルン ‐ Mimamorn |
初期費用0円、月額費用5万円~!低コストで始められるSNS炎上モニタリング・コンサルサービス
|
エルテス |
大手資本で検索エンジンの評判対策をサービス化した企業が提供 |
アディッシュ |
24時間・365日のネット監視サービスを提供 |
ソルフェリオーナ |
金融に関わる企業や福祉業界において実績多数 |
シエンプレ |
大手上場企業や官公庁など6,000社・団体以上の導入事例 |
ジールコミュニケーションズ |
SNSモニタリングの炎上対策で3,600社以上をリスク管理 |
ソルナ |
内閣府認証協会認定の資格を持ったプロによる炎上対策 |
大日本印刷 |
印刷・出版などの一環でSNS炎上監視サービスも提供 |
リリーフサイン |
自動車メーカーや大手食品メーカーなど実績多数 |
企業で起こり得るSNS炎上とは
企業のSNS炎上とは、企業の発言や不祥事がきっかけとなって、SNS上で批判や避難が殺到することです。投稿を見たユーザーが一気に話題にする、SNS内外へ拡散する、ネットニュースに転載されるなどで、批判や避難が広まります。
そもそも「炎上」とは、ネット上で非難が殺到することを指すもの。ただ、多くの個人がSNSを利用している現代では、炎上のほとんどがSNSで発生します。
炎上してマスメディアに取り上げられるようになると、SNSユーザーではない人や世間一般にもさらに広まってしまうため、未然の炎上防止や早期沈静化が必要です。
どんな時にSNSで炎上が起こるのか
企業のSNSが炎上する主な原因には、以下のようなことが考えられます。
- 企業の不正や不祥事
- ユーザーからのSNSを通したクレーム
- 従業員による悪ふざけ・SNS内外での言動
- 悪意のある発言・人をだます嘘の発信
匿名性が高く、何でも自由に発言できるSNSでは、悪い投稿は広まりやすく、表現が過激になったり誹謗中傷が殺到したりしやすい特性を持っています。
中には、たった1人のユーザーが発信した好意的ではない内容やクレームによって、別のユーザーが「自分も同じような目に遭った」などと投稿し、炎上の輪が広がる事例もあるのです。
企業の不祥事や従業員の悪ふざけに対して企業のSNSが炎上するパターンはテレビニュースなどでも報道されますが、自社に何ら落ち度がないのに炎上してしまうケースもあるため注意が必要です。
悪意のある発言で特定のユーザーを批判する、嘘の情報でSNS上のユーザーをだましてわざと炎上を起こすケースもあります。
なぜ炎上が起こっているのかを当事者自身が見極め、内容によっては公式に説明しなおす、事実無根であると訴えるなど、炎上内容に対し何らかの手を打たなくてはなりません。
また、過度な正義感による批判や、1つの言動に対する過敏な反応も増えています。SNSではたったひと言の発言でも、十分に気を配る必要があるのです。
企業がSNSで炎上すると想定される事態
企業がSNSで炎上すると、以下のような事態を招く恐れがあります。
- 企業ブランドの毀損
- 経営への悪影響
- 信用の失墜
いったん炎上してしまうと収めることが難しく、企業のイメージダウンや顧客離れに繋がってしまいます。風評被害によって経営状態が悪化するケースもあるので、放置しないで早めに対処することが大切です。
また、SNSは拡散性が高いため、誤った書き込みであっても情報がすぐに広まってしまいます。多くのSNSユーザーは情報の信ぴょう性について深く考えずに拡散させてしまうため、内容次第では企業の信用失墜が起きかねません。
経営に大きな影響を与える可能性が高いため、SNS運用の担当者だけに炎上対策を任せるのではなく、経営者層を含めた企業全体で取り組むことが大切です。
企業におけるSNS炎上の事例
ここでは、実際に起こった企業のSNS炎上の事例の一部を紹介します。
不謹慎な発言:ウォルトディズニー
ディズニーの映画作品になぞらえて「何でもない日おめでとう」と投稿したのですが、その日が8月9日の原爆の日だったことから、「不謹慎」「無神経」という声が殺到。ディズニーは投稿を削除し、公式サイト上で謝罪する対応を行いました。
個人への不適切なコメント:楽天トラベル
楽天トラベルの公式Twitterアカウントから、あるアーティストに「ぶさいく」というコメントが誤送信され、多くのユーザーがリツイートで拡散したために炎上に発展しました。
楽天トラベルは投稿を削除し、ツイートされたアーティストに対し謝罪。さらに「弊社の見解を示すものではありません。このようなツイートが発生した経緯を調査しています。」と対応しています。
不適切なハッシュタグ:ドン・キホーテ
ディスカウントショップのドン・キホーテが「#みんなはドンキで何盗んだことある?」というハッシュタグをつけたネタ投稿を行いました。
ハッシュタグには「#これは大喜利です」と追加のキーワードがつけられていましたが、企業アカウントの投稿としては不適切だとして炎上しました。
薬事法・景品表示法違反とステマ:FUJIMI
サプリメントを販売するFUJIMIは、本来効能を謳ってはいけないサプリメントにも関わらず、Instagramで「乾燥知らずのうるおい肌へ」と投稿して炎上しました。
FUJIMIを薦めるインフルエンサーも同じような表現をしていたため、「ステマ」としてさらに炎上を招いています。
SNSの炎上リスクを減らす対策
ここでは、SNSの炎上リスクを減らすための代表的な対策を紹介します。
SNSリスクを理解する研修を開催する
SNS炎上のリスクや、炎上の怖さ、企業に起こり得る事態を理解するための社員向けの研修を行うことで、炎上の抑止に繋がります。管理職や社員はもちろん、アルバイトやパートなど、階層や働き方に合わせた全従業員への研修が必要です。
SNSアカウントのルールを決める
従業員がSNSで不適切な発信をしない、言動を起こさないようSNSアカウントのルールを策定することも大切です。SNSとの関わり方を具体的に定義しておくことで、炎上抑止に繋がります。
重要な情報のやり取りをしない
SNSの企業アカウントから秘密や情報が漏えいしてしまった場合、担当者や管理者の責任になるだけでなく、損害賠償に発展する恐れもあります。
SNSで重要な情報のやり取りを一切行ってはなりません。すべてが公になるツールというのを改めて意識する必要があります。
事実かどうか不確かなものは発信しない
例えその情報に確信があったとしても、事実かどうか不確かなことを発信するのは避けましょう。特に医療や法律など、他者の利害に関わる情報は慎重に取り扱わなくてはなりません。
リスク発生時の危機対応フローを構築する
炎上の火種を発見した、万が一炎上してしまった場合、適切な対応が取れるようフローを構築しておくことが必要です。
報告フローや炎上発生時の対応マニュアルを作っておくことで、迅速な対応ができ、被害を最小限に抑えられるようになります。
他人のプライバシーや個人情報を発信しない
人物を特定できる可能性のある情報は発信しないように気を配りましょう。「誰かをどこかで見た」なども、他人のプライバシーに関する情報です。
また、発信のたびに公開範囲や送信先を確認するのも怠ってはなりません。 相手がなりすましアカウントである危険性もあるため、個人へ情報を送る際には特に注意が必要です。
SNSの炎上リスクを理解した上で十分な対策を
誰でも気軽に始められるSNSは、企業でアカウントを運用するケースも非常に増えています。無料な上、簡単に公開できる一方で、リスクも潜んでいることを理解すべきです。
もしも炎上してしまった場合、その対応次第では被害を最小限に抑えることもできれば、さらに炎上してしまうこともあります。今回の記事で知ったことを活かして、十分に注意した上で運用を行いましょう。
自社のターゲットをしっかり見据えた上で、それに合わせたリスク対策を行いながら、万一の際には適切な対処を施すことが大切です。
- 免責事項
- 本記事は、2022年8月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。