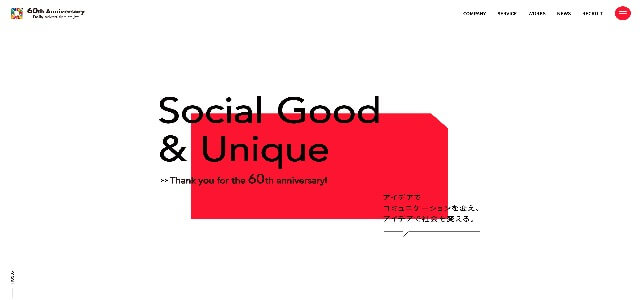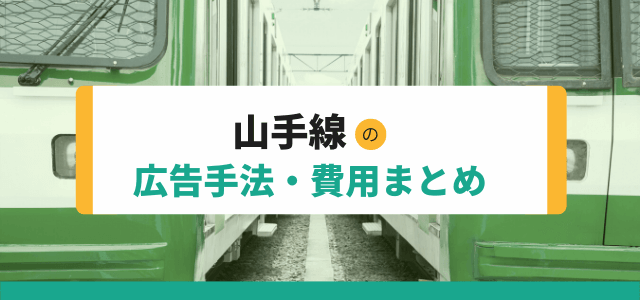電車内広告とは、車両内にポスターやステッカーを貼ることで自社の商品やサービスをアピールできる広告媒体の1つです。視認性が高く乗車客に反復的に訴求できることから、費用対効果の高い広告といえます。
一方で電車内の他の広告との差別化がしづらいこともあり、どれだけ話題性を持たられるかがポイントとなります。
本記事では、電車内広告を扱う代理店とその特徴をまとめて紹介。電車内広告にはどのような種類があるのか、費用はどのくらいかかるのかについても解説しているので、広告会社を探している企業はぜひご覧ください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
デイリースポーツ案内広告社 |
1車両を自社広告でジャック!月々約2万円から導入できるリーズナブルな料金設定
|
オリコム |
独立系広告会社ならではのニュートラルな立場で宣伝が可能 |
ニューアド社 |
制作部門完備で企画から掲出までをワンストップで対応 |
鉄道広告社 |
効果の出る広告展開のプランニングに注力 |
遠州鉄道 |
静岡県西部で予算を抑えた電車内広告の掲出ができる |
アド南海 |
利用者の多い南海鉄道ならではの戦略的アプローチが可能 |
春光社 |
全国の路線で広告制作から掲出までを手がける老舗代理店 |
ムサシノ広告社 |
市場調査から企画・提案、制作までオールインワン対応が可能 |
丸広 |
首都圏エリアの路線で予算や期間に合わせた広告を展開 |
サンエイ企画 |
顔を合わせた打ち合わせで細かいニーズまで応える |
大晃 |
目的や予算に合わせて路線や広告の種類を選べる |
ナウ・ハウ・センター |
車内外すべて含めた広告貸切列車にも対応 |
日本宣交社 |
近畿地方の電鉄で紙・デジタル・特殊素材の広告掲出に対応 |
山陽フレンズ |
選べる出稿期間やセットパックの提供など多彩なプランを用意 |
鉄道広告 |
広島県尾道市を拠点に地域密着型の宣伝活動を実施 |
日広通信社 |
ターケットに合わせた効果的な広告戦略を提案 |
阪急阪神マーケティングソリューションズ |
大阪梅田駅を拠点とする阪急電鉄の交通広告総合代理店 |
電車内広告とは
電車内広告とは、電車の車両内に掲出する広告の総称です。中吊り広告をはじめ、ドア上、ドア横、窓上、各種ステッカーなどいくつかの種類があり、広告の種類によって費用も変わります。昨今では、ディスプレイで表示するデジタルサイネージ広告や、車両すべての広告面を独占展開する貸切広告(トレインジャック)なども注目されています。
電車内広告は視認性が高く、乗客に自然かつ反復的に訴求できることから、費用対効果が高いことも特徴です。企業の知名度を上げたり、新商品の認知度を高めたりしたい場合に、まず検討したい広告媒体といえます。
電車内広告代理店の選び方
電車内広告代理店を選ぶ際は、目的や予算、契約期間などを考慮して総合的に判断すると失敗しにくくなります。まずは、電車内広告でどの場所にどのような広告を出稿したいのかを考えます。広告会社によって対応している広告の種類はさまざまです。中吊りポスター、つり革広告、デジタルサイネージなど、自社の希望に沿った広告を扱っているかを確認しましょう。
また、広告の出稿期間とコストもチェックしておきたいポイントです。どのくらいの期間広告を出稿したいのか、また費用はどの程度かけられるのかについても、あらかじめ検討しておくと良いでしょう。併せて、契約期間の縛りや途中解約の可否なども事前に確認しておくと安心です。
電車内広告の費用相場
電車内広告にかかる費用は、大きく「広告出稿費用」と「手数料や制作にかかる費用」の2つに分けられます。広告出稿費用は広告会社が個別に定めているもので、広告の種類や枚数、掲出期間などによって異なります。公式HPに掲載されている費用はこの「広告出稿費用」であることが多いです。
電車内広告を出稿する際は、その他にも手数料や制作にかかる費用が必要となります。例えば、広告会社に支払う手数料や広告制作費、デザインや企画にかかる費用などがあり、会社によって費用に差が出やすい部分でもあります。広告会社を選ぶ際は、事前に広告出稿費用以外にかかる費用も確認しておくと、予算オーバーを防げるでしょう。
電車内広告のメリット・デメリット
視認性が高く、繰り返し訴求できる
電車内広告は、通勤・通学で電車を利用する乗客に対し、繰り返し視認される点が大きなメリットです。特に中吊り広告やドア横広告は、座席に座っている人や立っている人の目に入りやすく、長時間接触しやすい傾向があります。
また、定期的に同じ路線を利用する乗客には、繰り返し広告が刷り込まれるため、認知度の向上に効果的です。
テレビやインターネット広告のようにスキップされたり、他のコンテンツに埋もれたりすることがないため、メッセージを確実に伝えられる強みがあります。
ターゲットを絞った広告展開が可能
電車の路線ごとに利用者の属性が異なるため、特定のターゲット層に向けた広告展開が可能です。
例えば、ビジネス街を通る路線では、BtoB向けの広告や金融・保険関連の広告が効果的です。大学や専門学校が多いエリアでは、教育関連や就活支援の広告がターゲットに刺さりやすくなります。
また、沿線の特性を活かして、地域密着型の広告を展開することもできます。ターゲット層が明確であれば、広告のクリエイティブやメッセージを最適化しやすく、より高い広告効果を期待できます。
多様な広告フォーマットが利用できる
電車内広告には、中吊り広告、ドア横広告、まど上広告、デジタルサイネージ、つり革広告など、さまざまな種類があります。それぞれの広告フォーマットには特性があり、目的や予算に応じた選択が可能です。
また、デジタルサイネージを活用すれば、動画やアニメーションを駆使したインパクトのある広告展開ができるため、ブランドイメージを強化したい企業にも向いています。
SNSで拡散される可能性がある
ユニークなデザインや話題性のあるキャッチコピーを用いた電車内広告は、乗客が写真を撮影し、SNSで拡散する可能性があります。
特に、つり革広告や車内ステッカーなど、乗客の目線の高さにある広告は、意外性やインパクトのある表現が話題になりやすいです。
近年では、トレインジャック(車両全体を広告でジャックする手法)や、QRコードを活用したキャンペーン型の広告も増えており、デジタル施策との連携によって、さらなる拡散効果を狙うことが可能です。
デメリット
他の広告との競争が激しい
電車内には複数の広告が掲出されており、特に中吊り広告や窓上広告は、乗客の視線が分散しやすい傾向があります。広告が目立たないと、乗客にスルーされる可能性が高くなるため、デザインやコピーに工夫が求められます。
視認性を高めるためには、コントラストの強い色使いや、大胆なレイアウトを採用することが重要です。また、満員電車では広告が隠れてしまうこともあるため、車内のどの位置に掲出するかも戦略的に考える必要があります。
出稿コストがかかる
電車内広告の費用は、路線や広告の種類によって異なるものの、主要都市の人気路線では高額になりがちです。例えば、東京メトロの中吊り広告は1週間で数百万円、デジタルサイネージはさらに高額になる場合があります。
また、トレインジャックのように車両全体を広告で埋め尽くすプランは、費用対効果は高いものの、予算を大きく確保する必要があります。中小企業にとっては、費用面でハードルが高いと感じるケースも少なくありません。
広告効果の測定が難しい
電車内広告は、Web広告のようにクリック数やコンバージョン率をリアルタイムで測定することが難しいため、広告効果の可視化が課題となります。
QRコードを掲載したり、広告を見た人限定のキャンペーンを実施したりすることで、ある程度の効果測定は可能ですが、正確なデータを取るのは容易ではありません。
特に、ブランドイメージ向上を目的とした広告の場合、具体的な成果を数値化しにくいため、効果検証の手法を工夫する必要があります。
掲出期間に制約がある
電車内広告は、一定の掲出期間が決められているため、短期的なプロモーションには向かない場合があります。
キャンペーンやイベントの告知など、短期間で集客したい場合には、別の広告手法と組み合わせる必要があります。
また、契約期間中の内容変更が難しいことも多く、柔軟な運用ができない点がデメリットとして挙げられます。
電車内広告のまとめ
電車内広告は、通勤・通学などの移動時間に自然と視界に入り、繰り返し訴求できるため、ブランド認知の向上に効果的な広告手法です。中吊り広告やドア横広告、デジタルサイネージなど多様なフォーマットがあり、ターゲットや目的に応じた広告展開が可能です。
電車内広告を検討する際は、目的やターゲットに合った広告を選び、適切な代理店を活用することが重要です。本記事を参考に、自社に最適な広告プランを見つけてみてください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年10月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。