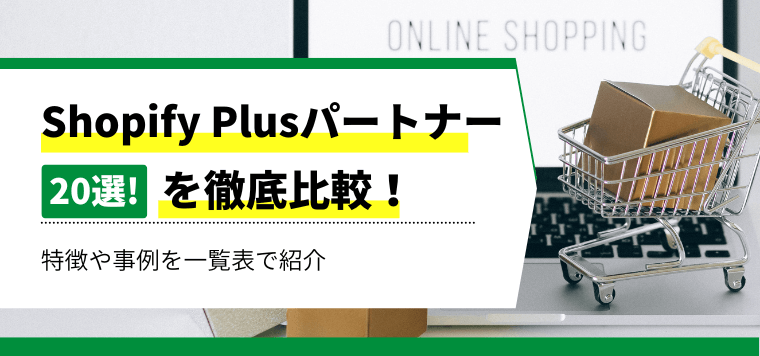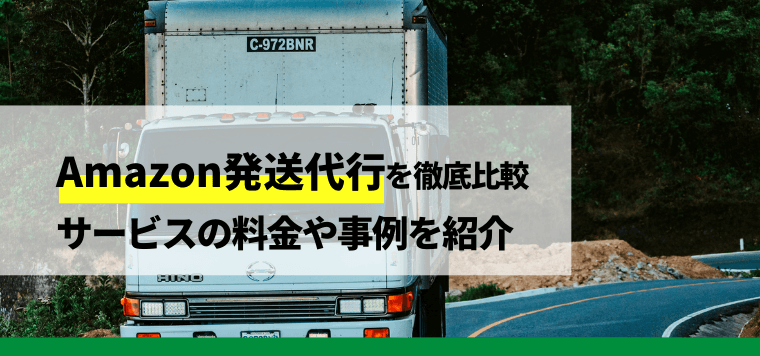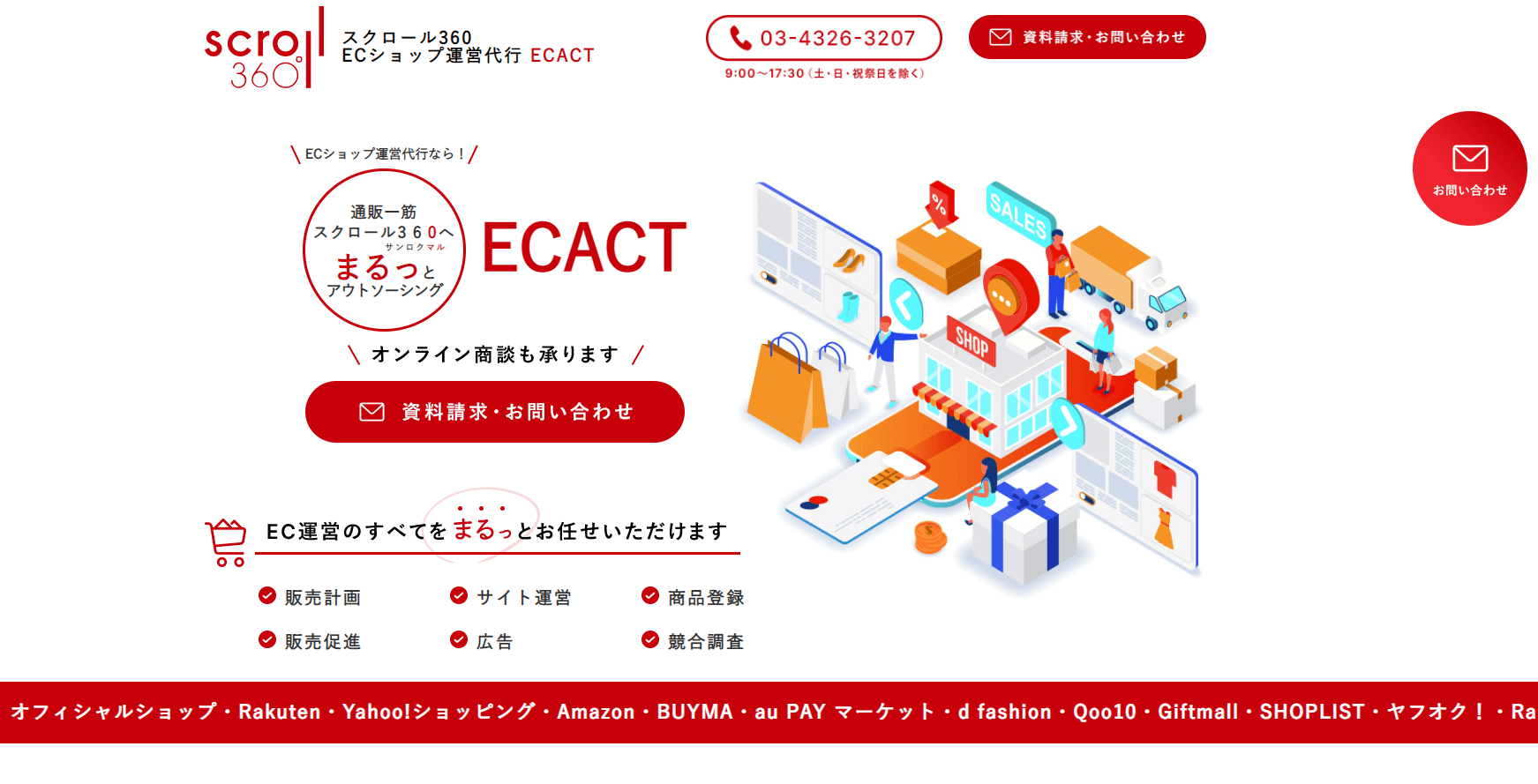定期通販・リピートカートシステムは、リピーターの増加で売上向上や、広告費の削減に役立つものです。
定期通販カートシステムの費用は、安いものであれば月額数千円~。大型システムとなると数十万円と高額になるケースもあります。対応範囲によって費用が異なりますので、比較検討の際は資料ダウンロードでご確認いただくことがおすすめです。
本記事では、定期通販カートシステムの特徴や評判をまとめて徹底比較していますので、定期通販の売上アップにお役立てください。
目的に応じて選ぶ
定期通販カートシステム
定期通販システムの利用経験が浅い企業向け
徹底的な技術活用によって売上を高めたい企業向け
たまごリピート魂
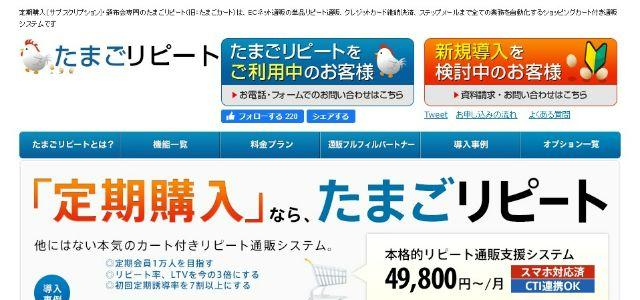
通常の電話・メールでのサポートに加え、プラットフォームユーザーが集うユーザー会も定期的に実施。通常サポートは専任担当制になっています。
メルカート

導入期には初期セットアップやデータ登録などに関するトレーニングを実施。リリース後は専用チーム・ヘルプデスク・カスタマーサクセスチームによる支援を実施。
リピストX

LP一体型フォーム、チャット形式購入フォーム、セット商品の組み合わせを自由に選べる「よりどり販売」など、リピート購入を実現するための機能が数多く搭載されています。
ecforce
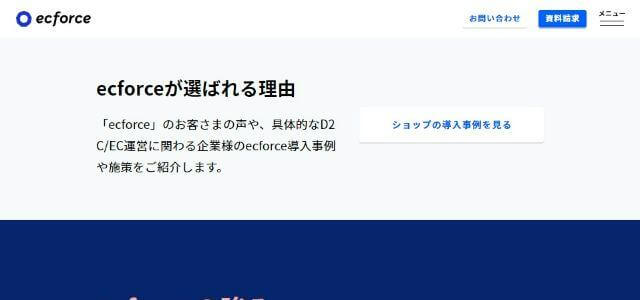
販売管理や顧客管理、受注管理の一般的な機能のほか、チャット型対話式EFOやWeb接客自動化システムなど、集客から顧客育成まで対応できる機能が搭載されています。
定期通販カートシステムの選定ポイントを解説

定期通販に特化したシステムが搭載されている
定期通販はECサイトを構築するだけでなく、定期販売の特徴を踏まえた上で販売戦略を練る必要があります。定期販売に特化したシステムは、定期販売においてどんなことを実現できるのかをしっかり確認しておきましょう。
LTV改善機能がある
定期通販は顧客単価やリピート率を見直すことでLTV(ライフタイムバリュー:取引期間中に顧客から得られる利益総額)が向上し、安定的な売り上げを担保できます。システム側にLTV改善機能があると施策を早期に打つことも容易です。
サポート体制が充実している
初期設定やシステム運用のサポートはもちろん、定期通販独自のトラブルにスピーディーに対応してくれるといった、サポート体制の充実度も選ぶ基準となります。各システムのサポート力は、システム導入数や継続率にも反映されていますので確認することがおすすめです。
定期通販カートシステム23選
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
W2 Repeat(旧:リピートPLUS) |
機能数1,000以上!自由なデザインカスタマイズにも対応している定期通販システム
|
リピストX |
満足度99.8%のサポート |
Shopify |
70種類を超えるWebデザイン(テンプレート)と豊富な機能 |
サブスクストア |
LP一体型フォームを採用した定期通販カートシステム |
楽楽リピート |
リピート通販・D2C特化型カートシステム |
たまごリピート魂 |
見込み客獲得のための自動ツールを搭載 |
ecforce |
一般的な販売管理・顧客管理のほか、Web接客自動化システムなどの技術活用が豊富 |
カラーミーリピート |
10分程度で定期通販・リピート通販ページを制作できるシステム |
STORES |
予約販売・定期販売に対応できるシステム |
イージーマイショップ |
一度の注文で最大100カ所まで送付先を設定可能 |
MakeShop |
定期購入オプションが付けられるECサイト構築サービス |
BASE |
初期費用・月額費用0円からスモールスタート可能 |
おちゃのこネット |
デザインテンプレートでネットショップを簡単作成 |
EC-CUBE |
クラウド版・ダウンロード版の2種類に対応可能な定期通販カートシステム |
Cafe24 |
基本機能自体はリーズナブルな価格で使用可能 |
aishipR |
機能カスタマイズに対応し配送周期・回数・初回~最終販売価格設定の変更が可能 |
らくうるカート |
ネットショップの開業から運用まで使えるサービス |
メルカート |
定期購入機能やギフト購入機能などECサイトにほしい機能が充実 |
侍カート |
ASPプラン・カスタマイズプラン・フルスクラッチプランの3つを用意 |
Smile Tools |
フォーム、メール、分析、LPOの4つのメイン機能 |
Vegas |
ECシステムと基幹システムを一元管理 |
ecbeing |
サイト開発は500名以上、運用支援は200名以上でクライアントを強力サポート |
futureshop |
継続利用店舗の平均成長率は153% |
定期通販カートシステムとは?

定期通販カートシステムとは、定期購入タイプのECサイトを構築・運営できるシステムのことです。お酒・雑貨・ペット用品・飲料・日用品・食品などを顧客に対して定期的に届けている企業の場合、定期通販カートシステムを導入すると、再注文の手間を省きたい、お得に購入したいなどの顧客のニーズにも対応できます。
定期購入へ繋げる仕組みが盛りだくさん
定期通販カートシステムは一般的なカートシステムとは異なり、定期購入率を上げるための機能が多く搭載されています。例えば、商品の配送周期を個別に設定できたり、定期購入へ引き上げるためのステップメール機能が搭載されていたりと、定期購入者を増やす仕組みが整っています。
アップセルは定期通販カートシステム、クロスセルはECカートシステムがおすすめ
定期通販カートシステムは“アップセル”のマーケティング手法を取り入れたい企業に向いています。利用すれば単品購入から定期購入へ引き上げられるほか、無料トライアルから定期購入サービスへ促すことも可能です。
反対に、クロスセルのマーケティング手法を取り入れたい企業、関連商品の提案やオプション提案で売上を伸ばしたい場合には、一般的な通販カートシステム(ECカートシステム)が向いています。
定期通販カートシステムを導入するメリット

ここからは、定期通販カートシステムを導入するメリットを解説していきます。以下のメリットを踏まえたうえで、自社に必要なシステムか否かを判断してみてください。
1.少ないコストで継続的な売上が見込める
定期通販カートシステムを導入するメリットは、少ないコストで継続的な売上が見込めるところにあります。広告で新規顧客を集めて客単価を増加させる手法は、一時は顧客・売上が増加するものの、継続に繋がらないケースが出てきます。
単品購入した際の満足度が高ければ企業イメージが上がり、リピート購入に繋がる可能性もあります。しかしながら、顧客をリピーターへ昇華させる前に、クロスセルで望まないサービスを進めることにより、企業イメージが低下する恐れもあるのです。無理な勧誘により顧客離反が起こる可能性が出てきます。
継続購入へ繋げたい企業は、定期購入へと引き上げる定期通販カートシステムの導入が向いています。
2.営業効率がアップする
定期通販カートシステムを導入すると、営業効率をアップさせられます。新規顧客の獲得は、既存顧客をリピーター昇華よりも約5倍コストがかかると言われています。つまり、新規顧客を獲得する際は、認知されるまでに広告費用がかかるため、既存顧客へ営業をかけるよりも時間と労力が必要です。
定期通販カートシステムの導入で営業効率がアップできれば、他の施策へ予算が回せるようになり、客単価の増加やリピート率の上昇などに期待が持てます。
定期通販カートシステムの種類
これより先は、定期通販カートシステムの種類を5つ取り上げています。定期通販カートシステムの種類について理解を深めて、自社に必要な機能を搭載しているシステムを導入しましょう。
ASP・SaaS型
- 1.参入ハードルが低い
- 2.サーバー設置・ECサイト構築の知識必要なし
- 3.短期間・小コストで始められる
定期通販カートシステムのASP・SaaS型とは、クラウド上のプラットフォームを使用し、ECサイトの構築・運営を行うシステムのことです。サーバーの設置が不要で、ECサイト構築にかける期間・コストを削減できます。既にECサイト構築・運営に必要な基盤が整っているので、デザインや機能を選ぶだけで簡単に運用が始められます。
サーバー設置やECサイト構築の知見がなくとも始められるため、小規模~中規模の企業に向いているシステムです。少ない投資で始めたい個人事業主を中心に人気で、これまで定期通販を行ったことがない企業でも参入のハードルを下げられます。
パッケージ型
- 1.フルスクラッチ>パッケージ>ASP・SaaSで中レベルの導入コストが発生
- 2.デザイン・機能面が充実している
- 3.フォローは手厚いが一定レベルの知識が必要
定期通販カートシステムのパッケージ型とは、ソフトウェアを購入し、自社のECサイトにシステムを組み込むタイプを指します。自社で一から開発するよりも手間を省けるうえに、クラウド上のプラットフォームを利用したシステムよりも、デザイン・機能面が充実しているケースが多いと言えます。
ただし、パッケージ型はASP・SaaS型よりも自由度が高い分、導入コストがかさむ恐れもあるものです。売上がある程度見込める、中~大規模の定期通販を行っている企業に向いています。導入後のフォローが充実していて、ECサイトの構築からサポートしてくれるシステムもありますが、ASP・SaaS型よりもECサイト構築の知識を必要とします。
フルスクラッチ型
- 1.導入・運営にコスト・期間・労力を必要とする
- 2.かなり自由度が高く、希望の形を実現できる
- 3.外注or自社で全て対応する必要があり、知見のある人材と莫大な投資が必要
フルスクラッチ型は、オリジナルの定期通販カートシステムを設計・開発するタイプを指します。ある程度土台が出来ているパッケージやASP・SaaSとは異なって自由度が高く、ニーズや課題に応じたシステムを構築することが可能です。ブランドや企業イメージに合わせた定期通販カートシステムを制作したいなら、フルスクラッチ型が向いています。
ただし、自社でほぼすべての作業を対応しなければならず、不具合発生時・効果測定時は多大な労力・コストを要するので注意が必要です。システム開発会社やサイト制作会社、運営管理代行会社など外部に依頼するケースでも期間やコストがかかるため、資金力のある大企業に向いています。
オープンソース型
- 1.無償のオープンソース利用でコストの削減可能
- 2.カスタマイズやトラブルは自社で対応しなければならない
- 3.ECサイト構築の知識が必要
定期通販カートシステムのオープンソース型とは、無償のソースコードを使用し、システムを構築するタイプのことです。一般公開されているソースコードを使えるため、開発費用を大幅に抑えられます。ただし、カスタマイズは自社で行う必要があり、ECサイト構築の知識を要します。
また、無償で公開されているソースコードを使うため、何か問題が生じた際は自社で全て対応する必要があるので注意が必要です。脆弱性診断を行ったり、バグを見つけたりと、自社で開発する際に手間がかかりますが、できる限りコストを抑えたい企業に向いています。
モール出店型
- 1.ECモールの知名度を利用して集客できる
- 2.出店の手間・時間・コストを削減できる
- 3.手数料が発生&価格競争が起きやすい
定期通販カートシステムのモール出店型とは、既に出来上がっているECモールへ出店する方法です。既存のECモールに一店として出店するので、手軽に導入ができ、短期間で商品の販売を開始できます。知名度があるECモールを使用すれば、自社やブランドの知名度が低くても集客できる可能性があります。
ただし、ECモールに競合他社が多く出店しており、価格競争が起こるケースも少なくありません。自社の商品が差別化できなければ、価格競争に負ける恐れがあります。また、売上毎に手数料が発生するので、ある程度売上が見込める企業でないと継続利用が難しくなります。
定期通販カートシステムの主な機能

定期通販カートシステムの機能を7つ解説していきます。以下の機能が自社に必要かどうかをよく考えて、自社に合ったシステムを選定しましょう。予算が限られている企業は、最低限自社に必要な機能を見極めたうえで、予算に合ったシステムを導入することをおすすめします。
アップセル
アップセルとは、定期購入へ引き上げるポップアップを表示させたり、カートへ入れた商品の上位商品や定期購入を紹介したりする機能のことです。単品購入や無料トライアルを利用する顧客を、より高額な商品へと引き上げることで、売上向上・継続利用へと繋げます。
機能によっては、定期購入の周期を細かく設定できるケースもあります。顧客によって購入周期が異なる商品を販売する場合は、購入周期を調整できる機能を搭載している定期通販カートシステムを選定することが大切です。
クロスセル
クロスセルとは、関連商品を表示させる機能のことです。取り扱っている商品が多い場合は、クロスセル機能を搭載している定期通販カートシステムを選定すると、客単価の向上が図れます。
ただし、関連性の低い商品が表示されたり、別の商品表示により使いにくいと判断されたりすると、顧客離反が起こる可能性があることを頭に留めておきましょう。
ステップメール
ステップメールとは、定期購入へと引き上げるためのメール配信ができる機能のことです。属性や商品などでターゲティングをしてメール配信ができるので、広告費をかけずにリピーターへと昇華できる可能性があります。
製品の無料トライアルを提供している企業は、ステップメール機能が搭載されている定期通販カートシステムを選定すると便利です。
商品同梱
商品同梱とは、配送時にカタログ・サンプルなどを同梱できる機能のことです。例えば無料トライアルを頼んだ顧客向けに、定期購入者の声を載せたチラシを入れたり、定期購入へ申込む際のクーポンを同梱したりと、施策に活用できます。
後日カタログを送付するよりも配送コストを抑えられるので、カタログやサンプルの同梱を検討している企業は、同梱機能が付いている定期通販カートシステムが向いています。
分析
定期商品への引き上げ率や、定期購入者の属性や金額を分析したいなら、分析機能が搭載されている定期通販カートシステムを選ぶことがおすすめです。
分析機能といってもピンキリで、顧客属性・購入金額・定期購入への引き上げ率を分析できるものから、広告媒体別に成約率が分かるものまで様々あります。自社が分析したい項目を網羅できるシステムを選定してください。
バックオフィス機能
バックオフィス機能は、定期通販カートシステムを運営するのに必要な機能のことです。例えば、顧客の受注や商品在庫管理、顧客管理ができる機能などが挙げられます。システムによっては、各種決済サービスや配送サービスが利用できるケースもあります。
多くの決済サービスに対応している定期通販カートシステムを選ぶと、利便性が向上して、顧客がカゴ落ちするのを未然に防げるのが利点です。業務効率化を図りたい企業は、バックオフィス機能が充実している定期通販カートシステムを選ぶのがおすすめです。
フロント機能
フロント機能は、売上を向上させるために必要な機能のことです。上述した顧客管理や分析機能、ステップメール機能などはフロント機能に含まれています。
リピーター獲得や定期購入への引き上げのために活用できる機能なので、継続率を向上させたい企業はフロント機能の有無を確認しましょう。サンクスメールやクーポン配信がスムーズに行える定期通販カートシステムを選定すると、定期購入への引き上げ時の営業効率が向上します。
定期通販カートシステムの選び方
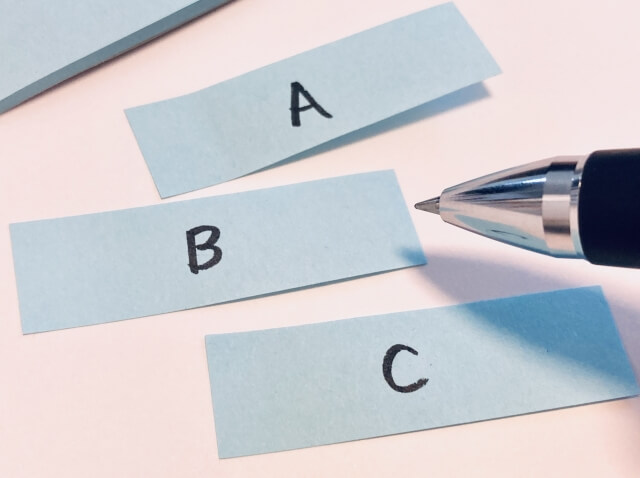
定期通販カートシステムの選び方を解説しています。以下の5点に気をつけて、システムを選定してみてください。
業界(BtoB・BtoC)
定期通販カートシステムには、BtoB型・BtoC型の2タイプがあります。企業向けに商品を販売するならBtoB向けのシステムを選択し、一般顧客に向けて商品を販売するならBtoC向けのシステムを選定することが大切です。
機能・カスタマイズ性
定期通販カートシステムは、ほぼ仕様が決まっているASP型、少し独自性を出せるパッケージ型、自由に仕様を変えられるフルスクラッチ型があります。システムを選定する際は、予算・スタッフの能力を考慮して、自社に合ったものを導入してください。決まった型から選びたい場合は、ASP型やパッケージ型を選ぶと、スムーズに制作できます。
料金設定
定期通販カートシステムの料金設定は提供企業によって異なっており、キャッシュレス決済手数料のみかかるものや、月額固定費用とキャッシュレス決済手数料がかかるもの、月額固定費用と初期費用とキャッシュレス決済手数料がかかるものと様々です。予算と望む機能を明確にしておくと、システム選定が楽になります。
決済手段
決済手段は定期通販カートシステムによって色々で、クレジットカード決済・電子マネー決済・携帯キャリア決済・後払い・銀行振込・コンビニ決済など多岐にわたります。選べる決済方法が多いほど集客力が上がりますが、費用が高くなる恐れもあるため、予算と外せない決済手段を考慮してシステムを選定しましょう。
セキュリティ
顧客情報を扱う以上、セキュリティ対策が必要です。特に、リピーター機能などを搭載しており、クレジットカード情報を預かるサービスを提供しているシステムは、セキュリティ対策がどうなっているかを確認してください。
定期通販カートシステムに関するQ&A

Q1.定期通販向けカートシステムの導入パターンは?
カートシステムのサイト構築機能ですべて構築
定期通販カートシステムのサイト構築機能を活用して、通販サイトを一から構築する方法です。
メリットとして、ECサイトの運営を1つのサイトで完結できる、カスタマイズ性も高く、ブランドの要件に合わせてデザインや機能を調整できるといった点が挙げられます。
ただし、デメリットとして、自社でサイト構築を行うため、時間と労力が求められます。
LPのみで構築
2つ目はランディングページ(LP)を用いた方法です。LPの下部に入力フォームを設置してページ遷移をさせることなく決済完了することができます。
LPのみで構築するメリットは、迅速に市場投入できることと、特定の商品やサービスに焦点を当てたプロモーションが可能であることです。また、低コストで定期通販カートシステムを導入できます。
一方で、LPのみでは顧客の信頼性やブランドの安心感を損なう可能性もあるため慎重に判断する必要があります。
CMSと連携して構築
最後の導入パターンは、CMSとカートシステムを連携させて通販サイトを構築する方法です。この方法は、コンテンツと通販を統合的に運営したい場合に適しています。
CMSと連携する利点は、コンテンツと商品情報を一元管理できることと、カスタマイズ性が高いことです。
ただし、カートシステムとの連携には一定の専門的な知識や技術が必要となり、カスタマイズに一定の制約が生じることもあります。
導入パターンを選択する際には、ビジネスニーズや戦略に合わせて検討し、最適な定期通販カートシステム導入方法を見つけましょう。
まとめ

定期通販カートシステムと一口にいっても様々で、テンプレートから選択する操作性に特化したタイプから、自由に構築できる独自性に特化したタイプまであります。自社が予算・操作性・独自性・機能性の何を重視しているかをよく考えて、必要な条件を満たしているシステムを選定してください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年1月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。