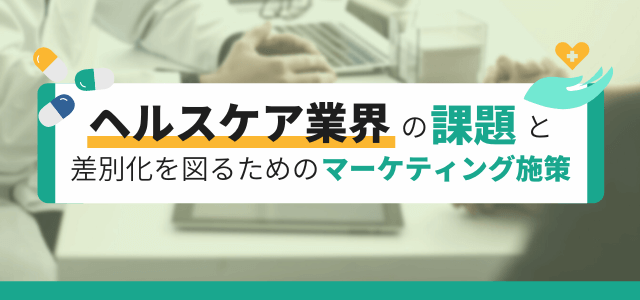作業員が転倒や熱中症のリスクにさらされる場面は多く、夜間や少人数シフトではさらに発見が遅れがちです。ここでは、遠隔でのモニタリングやAIによる異常検知機能など、様々な仕組みが備わった見守りシステムを紹介します。自社に合った導入ポイントや選定方法についても解説しているので、最後まで記事を読んでいただき事故を未然に防ぐヒントを見つけてください。
作業員見守りシステムの一覧
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
ワーカーコネクト |
手間なく始めるIoT見守り。多彩な通信方式で遠くまでつながる
|
DecoBull |
ヘルメットでも手首でも装着OK。仲間との連携で異常を見逃さない。 |
安全見守りくん |
映像×センサーで、リアルタイムに作業現場を視える化 |
労働安全衛生 作業員活動支援サービス |
データ集約と可視化で、広範囲な事故予防と安全対策をサポート |
MAMORINU |
スマートウォッチ1台で業務改善と安全管理を同時に |
作業者安全モニタリングシステム |
ヘルメット装着型で精度の高い異常検知。過酷な現場向け安心ソリューション |
みまもりがじゅ丸® |
リストバンド型で手軽に導入。リアルタイム脈拍監視で異常を素早く察知 |
Work Mate |
スマートウォッチが作業者のパルスを学習。個人最適な安全管理を実現 |
アイフォーコム・スマートエコロジー |
カスタマイズ自由度の高い見守りソリューション。ガス検知・水没検知も一括管理 |
SAFEMO安全見守りクラウドサービス |
4GかBluetoothか、自由に選べるウェアラブル端末で作業員を守る |
作業員見守りシステムとは?

作業員見守りシステムとは、作業現場で発生する可能性のある事故やトラブルに対し、迅速かつ適切な対応を行うためのシステムの総称です。このシステムを活用することで、作業員の状態や位置情報をリアルタイムで把握し、安全管理を強化することが可能になります。
特に、建設業・製造業・プラント・運送業など、危険を伴う作業環境では、転倒や転落、機械への巻き込まれ、熱中症といった予期せぬ事故が発生するリスクが高くなります。そのため、万が一の事態が発生した際に、いかに早く異常を検知し、適切な処置を講じるかは、作業員一人ひとりの安全確保だけでなく、企業の責任や信頼の維持にも直結する重要な課題といえます。
従来の安全対策は、巡回や監視カメラなどアナログな手法が主流でした。しかし、近年ではICT(情報通信技術)の発展により、ウェアラブルデバイスの進化、高性能カメラの普及、リアルタイム通信技術の向上が進み、より高度で精密な見守りが実現可能になっています。
たとえば、作業員が着用する小型トラッカーや腕時計型の端末を用いれば、心拍数や体温といったバイタルデータをクラウド上で一括管理することができます。このようなシステムでは、作業員の心拍数の急上昇や転倒を検知すると、管理者に自動でアラートが送信されるため、異常発生時の対応が迅速化されます。さらに、本人が異常を自覚していない段階でも体調の変化を察知できるため、事故を未然に防ぐ仕組みを整えることが可能になります。
また、GPSやビーコンなどの位置情報技術を活用することで、広範囲の作業現場において作業員の正確な位置を把握できるようになります。特に、工場やプラント、トンネル建設現場など、入り組んだ構造のエリアでは、作業員の所在が不明になった際に迅速に特定できることが大きなメリットとなります。これにより、緊急時の救助にかかる時間を短縮し、重大事故のリスクを軽減することが可能となります。
さらに、作業員見守りシステムは、労務管理の分野でも注目を集めています。クラウド上の管理画面を通じて、誰がいつどの現場で作業しているのかをリアルタイムで確認できるため、稼働状況の可視化や、残業時間・連続稼働時間の管理が容易になります。これにより、作業員の健康管理を強化するとともに、コンプライアンスリスクの低減や生産性向上にも貢献できるのです。
作業員見守りシステムのメリット・デメリット
メリット
安全性の向上とリスク低減
リアルタイムに作業員のバイタルデータや位置情報を把握できるため、万が一の事故発生時にも素早く異常を検知し、適切な救護ができます。これにより重篤化を防ぎ、人命を守ることが最優先でありながら、企業としてのリスクや社会的責任を大きく軽減できます。
作業効率の向上
作業員がどこで何をしているかを正確に把握できるため、現場の動線を最適化したり、必要な資機材の配置を効率化したりできます。無駄な移動や待機を減らすことで、全体的な作業効率アップに繋がり、生産性向上が期待できます。
労務管理の精度向上
個々の作業員の稼働時間や休憩時間を正確に取得できるため、勤怠管理や残業の把握がしやすくなります。とりわけ長時間労働による疲労リスクの軽減や、適切な休息の確保が可能になり、作業員の健康維持にも寄与します。
信頼性の確立と企業イメージの向上
安全第一の姿勢を明確に打ち出すことで、取引先や顧客、地域社会からの信頼を高める効果があります。特に建設業や製造業などは、労働災害のニュースが報じられると大きなダメージを受けることが少なくありません。先進的な見守りシステムを導入し、実際の事故を減らせれば、企業としてのイメージアップにも繋がります。
アフターコロナ時代の新しい働き方に対応
新型コロナウイルス感染症をきっかけに、作業現場でもソーシャルディスタンスや衛生管理が一層重視されるようになりました。個々の動きを可視化できるシステムは、接触履歴の確認にも役立ち、クラスター発生時のリスク管理にもつながります。
デメリット
初期導入コストの高さ
見守り用の機器(ウェアラブル端末、センサー、通信機器など)と管理用ソフトウェア、さらにはネットワークインフラの整備や設置工事など、システム導入にはまとまった費用がかかります。設備投資に予算を割けない企業にとっては、大きなハードルとなり得ます。
プライバシーに対する懸念
作業員の位置情報やバイタルデータなど、非常にセンシティブな情報を扱うため、社員からの抵抗感や不安を招きかねません。モニタリングに対する心理的負担を軽減するためには、なぜ導入するのか、どのようにデータを扱うのかを十分に説明し、企業として守秘義務を徹底する必要があります。
システム運用の手間とノウハウ不足
ICTに不慣れな現場担当者が多い場合、新しいシステムが導入されても正しく使いこなせず、現場で混乱が生じるリスクがあります。トラブル発生時の対応方法や、データ分析のノウハウを蓄積するまでに時間がかかるケースもあるため、導入後も継続的な教育やサポート体制を整えなければ、本来の効果を十分に発揮できません。
環境要因によるトラッキング精度の変動
工場やプラントなど、鉄骨やコンクリートなど障害物の多い環境では、電波が遮断されやすい場合があります。そのため位置情報やバイタルデータの取得が安定しないケースが考えられ、システムの信頼性を損なう一因になることもあります。
システムのカスタマイズ性
一口に「作業員見守りシステム」といっても、扱う環境や企業ごとに必要な機能は異なります。完全自社専用にカスタマイズされたシステムを開発するとなると膨大な費用や期間が必要となる場合があり、パッケージ型を選んだ場合は逆に柔軟性に限度があるなど、どちらも一長一短が存在します。
作業員見守りシステムの選び方
1. 安全管理の目的を明確化する
作業員見守りシステムを導入する際、まずは自社の現場で想定されるリスクや課題を整理し、安全対策のどの部分を強化したいのかを明確化することが大切です。たとえば、「高所作業での転落事故を減らしたい」「熱中症対策に力を入れたい」「夜間作業の巡回を自動化したい」など、目的によって最適なシステムの機能や導入形態は異なります。
また、予算との兼ね合いを考慮しながら、段階的に拡張が可能なシステムを選ぶか、一度にフルスペックで導入するかを見極めることも重要です。
2. ウェアラブルデバイス・センサーの精度と使いやすさを確認
作業員が常時着用するウェアラブルデバイスの装着感や操作性は、生産性にも大きく影響します。あまりに大きかったり重かったりすると、作業の邪魔になって作業員が敬遠してしまう恐れがあります。さらに、防水・防塵性能、耐久性といったハード面の要素も見逃せません。建設現場や工場などは過酷な環境になりやすいため、屋外や高温多湿下で問題なく動作するデバイスであることが望ましいでしょう。
また、バイタルデータの測定精度や、転倒検知・パニックボタンなどの緊急通知機能の正確性もチェックすべきポイントです。実際の運用で誤報が多発すると、アラートが“オオカミ少年”化して管理者が重要なアラートを見落とすリスクがあるため、導入前のデモンストレーションやテスト稼働を通して精度を確かめることが推奨されます。
3. 通信インフラとクラウド管理の体制を確保
見守りシステムは、リアルタイムでデータを収集・送信する関係上、通信インフラの整備が不可欠です。屋内外におけるWi-Fi環境や携帯回線、ビーコンなどの位置情報技術がどの程度整っているかを事前に確認し、設置工事やネットワークの増強が必要かどうかを洗い出すことが重要です。通信が不安定な現場では、オフラインでも一時的にデータを蓄積し、繋がり次第送信する仕組みなどを備えたシステムが望ましい場合もあります。
また、収集されたデータを管理するクラウドのセキュリティは非常に重要です。外部からの不正アクセスや情報漏えいを防ぐために、どのような暗号化技術や認証プロセスを導入しているか、システム提供会社のセキュリティ体制を調査し、契約書にも明確に記載してもらうことが求められます。自社内にサーバーを置くオンプレミス型の場合は、サーバー管理者を確保できるか、セキュリティ対策を継続して実施できるかもチェックポイントとなるでしょう。
4. 運用サポート・アフターサービスの充実度
作業員見守りシステムは導入して終わりではなく、日々の運用が大きな鍵を握ります。システムのトラブル対応や定期的なアップデート、故障時の修理や交換など、迅速かつ丁寧なサポートが受けられるかどうかを事前に確認しましょう。サービス提供会社のサポート窓口の対応時間や休日対応の有無はもちろん、現場へ駆けつけてくれるのか、オンラインでの問題解決サポートが充実しているかなども重要です。
さらに、実際に利用している企業の声を確認するためには、導入事例や口コミを調査することが有効です。同じ業種・業態であれば、類似の課題や環境でどのように役立っているのかを知ることで、運用イメージを掴みやすくなります。自社の規模に合ったプランや料金体系を提示してくれるかどうかも含めて、比較検討を行うことが賢明です。
5. データ活用の可能性を見据える
作業員見守りシステムを導入する最大の目的は安全管理ですが、蓄積されたデータを活用することで、生産性向上やコスト削減につなげられるケースも増えています。たとえば、稼働時間や動線データを分析してレイアウトを最適化したり、休憩のタイミングを見直して疲労を軽減する仕組みを考案したりと、DX(デジタルトランスフォーメーション)の観点からも大きな価値を生むことが可能です。
そのためには、データを可視化するダッシュボードの操作性やレポート機能、システム同士の連携性(API連携など)をチェックすることが望まれます。将来的に人事システムや生産管理システムとつなげる計画がある場合は、スムーズに連携が図れるプラットフォームかどうかを見極めることも大切です。
まとめ
現場で働く作業員の安全を守り、企業リスクを低減するための「作業員見守りシステム」は、建設や製造、プラント、運送など、危険が伴う作業を抱える多くの企業にとって、今や検討すべき最重要課題の一つとなりつつあります。リアルタイムにバイタルデータや位置情報を取得することで、事故の早期発見と被害拡大の防止に大きく貢献できるだけでなく、現場の効率化や勤怠管理の精度向上といった効果も期待できるでしょう。
ただし、導入コストやプライバシーの問題、システム運用の難しさなど、注意すべき点が存在するのも事実です。そのため、目的や現場の特性、導入後の運用体制をしっかりと見極めながら、最適なシステムを選ぶことが重要となります。最終的には、「安全第一」を徹底しながら、社員の健康や働きやすさにも配慮した現場づくりを進めることが企業全体の信頼性や生産性向上につながるのです。
ぜひ本記事を参考に、貴社が抱える課題に合った作業員見守りシステムを検討してみてください。
- 免責事項
- 本記事は、2025年3月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。