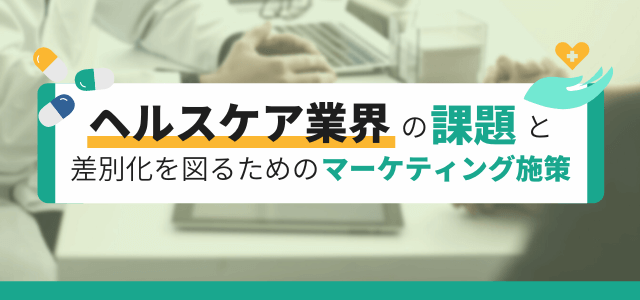作業現場や屋外活動での暑熱下でのリスクが増す中、労働安全や熱中症対策に特化したウェアラブルデバイスが注目されています。本記事では、複数の製品・サービスを比較検討し、それぞれの導入メリットや機能を解説します。
実際の作業環境やニーズを踏まえながら、安心して導入できる手がかりを得てください。
熱中症対策用ウェアラブルデバイスの一覧
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
ワーカーコネクト |
遠くまでつながり、作業者をしっかり見守るウェアラブルIoTサービス
|
みまもりがじゅ丸® |
スマホ連携や専用中継機で、かんたんに従業員を見守るウェアラブルサービス |
eMET |
ヘルメットに取り付けるだけで手軽に熱中症リスクを監視 |
REMONY |
充電不要のウェアラブルで24時間バイタルを取り逃さない体調管理システム |
hamon band |
リストバンドを巻くだけ、アルゴリズムで暑熱リスクを見える化 |
Smartfit for work |
AI搭載で一人ひとりの体調しきい値を学習、安心をつづけるウェアラブル |
みまもりふくろう |
4秒に1回の高頻度測定とAIがあなたの現場をしっかり見守る |
eメットシステム |
ヘルメット着用でひたい温度と外気温を同時にモニタリング |
hitoe® |
ナノファイバー×導電性高分子、着るだけで生体情報を計測 |
Work Mate |
スマートウォッチで作業者を見守り、注意力低下まで検知する多機能デバイス |
熱中症対策サポーター |
作業場所の熱中症危険度を遠隔地で監視、簡単導入のIoTサービス |
ThingBridge VISION |
センサーからクラウド、アプリまでオールインワンのIoTプラットフォーム |
MULiSiTEN® MS200 |
スタンドアローンで暑さストレスを可視化、東芝発のタフネスリストバンド |
SAFEMO |
スマホ不要の4Gウェアラブルも選べる安全見守りクラウドサービス |
カナリア |
ワンシーズン使い切りで充電不要、危険を事前に知らせる熱中対策ウォッチ |
熱中症対策用ウェアラブルデバイスとは?
熱中症対策用ウェアラブルデバイスとは、常に身体につける形で使用し、熱中症のリスクを監視・警告する機能を備えたデバイスを指します。代表例としては腕時計型やリストバンド型があり、内蔵のセンサーで皮膚温度や心拍数、周囲の環境情報を取得するものが多くなっています。データはスマホやPC、あるいはクラウドサービスと連携でき、遠隔地にいる管理者でも作業員の体調を把握しやすいのが特徴です。
さらに、GPSを搭載している製品なら、万が一の転倒や体調不良が起こった場合にも、作業員の位置を特定しやすくなる利点があります。特に広い作業現場や夜間作業の場面では、誰も気づかないうちに体調が急変したり倒れたりするリスクを軽減できるため、安全管理の面で大きなサポートとなるでしょう。
熱中症対策用ウェアラブルデバイスのメリット・デメリット
メリット
まず挙げられるのは、リアルタイムで体調を確認できる点です。従来は、熱中症の予防策としてこまめな水分補給や休憩が推奨されていましたが、個人差があるため「どのタイミングで休憩を取るべきか」を正確に把握しにくいケースがありました。ウェアラブルデバイスを活用すれば、心拍数や体温などのデータを参考に休憩や水分補給のタイミングを判断でき、より効果的な予防策を実行できます。
また、複数人を同時に管理する現場でも効率化につながります。デバイスから送信されるデータを一括でモニタリングすれば、危険な数値を示した作業員を即座に把握し、連絡を取ることが可能です。転倒センサーなどを併用すれば、事故や意識を失ったケースにも早めに気づき、救助を行えます。夜間作業や広範囲を扱う現場では、迅速な対応が安全確保において重要です。
さらに、作業者自身も数値を意識しながら行動を調整できるというメリットがあります。例えば、作業前に心拍数が高い状態であれば軽いストレッチを行ったり、こまめに水を飲むなど、自主的な予防策を取りやすくなります。数字で示されると説得力があるため、「これくらい大丈夫だろう」という油断を減らす効果も期待できます。
デメリット
一方で、導入費用やランニングコストがかかる点は無視できません。デバイスそのものの価格に加え、通信費やクラウドの利用料、さらにはメンテナンス費など、トータルコストが上昇する可能性があります。大規模に導入するほど高額になりやすいため、コスト対効果をしっかり検討することが必要です。
また、充電やデバイスの管理も課題となります。バッテリーが切れた状態ではまったく役に立たないため、常に使用する現場ほど充電スケジュールの徹底が求められます。高温多湿の環境や長時間稼働が必要な場面では、予想より早くバッテリーが消耗する可能性もあるでしょう。こうした運用面の煩雑さは、導入メリットとのバランスで判断する必要があります。
さらに、GPS機能やバイタルデータを取り扱う場合、プライバシーと情報管理の問題も考慮しなければなりません。どのようなデータを誰が閲覧し、どの範囲で利用するのかを明確にしないと、従業員や利用者からの不信感を招く恐れがあります。企業としては、デバイス導入前に目的や利用ルールを示し、個人情報が不必要に収集されないよう配慮すべきです。
熱中症対策用ウェアラブルデバイスの選び方
熱中症対策としてウェアラブルデバイスを導入する際は、まず「どのようなデータを取得できるか」を最優先で確認しましょう。熱中症のリスクは、体温だけでなく、心拍数や周囲の気温・湿度など、さまざまな要因が複雑に絡み合って高まります。そのため、多角的なデータを取得できるデバイスほど、熱中症の危険をより正確に検知できる傾向にあります。ただし、高機能なデバイスほど価格も高くなりがちなので、導入の目的や予算とのバランスを考慮しながら選ぶことが大切です。
次に、「通信方式やアラート通知の仕組み」にも注目しましょう。Wi-FiやBluetoothを利用する製品は、電波干渉の影響を受けやすいため、現場の環境によっては通信が不安定になる可能性があります。そのような場合は、LoRaWAN®やLTE-Mなどの長距離かつ安定した通信が可能な方式を採用しているデバイスを選ぶと安心です。また、アラートの通知方法にも配慮が必要です。メール通知だけでなく、SMSや音声アラート、さらには信号灯と連動できる製品を選べば、異常を見逃すリスクを大幅に低減できます。
操作性やデータ管理のしやすさも重要なポイントです。管理画面が複雑すぎると、現場での運用がスムーズに進まず、せっかくの機能を十分に活用できなくなる可能性があります。直感的に操作できるインターフェースを備えたデバイスや、後から蓄積したデータを分析できる機能があるものを選ぶと、長期的にも有効活用しやすいでしょう。
さらに、「サポート体制や契約形態」についても事前に確認しておくことが大切です。導入時の初期設定が簡単か、トラブル発生時に迅速に対応できるサポート窓口があるかなど、安定した運用のために欠かせない要素です。特に月額課金型のサービスを利用する場合は、契約期間や解約条件、追加オプションの料金などをしっかり確認し、想定外のコストが発生しないよう注意しましょう。
まとめ
熱中症対策用ウェアラブルデバイスは、猛暑下で作業や活動を行う人々の健康と安全を守るうえで大変有効な手段です。リアルタイムに身体や環境のデータを取得し、リスクが高まれば即座に通知してくれるため、熱中症による事故や重大なトラブルを未然に防ぎやすくなります。一方で、導入コストや運用の手間、プライバシーへの配慮など、考慮すべき課題も複数存在します。だからこそ、自身の現場環境と導入目的を整理したうえで、求める機能やサポート体制、費用面を総合的に比較検討することが不可欠です。
もし複数の製品で迷っている場合は、短期トライアルなどを活用して実際の通信状況や操作性を試すのが賢明でしょう。適切なデバイスを選択し、従業員や利用者への周知を徹底することで、危険な暑さの中でも安全を維持しながら業務や活動を継続することが可能になります。熱中症は正しい知識と備えがあれば、十分に予防できる病気です。ウェアラブルデバイスを上手に使いこなし、多くの人の命と健康を守る取り組みをさらに進めていきましょう。
- 免責事項
- 本記事は、2025年3月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。