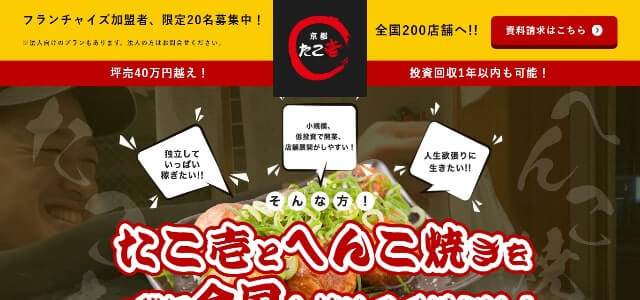食材発注ツールとは、食材発注の仕入れ業務を電子化するソフトウェアツールです。従来は、電話・メール・FAXなどで行われていた発注業務をオンラインで完結させられるため、業務効率化や従業員の負担削減に繋がります。
このページでは食材発注ツールを取り扱う企業を紹介しています。各ツールの強み、費用、評判などをまとめているので、自社に最適なツール選びにご活用ください。
食材発注ツールの一覧表
ここでは、食材発注ツールをまとめて紹介します。各サービスの特徴が分かる早見表を作成しましたので、自社に最適なツール選びにご活用ください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
Order Gate |
共同購買で最大15%のコスト削減!大型店舗と同様の仕入れ額を実現
|
PlaceOrders |
発注先の環境に合わせて送信方法を選べる。システム導入の手間やコストを削減 |
食べログ仕入 |
食べログ店舗会員登録があれば無料で利用できるツール |
BtoBプラットフォーム 受発注 |
発注業務はもちろん、店舗経営の判断材料にも活用できる |
CO-NECT |
スマホやPCでかんたんに発注。クラウド会計ソフトfreeeとも連携 |
COREC |
シンプルなインターフェースなので、ITに弱い人でも簡単に使える |
魚ポチ |
冷蔵庫の在庫を確認しながら翌日の食材を小ロットで注文できる |
クロスオーダー |
発注したらすぐにLINEメッセージで発注内容が届く |
TANOMU |
利用料無しでスマホからカンタンに注文可能 |
HANZO 自動発注 |
AIによる高精度な需要予測で適正な発注管理を実現 |
八面六臂 |
取扱商品114000点の幅広い品揃え |
食材発注ツールとは?
食材発注ツールとは、発注に関する処理をWEB上で完結させることにより業務の効率化やコスト見直しが実現するツールのことです。
オンライン上でやりとりを完結させることから「Web発注システム」とも呼ばれています。
食材発注ツールで期待できる導入効果
従来は電話・メール・FAXで行っていた仕入れ作業について、システム上で発注すれば入力作業を短縮でき、ほかの業務に時間が割けられます。
請求時の仕入れ金額の確認や在庫の棚卸などの業務についても、ある程度は自動化が可能。決算の早期化や接客時間の増加による売り上げアップなどの効果もあるでしょう。
食材発注ツールの主な機能
サービスによって対応範囲は異なりますが、注文用Webページ、発注機能が主な機能です。
注文用Webページは、Webカタログを設置して注文フォームからオンライン上で受発注できるようになっています。
発注機能は、発注書の作成・送信や、在庫確認しながら発注できる棚卸機能などです。他に原価管理やフランチャイズ管理機能などもあります。
飲食店で食材発注ツールを導入するメリット
メリットとしては、下記があります。
- 人為的ミスを防止する
- 業務を効率化する
人為的ミスを防止する
食材発注ツールは、商品の数量および金額をデータとして反映することができます。そのため、電話・FAX・メールでの発注で起こりうる数量間違いや入力・転記ミスなどが発生する心配もありません。
商品名と価格を登録しておけば発注金額の合計も自動で計算されて、取引先ごとに最低金額が決まっている場合も素早く発注できます。
月間の発注金額や発注先ごとの仕入れ額を正確に抽出したうえで分析が可能なシステムもあります。
業務を効率化する
食材発注ツールは、商品情報をあらかじめ登録しておけば発注作業もボタンを押すだけで実行できます。「紙に記入しFAXで送信する」「手書きでメモを残す」といった、手間がかかる業務は不要です。
またシステムは24時間対応のため、取引先の都合にあわせる必要もありません。空いた時間さえあればいつでも発注作業が可能です。
食材発注ツールは発注の場所を問いませんので、電車での移動時間なども有効活用できます。ほかの重要な業務に割ける時間も増えます。生産性の向上が期待できます。
飲食店で食材発注ツールを導入するデメリット
デメリットとしては、下記が考えられます。
- 導入コストが高額になる場合がある
- 取引先の同意が必要な場合がある
導入コストが高額になる場合がある
発注ツールの導入には、新たに機器の導入が必要なケースがあります。
機器を購入する初期費用や運用する月額費用、メンテナンス費用などから、コストが高額になるリスクがあるでしょう。
取引先の同意が必要な場合がある
発注ツールは、自社だけでなく取引先も導入しなければ利用できないものもあります。その際、事前に取引先に説明し、同意を取り付ける必要があります。断られるケースも想定されるでしょう。
飲食店の発注業務を効率化するコツ
コツとしては、「決まった時間・スケジュールで実施する」点があります。
発注の時間・スケジュールを決めれば、発注業務にかかる時間が明確化するでしょう。工程の進捗状況や、いつ・誰が・どこで・何をしているのかも把握できます。業務に優先順位をつけてチームを管理でき、具体的かつ理解しやすい指示出しも可能です。
「発注点を決めておく」のもコツです。発注点とは、商品を発注する基準となる在庫数を指します。機会損失につながる基準を示すため、発注作業に取り掛かる目安として利用可能です。
食材発注ツールの相場
相場は、大きく分けて3つあります。
1からオリジナルでシステムを開発するフルスクラッチの場合、初期費用:数百万~数億、維持費用:月額3万~数十万と高額になります。
1からオリジナルでシステムを開発するという性質上、当然なのかもしれません。
基本パッケージはあり業務に合わせて一部の機能のみ追加開発を行うハーフスクラッチの場合、初期費用:100万~数千万、維持費用:月額3万~数十万とフルスクラッチよりは安くなります。
基本パッケージの機能のみを利用し、追加プラン等で機能追加を行うクラウドの場合、初期費用:無料~、維持費用:月額980円~とかなり安くなります。中小の会社が導入するにはクラウドが現実的でしょう。
食材発注ツールを導入する際によくある質問
Q1.食材発注ツールを選ぶ際のポイントは?
スマートフォンやタブレットといったモバイル端末に対応しているか確認することが重要です。モバイル端末に対応していれば、在庫確認しながらその場で発注や修正を行うことができるからです。
パソコンの操作に慣れていない従業員であっても、普段利用しているモバイル端末なら使いやすく直感的に操作ができます。
食材発注ツールまとめ

食材発注ツールには様々なタイプがあります。サービスを選ぶ際にはまず、「どのようなツールが必要か」、「コスト低減・業務効率向上のために何をどこまで依頼するのか」など選ぶ目的を明確にしましょう。
さらに、食材発注ツールを利用する際には費用がかかります。そのため、予め月額いくらまで払えるのか、予算規模はどのくらいかといったコストシミュレーションをしておくと良いでしょう。
- 免責事項
- 本記事は、2024年4月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。