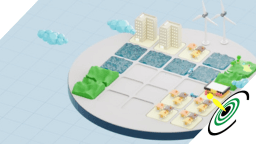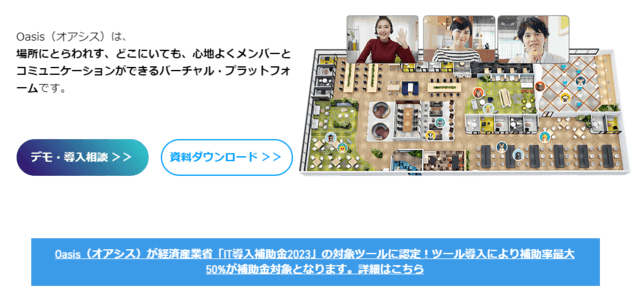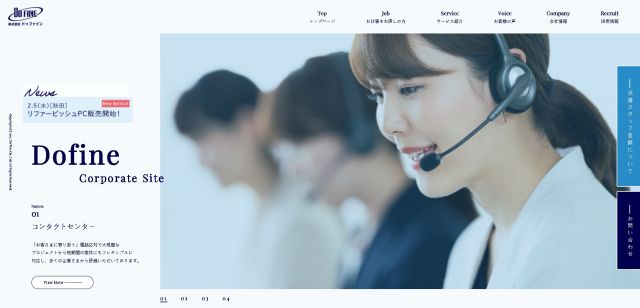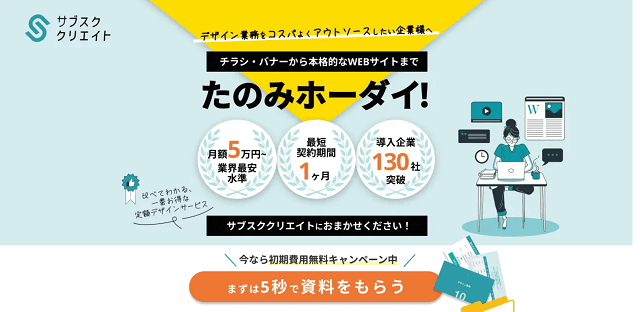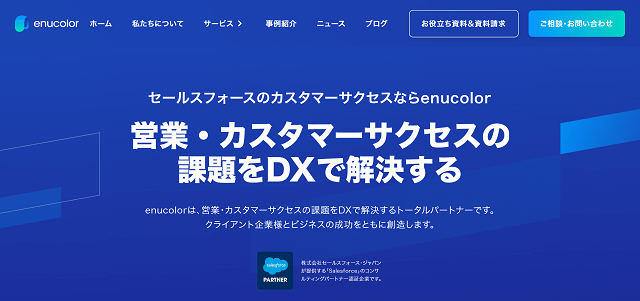バーチャルオフィスツールとは、仮想空間上に構築するオフィスのことです。
それぞれの動向やステータスをリアルタイムで共有できるため、まるで実際のオフィスで働いているような環境を構築できる点がメリットだといえます。バーチャルオフィスツールを利用すれば気軽な相談やミーティングがおこなえるので、コミュニケーションの活性化が達成できるでしょう。
この記事では、各社が提供するバーチャルオフィスツールの特徴や料金などを比較した内容をまとめました。ツール導入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
Oasis |
豊富なプランの選択肢から自社に合ったものを選んでコスパを高めるなら
|
FAMoffice |
1フロア最大150人収納できるバーチャルオフィス |
RISA |
ゲーム感覚で同僚と話したりチームメンバーの状況をひと目で把握 |
oVice |
アバターの距離に応じて相手の声の大きさが変化する |
Kumospace |
チームビルディング向けのゲームが搭載されている |
Gather |
オフィス以外にもグラウンドやダンジョンなどのテンプレートがある |
TEEMYCO |
家具が配置できるだけでなくカラーを変えたりロゴを挿入できる |
Remo |
セミナーや展示会などを開催できる |
NeWork |
プロジェクトや業務ごとに仮想の会話スペースである「バブル」を作れる |
VOICHAT |
必要に応じて相手のルームに入ればすぐに会話ができる |
LIVEWORK |
PCカメラで自動撮影された写真が一定間隔で共有される |
SoWork |
AIがSoWorkで話した内容を文字起こしして要約してくれる |
仮想オフィスサービス |
今日の一言コメントや気持ちアイコンが機能がある |
Remotty |
PCのカメラで自動撮影された写真が2分間隔で共有される |
Spatial Chat |
5人までなら無料で利用できる |
リモートワークの現状・動向とチーム管理の変化について
ここでは、リモートワークが現状どのようになっているのか、またチーム管理のあるべき変化について述べていきます。
リモートワークの現状・動向
リモートワークが広がるにつれて、下記のような現状・動向が見られます。
- 継続・廃止の2極化が進んでいる
- 現状の実施率は4割程度
- 業種ごとにバラツキがみられる
継続・廃止の2極化が進んでいる
リモートワークは大きくわけて、次のような過程を経て会社に取り入れられてきました。
- 新型コロナ感染症が流行する前から続けている
- コロナによってリモートワークに変えた
現在では、リモートワークを実施していたがリモートワークを廃止し出社型に切り替えた会社とリモートワークを実施し続けている会社に分かれています。
リモートワークを廃止した理由としては、急なリモートワークへの対応によってデメリットの方が大きくなり、社内の統制が取りづらくなった点が想定されるでしょう。
一方、リモートワークを実施し続けている会社も存在していることから現状では2極化が進んでいると考えられます。
現状の実施率は4割程度
現状のテレワークの実施率は大企業を中心に38.4%で約4割程度にとどまっており、中小企業のみの数字をみれば33%となっています。(令和3年版 情報通信白書より)
これは、緊急事態宣言によってテレワークを実施したが、中小企業ではテレワークのまま事業を継続することが難しかったという見方ができるでしょう。
ただし、現在もテレワークで事業を継続している会社もあることから、テレワークという働き方が会社の経営陣に受け入れられ定着しているともいえます。
業種ごとにバラツキがみられる
リモートワークはITを中心に実施されており、一方運送や医療、建設などでは実施率が低くなっています。
医療に関してはオンライン診療などの対応も増加しつつあるものの、現状では対面での診察を望む人々が多いことからリモートワークの普及はまだ先だと予想されます。
ただし、どうしても人が管理しなければならない業務の場合はリモートワークが不可能です。
したがって、業務内容と照らし合わせながら取り入れていく必要があるでしょう。
リモートワークによるチーム管理の変化
リモートワーク導入後のチーム管理の変化については、下記が挙げられます。
- 業務が可視化される
- プラットフォーム作りの必要性が高まる
- 認識をすり合わせる
業務が可視化される
テレワークを導入している職場では、各社員の仕事の進捗状況が可視化される必要があります。
業務シートを作成し、担当者や現状をこまめに記載すると効果的でしょう。業務シートを閲覧するだけで全体の状況を把握できるため、連携しやすい環境になります。
また、顧客に対する連絡もこまめに共有しないとサービスの質を低下させる原因になります。
テレワークで社員同士が離れて働く場合、より確実に情報共有を行う必要があります。たとえば顧客にメールを送る際には必ず上司をBccに入れるようにすると、確認や指導もスピーディに行えるため効果的です。
プラットフォーム作りの必要性が高まる
また、テレワークではプラットフォーム作りの必要性が高まっています。
まず業務に必要な書類やデータは一元化し、シートにまとめてわかりやすく管理する必要があります。
たとえばテレワークを行う日程、問い合わせ先の一覧、システムを利用する際のルールなどをまとめておくと便利です。
情報を一元化していると、知りたいことをすぐに確認できるため、生産性の向上にもつながるでしょう。
またテレワークを始めるときは、業務全体の流れを見直したうえでルールを決めることも重要です。
ルールが明確になると、社員同士が離れた場所で働いていても業務をスムーズに進められます。
工程を切り分けて作業できる体制がつくられるので、誰が何をすべきであるかもわかりやすくなります。
認識をすり合わせる
テレワークを導入している職場では、認識をすり合わせることも重要です。
テレワークでは、他のメンバーが個別にやり取りしている内容を知ることが難しいです。
そのため指示するポイントを役職ごとに決めておかないと、部下は同じ指示を複数の上司から何度も受ける場合があります。
業務の効率化により生産性を高めるには、そのような状況は避けるべきでしょう。
マネージャーからは連絡や共有を行う、リーダーからは具体的な数字について指示するといったルールを決めると風通しの良い環境になります。
チーム管理ツールについて
ここでは、チーム管理ツールについて見ていきましょう。
チーム管理とは何か
チーム管理とは、チームに属する個々のメンバーが能力を発揮しやすい環境を整え、チーム全体の生産性を高める手法を指します。
管理といっても、単にメンバーを管理して統率することだけを意味しているわけではありません。
チームをまとめていくにあたって、リーダーが果たすべき最も重要な課題は「目標達成」といえます。
一人では実現が難しい大きな目標を達成することが、チームの存在意義でしょう。
そこで、リーダーはいかにチーム全体の生産性を高め、目標を達成していくかを考えなくてはなりません。
チームマネジメントツールとは
チームマネジメントツールには、大きく分けてプロジェクト管理と人材マネジメントの2つがあります。
プロジェクト管理
1つ目がプロジェクト管理ツールです。情報をリアルタイムで共有しデータの格納先を集約させ、状況を一覧化させて全体像を掴めるようにするためのツールのことです。
新しいチームでプロジェクトを推進すると、誰が何を担当しているのかが分からなくなったり、その進捗具合が見えなかったり、どこにファイルが格納されているのかが分からなくなったりすることがあります。
また、それを一元化するツールを作る工数もさけなければ、いざ導入しても抽象度がバラバラで意味を成していない場合もあります。
プロジェクト管理におけるチームマネジメントツール選びでは、管理職・マネージャーのためだけではなく、メンバーも使いやすいUI/UXになっていることがポイントです。
人材マネジメント
チームマネジメントツールの2つ目のカテゴリが、人材マネジメントツールです。
人材マネジメントは、さらに人事部向けのツールと現場向けのツールの2つに分かれています。
人事部向けには、タレントマネジメントのためのツールがあります。
入退社の推移や人員配置など、組織全体の管理のために使用していきます。部署単位でデータを得ることが多く、組織全体の変化をみることが可能です。
一方、現場向けにはピープルマネジメントのためのツールがあります。
管理職とメンバー、メンバー同士が滞りなくコミュニケーションが取れ、それがデータとして蓄積され、人事制度・目標設定との関連が見えることが従業員のエンゲージメントに繋がるツールを指します。タレントマネジメントと比較すると、1on1や日報やフィードバックなど日常的なコミュニケーションに強いのが特徴です。
人材マネジメントのツールは人事部向けをイメージする人が多いのですが、部署単位でこそ活用できるのがピープルマネジメントのツールです。
バーチャルオフィスツールとは
ここでは、バーチャルオフィスツールとはなにかについて解説していきます。
バーチャルオフィスツールとは仮想空間上でコミュニケーションできるツール
バーチャルオフィスツールとは、仮想空間上に構築するオフィスを指します。仮想的なオフィス環境に従業員がアバターを登場させ、仮想デスクへの着席や会議室の入室などができます。
各自の動向やステータスをリアルタイムで共有できるため、まるで実際のオフィスで働いているような環境を構築できる点が魅力の一つといえるでしょう。
バーチャルオフィスツールを利用すれば気軽な相談やミーティングがおこなえるため、コミュニケーションの活性化が実現可能です。
バーチャルオフィスとの違いについて
バーチャルオフィスツールと混同されやすいサービスとして、バーチャルオフィスがあります。バーチャルオフィスとは、物理的に実体を有しない仮想事務所のことをいいます。
企業は、登記手続きや郵便物の受取などで住所が必要です。バーチャルオフィスでは住所をレンタルできるため、物理的なオフィスがなくても利用可能です。
新宿や渋谷などの都心の一等地に住所があるバーチャルオフィスサービスも多く、社会的信用性を高められるためブランディングの強化を目的に利用する企業もあります。
メタバースオフィスとの違いについて
メタバースオフィスとは「meta」と「universe」を組み合わせた言葉で、仮想空間上に構築されたオフィスサービスを指します。
参加者がアバターを使用し、ほかの参加者とコミュニケーションが取ります。必要に応じて画面や資料を共有できるため、離れた場所で仕事をしている従業員同士がリアルタイムで業務を進めることが可能。
バーチャルオフィスツールとメタバースオフィスは、どちらもバーチャル空間でのコミュニケーションツールとなっています。同じような機能が利用できるため、現状では明確に区別されていません。
バーチャルオフィスツールを導入するメリット
バーチャルオフィスツールを導入するメリットには、何があるのでしょうか?おおよそ、下記があります。
- 気軽にコミュニケーションがとれる環境を用意できる
- リモートワークによる孤独感が解消する
- 業務状況の可視化
- 適度な緊張感が得られる
気軽にコミュニケーションがとれる環境を用意できる
バーチャルオフィスツールでは、気軽にコミュニケーションがとれる環境を用意できます。
リモートワークでは、従業員同士が気軽にコミュニケーションが取りにくい点が課題として挙げられます。バーチャルオフィスツールでは仮想のオフィス空間に常時アバターを表示できるので、従業員がどこで何をしているのかが一目で把握可能です。
一般的なチャットツールでは相手の状況を把握できないため、連絡を取るタイミングを図りにくい部分がありました。しかし、バーチャルオフィスツールでは相手の状況をリアルタイムで把握できるため、気軽にコミュニケーションが取れる環境を用意できます。
リモートワークによる孤独感が解消する
また、リモートワークによる孤独感が解消します。
リモートワークによって従業員同士のコミュニケーションが少なくなり、孤独を感じる従業員もいます。コミュニケーション不足による孤立化が加速し、中にはメンタルの不調を訴える従業員もいるかもしれません。
バーチャルオフィスツールでは仮想空間上のオフィスにアバターでリアルな状況を表示できるため、オフィスに出社したような状況を演出できます。常に誰かとつながっている感覚で仕事をできるので、孤独感の解消が期待できるでしょう。
業務状況の可視化
バーチャルオフィスツールを使えば、業務状況の可視化がはかれます。バーチャルオフィスツールでは「在籍中」や「離席中」、「会議中」「休憩中」などのステータスを表示させることが可能です。
リアルタイムで業務状況を把握できるため、相手の都合に合わせて連絡を取ることができ、企業側も一目で稼働状況を管理できます。
適度な緊張感が得られる
さらにバーチャルオフィスツールによって、適度な緊張感をもって仕事ができます。自宅でのテレワークはオンとオフの切り替えが難しいため、中にはオフィスに出社するときのような緊張感を維持できない従業員もいます。
バーチャルオフィスツールでは、アバターで自分の業務状況を表示可能です。出社するのがアバターでも出社している感覚や周囲の視線を感じる環境を作り出せるため、適度に緊張感を持って仕事をするようになります。
バーチャルオフィスツールを導入する場合、注意すべきポイント
バーチャルオフィスツールを導入する場合、注意すべきポイントとしては下記があります。
- 従業員に一定の操作スキルが必要
- 従業員にストレスを与える場合がある
- ランニングコストが発生
- PCのスペックや通信環境の見直しが発生
従業員に一定の操作スキルが必要
バーチャルオフィスツールを利用するには、従業員の側に一定の操作スキルが必要とされます。バーチャルオフィスツールは近年登場した新しいツールのため、導入しても使いこなせない従業員がいるかもしれません。
従業員に一定の操作スキルが求められるため、慣れるまではツールの操作に集中し過ぎて一時的に生産性が低下する恐れがあることに注意が必要です。
従業員の混乱を来さないよう、事前に研修会を開いて導入目的や操作方法などを説明しておくことが重要です。
また導入後もスムーズに運用するために、操作方法を問い合わせできる窓口を設置するなど従業員をサポートする体制を整えなければなりません。
従業員にストレスを与える場合がある
バーチャルオフィスツールが従業員にストレスを与える場合があるので、注意しましょう。
バーチャルオフィスツールは、従業員一人ひとりのステータスや業務状況をリアルタイムで把握できるメリットもあります。しかし、なかにはこうした状況を「常に監視されている」と捉える従業員がいます。
従業員の精神的な負担を軽減するためには、導入の目的やメリットを説明し十分に理解を得ることが重要です。また導入後はオフラインにできる時間を設け、オンとオフのバランスを取りながら運用していくことが望ましいです。
ランニングコストが発生
バーチャルオフィスツールを導入すると、ランニングコストが発生します。多くのバーチャルオフィスツールでは、毎月料金を支払う月額課金制を採用しています。
また、ユーザー数やサービス内容に応じてさまざまなプランが用意されており、なかには初期費用がかかるサービスもあるためあらかじめ確認が必要です。
料金だけでなく機能面やサポート体制などを比較の上、自社に適したサービスを選ぶことが重要です。
PCのスペックや通信環境の見直しが発生
バーチャルオフィスツールを使うにあたり、PCのスペックや通信環境の見直しが発生する場合があります。
従業員個人のPCを使用する場合、機種によってスペックが異なるためスムーズに動作しないバーチャルオフィスツールもありえます。ツールを導入する際には、必要に応じて従業員にPCやモバイルルーター貸与の検討も必要です。
また、インターネット回線の通信量に上限があるプランで契約している従業員もいるでしょう。通信制限がかかった場合、日々の仕事にも影響をおよぼすため無制限プランのモバイルルーターを貸与するなどの対策が必要になります。
ツールを導入する際には、従業員がストレスなく仕事ができる環境を作りましょう。
バーチャルオフィスツールの利用がおすすめの企業や業種
バーチャルオフィスツールの利用は、やはりテレワークに適した企業や業種がおすすめです。例えば、下記のような業種でしょう。
- IT・インターネット
- マスコミ・広告
- 金融・保険
- 弁護士・翻訳
テレワークをおこなうには、PCやスマホと接続できるインターネット環境、データを保存・共有できるクラウド、情報漏えいなどを防ぐセキュリティ対策などの条件が必要です。
これらの条件が整いやすいIT・インターネット業界、マスコミ・広告業界では、多くの企業がテレワークを導入済です。
また対面での接客、営業、販売が中心だった金融・保険業界 や不動産業界でも、Web会議ツールやチャット、電子文書決済システム、商品提案から申込手続きまでワンストップの対応を可能にする専用端末などを活用して、テレワークが可能です。
弁護士や行政書士、法務・給与などの事務業務、翻訳・通訳 といった専門的な知識や技術提供をおこなう個人作業が中心の業種もテレワークに向いています。
こうした業種で、テレワークを行っている企業にバーチャルオフィスツールを導入すると大きなメリットが得られます。
バーチャルオフィスツールのまとめ
バーチャルオフィスツールは、リモートワークにおけるコミュニケーション不足や状況把握の難しさといった課題を解決する手段として注目されています。
従来は一時的な対応として使われることが多かったものの、今後は継続的にリモートワークを選ぶ企業や個人も増えると考えられます。そのため、使いやすさや料金の継続性に加え、チームの一体感や企業文化の醸成に寄与するかどうかも、ツール選びの重要なポイントとなります。
サービスによって強みも機能性も異なっています。ぜひ会社にあったバーチャルオフィスツールを取り入れてみてください。
- 免責事項
- 本記事は、2024年3月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。