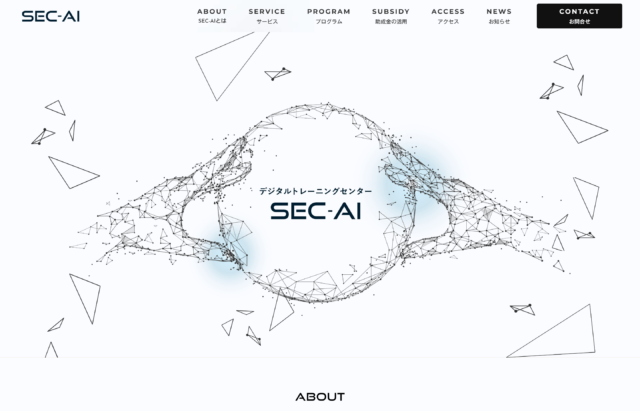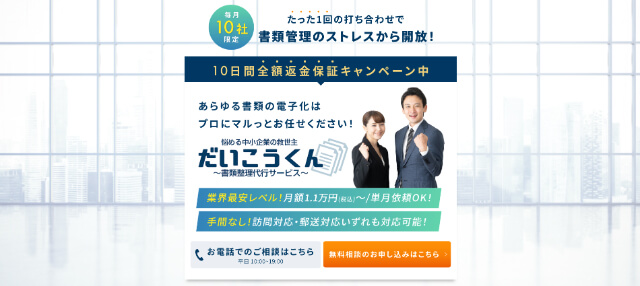近年、多くの企業が生成AIを活用し、競争力向上を目指しています。「生成AIに関する実態調査 2024 春」によると、43%の企業が生成AIを活用中です。
生成AIを効果的に導入するには課題も多く、ChatGPT導入研修が注目を集めています。
この記事では、ChatGPT研修を提供するおすすめの会社を比較し、各研修内容を紹介します。サービス選びの参考にしてください。
ChatGPTの導入研修を実施している会社一覧表
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
SEC-AI(DXHR) |
1000以上の学習プログラムから業種別・職種別・レベル別にオーダーメイド!
|
AIイノベーションズ |
企業ニーズに応じた柔軟なChatGPT研修を提供 |
日本能率協会マネジメントセンター |
初心者歓迎、実践で学べるChatGPT活用研修 |
インソース |
非エンジニアでも安心、基礎から学べるChatGPT研修 |
ビズアップ総研 |
非エンジニア向け、実践重視のChatGPT活用研修 |
リスキル |
基礎から応用まで効率学習、ChatGPT活用研修 |
キカガク |
多様なニーズに応える3つのChatGPT研修を提供 |
トレノケート |
半日で学ぶChatGPT活用、オンライン研修を提供 |
インターネット・アカデミー |
基礎から実践まで学べる、柔軟カスタマイズのChatGPT研修 |
ChatGPTとは?
ChatGPTとは、OpenAIが手掛ける生成AIであり、人間と会話しているかのような自然な受け答えを生成するサービスです。2022年11月にリリースされると、さまざまな業種でパラダイムシフトを起こすツールとしてたちまち注目を集めました。 その誕生はしばしばインターネットの誕生にも準えられるChatGPTですが、
- 企画書作成
- メールマガジン作成
- 翻訳
- コーディング
といった、これまで自動化が難しかったさまざまな業務を自動化することが出来るツールとして、ビジネスシーンでの活用も広がりつつあります。 リリースからわずか3カ月後の2023年1月にはマイクロソフトが100億ドル規模の投資を発表するなど、今後のさらなる成長が期待されているサービスです。
ChatGPTのメリットとデメリット
メリット
- 業務効率化: 企画書やメールの作成、コーディング、翻訳など、時間がかかるタスクを迅速に処理。
- 幅広い活用性: ビジネス、教育、エンターテインメントなど、多岐にわたる分野での利用が可能。
- コスト削減: 自動化により、従業員の時間を節約し、人件費の削減に寄与。
- 学習と改善: 継続的なモデルのアップデートにより、精度や機能が向上し続ける。
- 24時間稼働: 人間の労働時間に縛られず、いつでも利用可能。
デメリット
- 事実確認の必要性: 生成された内容が誤っている場合があり、特にビジネスで使用する際には慎重なチェックが必要。
- 倫理的リスク: 無断引用や偏った情報に基づいた回答を生成する可能性。
- 依存リスク: 人的スキルや判断力が損なわれる可能性があるため、過度な依存は避けるべき。
- プライバシーの懸念: 利用時に入力するデータが第三者に影響を及ぼすリスクがあるため、取り扱いに注意が必要。
- 導入と学習コスト: 効果的に使用するためのスキル(例: プロンプトエンジニアリング)を学ぶ必要がある。
ChatGPT研修サービスの選び方
ChatGPT研修サービスを選ぶ際には、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。以下に、その選び方について詳しく説明します。
カリキュラム内容の充実度
まず、カリキュラム内容の充実度です。実務に直結する具体的なスキルや知識を提供するカリキュラムが含まれているかどうかを確認しましょう。基本的な理論だけでなく、実際の業務で活用できる実践的な内容が盛り込まれていることが重要です。
講師の専門性
次に、講師の専門性も重要なポイントです。実際の業務経験を持つ専門家が指導する研修は、理論だけでなく実践的な知識も得られます。講師の経歴や実績を確認し、信頼できる研修を選ぶことが大切です。
研修形式の柔軟性
また、研修形式の柔軟性も検討ポイントです。オンライン研修、対面研修、ハイブリッド形式など、自社のニーズに合った形式を選ぶことが大切です。特に、リモートワークが普及している現在では、オンライン形式の研修も多くのメリットがあります。
受講後のフォローアップ体制
さらに、受講後のフォローアップ体制もチェックしておくと安心です。研修終了後もサポートを受けられる環境が整っていると、学んだ内容を定着させやすくなります。質問対応や追加トレーニングの提供など、アフターケアが充実しているかを確認しましょう。
費用対効果
最後に、費用対効果を考慮することも忘れずに。高品質な研修を適正な価格で提供しているサービスを選ぶことで、投資に見合う成果を期待できます。コストだけでなく、得られるメリットや長期的な効果を見極めて、最適な研修サービスを選びましょう。
これらのポイントを総合的に判断し、自社の課題解決に最適な研修サービスを選ぶことが、ChatGPT研修の成功への第一歩です。
費用負担を軽減!ChatGPT研修の助成金
ChatGPT研修の費用負担を軽減するために利用できるのが、人材開発支援助成金です。
この助成金制度は、企業が従業員に対して職務に関連する専門知識や技能を習得させるための研修を実施する際に、研修費用や研修期間中の賃金の一部を補助するものです。最大75%の補助を受けられるため、企業にとって大きな財政的サポートとなります。
助成金を受けるためには、いくつかの要件や手続きがあります。例えば、研修計画の策定や実施報告、関連書類の提出などが求められますが、これらをクリアすれば大幅に研修費用を抑えることが可能です。また、助成金を活用することで、多くの従業員が質の高い研修を受けられるようになり、組織全体のスキルアップが期待できます。経営者や人事担当者にとって、助成金の活用はコストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。
ChatGPT研修の費用相場
ChatGPT研修の費用相場は、研修の形式や内容によって異なります。一般的には、基礎的なオンライン研修であれば、1名あたり数万円程度から受講可能です。
一方で、実践的な対面研修や、専門家によるマンツーマン指導を受ける場合、1回あたり数十万円以上の費用がかかることもあります。また、企業向けにカスタマイズされた研修プログラムは、受講人数や内容に応じてさらに費用が増加する傾向があります。
企業にとって重要なのは、研修の費用対効果を考えることです。単に安価な研修を選ぶのではなく、実務に直結するスキルを習得できるか、研修後のサポートが充実しているかなどを基準に選定することが求められます。助成金制度を活用すれば、コストを抑えつつ質の高い研修を実施することが可能です。費用相場を理解し、最適な研修プランを選ぶことで、従業員のスキルアップと企業の成長を実現できます。
ChatGPTに関するQFA
Q1. ChatGPTはどんな業務で役に立ちますか?
ChatGPTは、これまで自動化することができなかった業務を自動化することが出来るツールとして、さまざまな業務で利用することが出来ます。いくつか具体例を挙げると、
- 企画書の作成
- メールマガジンの作成
- クライアントへのメールの作成
- 業務マニュアルの作成
といった業務での活用が可能です。
また、ChatGPTは文章の生成に加えて文章の要約やインターネット上での調査も得意です。そのため、
- クロスレビュー
- 競合リサーチ
- リファレンスチェック
- 非上場企業の事業内容の要約
- 動画コンテンツの要約・概要の作成
といった業務でもChatGPTを活用することが出来ます。
さらに、ChatGPTはプログラミング言語を取り扱うことも出来ます。従って、
- コーディング
- コードの軽量化
- デバック
といった業務でもChatGPTを利用することが可能です。
Q2. なぜChatGPT研修を受けたほうがいいのですか?
さまざまな業界で大きな変革を起こす革新的なツールとして注目を集めているChatGPT。しかし、ChatGPTは誰でも簡単に操作することが出来るツールではありません。
例えば、生成AIに与える指示の事をプロンプトと呼びますが、このプロンプトを出す際の技術(プロンプトエンジニアリング)についてのノウハウやナレッジがなければ、ChatGPTから望み通りの回答を得るのは難しいでしょう。まして、ビジネスの現場で問題なく使えるような文体・表現の回答が欲しいとなればなおさらです。
ChatGPT研修を受けることで、そうしたChatGPTを使う上でのノウハウ・やナレッジについて効率良く学ぶことが出来ます。
他方で、ChatGPTを活用するにあたって注意したいポイントについて知ることが出来るのも、ChatGPT研修を受けたい理由の一つ。
まるで人間が書いたかのような自然な文章を生成できるChatGPTですが、ChatGPTはあくまでインターネット上での単語相互の関係性から文章を自動生成しているにすぎません。そのため、ChatGPTを使用するにあたっては、
- 事実に反する内容をあたかも事実であるかのように生成することがある
- 特定の著作の内容を無断で引用して文章を生成することがある
といった倫理的および法的リスクがあります。
ChatGPT研修を受けることで、こうしたリスクを回避するための方法について学ぶことが出来ます。
ChatGPT研修の利用を考えている方は、本ページの「ChatGPTの導入研修を実施している会社一覧表」をご覧ください。
まとめ
おすすめのChatGPT研修の特徴を紹介してきました。
自動化が難しいとされてきた業務を自動化できるツールとして、すでにビジネスシーンでの導入が始まっているChatGPT。ビジネスシーンでのChatGPTの活用の仕方について学びたいならChatGPT研修を受けるのがおすすめですが、それぞれのサービスには異なった特徴があり、A社にとって良いサービスがB社にとっても良いサービスとは限りません。 ChatGPT研修選びで迷ったら、ぜひこのページをお役立てください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年12月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。