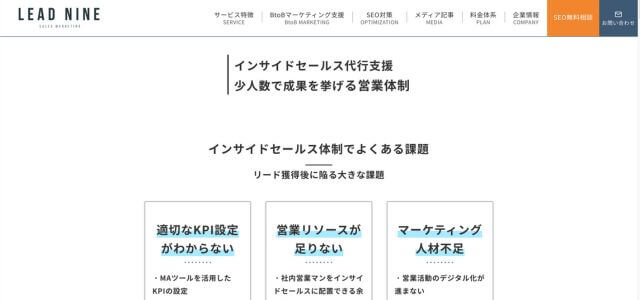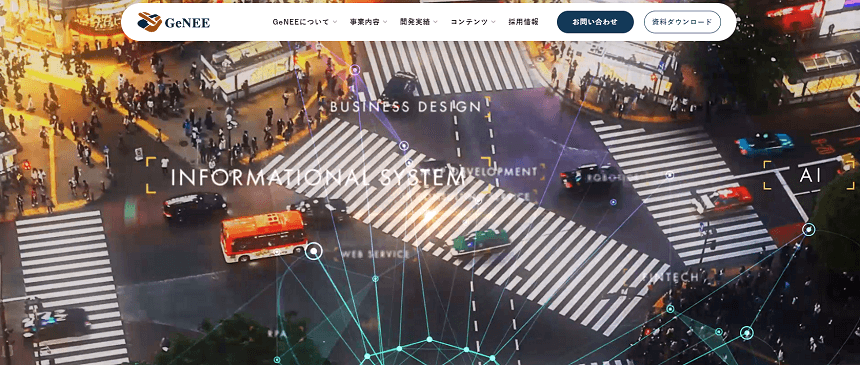IT業界におすすめの営業代行の一覧
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
BCC |
「IT営業」に特化した人材派遣で、即戦力を提供
|
ワールドスタッフィング |
フルファネル×アナリティクスなインサイドセールスで、あらゆる業種の営業課題を支える
|
セレブリックス |
“現場主義”で営業課題をまるごと支援し、収益力向上をサポート |
スタジアム |
オンライン商談・CSまで一気通貫でサポート |
ビートレード・パートナーズ |
成果型の営業支援で安定的に商談を創出し、売上拡大を加速 |
EBAテック |
実践的コンサル×Web営業代行で、IT/Web商材の拡販を強力サポート |
ジャパンプ |
訪問営業~テレアポまで「質」にこだわる営業支援で成果を追求 |
エフ・コード |
デジタルマーケティング戦略×セールス支援の両軸でビジネスを強くする |
プロセルトラクション |
新規事業立ち上げ×BtoBマーケ支援で、事業をトラクションさせるプロ集団 |
インプレックスアンドカンパニー |
営業組織構築から実運用代行まで、マネジメント力を強みに現場を変革 |
エッジコネクション |
データ活用×テレマーケティングでBtoB営業の効率と成果を最大化 |
3MA |
IT営業プロがBDR/SDRを代行し、DX時代のBtoBビジネスを加速 |
グローバルステージ |
新規事業開発×営業力でスタートアップから大手まで事業加速 |
パーソルビジネスプロセスデザイン |
マーケ×セールス×バックオフィスを一括BPOで業務効率と成果を両立 |
セールスドライブ |
成果報酬型のアウトバウンド営業で商談数を増やし、売上拡大を実現 |
ウィルオブ・ワーク |
人的リソースの強みを活かし、全国規模のBtoB営業支援を実現 |
アースリンク |
Salesforce活用×インサイドセールスで、データドリブンな営業活動を支援 |
ビズリンクス |
オンライン営業アシスタントでテレアポ・リード獲得を低コスト化 |
ネオキャリア |
人材採用×BPOのノウハウを駆使し、営業力を最短スピードで強化 |
コンフィデンス |
マーケ×セールスの実働支援で新規事業を成功に導く“売る仕組み”を構築 |
なぜ今「IT業界におすすめの営業代行」が注目されているのか
ここ数年、IT業界では製品やサービスの進化に伴い、新規顧客開拓の重要性がかつてないほど高まっています。特にSaaSやクラウドサービスといった分野では、競合が増える一方で需要も急拡大しており、従来の営業手法だけでは十分にカバーできないケースが多くなっています。エンジニアや技術者を抱える企業であっても、実際に顧客を獲得し、契約を取り付けるためには営業力が欠かせません。しかし、営業部門の強化には大きなコストやリソースが必要であり、ノウハウも蓄積しなければなりません。
こうした状況を背景に注目されているのが、「営業代行」というビジネスモデルです。特にIT業界に特化したノウハウや実績をもつ営業代行会社の存在が、急速に脚光を浴びています。営業代行をうまく活用することで、企業は短期間で新規案件を増やし、技術者をコア業務に集中させることが可能になります。また、営業活動を外部に委託することで、固定費を圧縮しながら成果を得る「変動費化」のメリットを享受できる点も、経営層にとって魅力的です。
さらに、政府や行政によるDX推進の後押しや、在宅勤務・リモート商談の一般化といった社会的背景により、オンライン主体の営業活動が大きく進んでいます。インサイドセールスやウェブ会議ツールの普及によって、場所や時間に縛られない柔軟な商談が当たり前になりつつあるのです。こうした変化の波に乗るためには、営業手法そのものをアップデートする必要があります。IT業界の商材特性に精通した営業代行会社は、このような新しい営業スタイルをすでに体系化・標準化しているケースが多いため、導入企業にとって早期の成果が期待できます。
これらの理由から、今「IT業界におすすめの営業代行」が注目を集めているのです。しかし、営業代行会社にはさまざまな種類があり、サービス範囲や料金形態も多岐にわたるため、自社の課題やリソースに合った選択をしなければ十分な効果を得られません。
IT業界におすすめの営業代行の基本:サービス内容と依頼する理由
営業代行とは、企業の営業活動を外部の専門組織に委託することを指します。特にIT業界における営業代行は、IT製品・サービスの専門知識を有するスタッフによるリード獲得から商談化、成約フォローまでを一貫してサポートするケースが多いのが特徴です。従来の一般的な営業代行と異なり、クラウドサービスの仕組みや技術的背景を理解した上で、企業の強みや提供価値を適切に訴求できる点が大きな強みといえます。
では具体的にどのようなサービスを提供しているのでしょうか。たとえば、以下のような流れが典型的なIT特化型営業代行の業務イメージとなります。
ターゲットリストの作成・整備
業種や企業規模、課題を抱えているであろうセグメントなどを分析し、優先度の高いリストを作成します。ここでの精度が商談化率に大きく影響します。
リード獲得施策の実施
電話やメール、SNS(LinkedInなど)を通じたアウトバウンド、あるいはウェビナーの企画・運営、広告運用を組み合わせることもあります。
アポイント設定・商談化
インサイドセールス(オンラインや電話での商談前段階の提案)を行い、顧客の課題をヒアリングしながら商談に進めます。ここでITサービスの基本的な仕組みや導入メリットを説明するには、一定の技術・製品知識が不可欠となります。
契約・クロージング支援
必要に応じて営業担当が同行(あるいはオンライン商談に参加)し、クロージングのサポートを行います。ITの場合、料金体系や導入フローが複雑なことも多いため、ここでの的確な説明が成約率に直結します。
導入後のフォロー・顧客満足度向上
契約後のオンボーディング支援やアップセル・クロスセルを代行する場合もあります。サブスクリプションビジネスでは、契約継続や追加契約の獲得が重要な収益源になるからです。
企業がこうした営業代行を依頼する理由としては、「IT商材を理解している営業担当を短期間かつコストを抑えて確保したい」、「自社に営業リソースがなく、エンジニアや開発に注力したい」、「新規市場へ参入する際のスピードを重視したい」という動機が挙げられます。特にスタートアップや中小企業の場合、経営者自身が営業を兼任しているケースも珍しくありません。しかし、経営判断や開発、チームマネジメントなど他の業務に追われ、十分な営業活動が行えないまま機会を逃してしまうことが多いのです。IT営業代行を導入することで、そうしたボトルネックを解消し、本来のコア業務にリソースを集中できるようになります。
IT業界におすすめの営業代行の料金体系と相場:固定報酬・成果報酬・ハイブリッド
営業代行の料金形態は多岐にわたりますが、主に以下の3つに分類されることが多いです。IT商材は営業難易度が比較的高いとされるため、設定金額もやや高めになる傾向があります。
固定報酬型
月額で一定の報酬を支払う形態です。たとえば「月額50万円〜150万円」というように幅があり、依頼する業務範囲の広さや扱う商材の難易度によって大きく変動します。固定報酬型のメリットは、代行会社が安定的にリソースを確保しやすく、長期的な視点で営業施策を実施できること。デメリットとしては、成果が出なくても一定額のコストが発生するため、短期間に成果を求める企業からするとリスクが高いと感じる場合があります。
成果報酬型
アポ獲得1件あたりや成約金額の○%といった、成果に応じて報酬を支払う形態です。IT商材の場合、商談を獲得する難易度が高いことから、1アポイントあたり3万円〜10万円程度、成約報酬なら契約額の10〜30%といった設定例が見られます。企業側からすると成果とコストが連動するため、無駄な支出が減るのがメリットです。一方、代行会社にとってはリスクが高く、対応可能な業務範囲が限られたり、事前の要件定義が厳密になったりする点がネックです。
ハイブリッド型(固定+成果報酬)
固定報酬と成果報酬を組み合わせた形態です。たとえば「月額30万円をベースに、成約時は契約金額の15%を成果報酬として支払う」など、双方が納得できるバランスを取る形にします。この方式は代行会社に最低限のリソースを確保する手当を行いつつ、成果が出た場合に上乗せで報酬を支払うため、両者にとって妥協点を見出しやすいメリットがあります。ただし、報酬計算がやや複雑になるため、あらかじめKPIや計算方法を厳密に定義しておく必要があります。
営業代行の相場
相場としては、依頼内容や取り扱うIT商材の単価・販売難易度によっても差が大きいですが、一般的には月額20万〜100万円前後の範囲に収まることが多いです。IT系の複雑な商材や大型案件が絡む場合は、月額150万円以上になるケースもあります。費用対効果を見極めるためには、必ずKPIを設定し、「どのくらいのリード獲得が見込めるのか」「1件あたりの平均受注単価はどれくらいか」といった数値をもとに計算しておくことが重要です。
IT業界におすすめの営業代行の導入メリット・デメリット
営業代行は、その専門性を活かして企業の営業活動を強力に支援してくれますが、同時に注意しなければならない面も存在します。ここでは導入メリットとデメリットを明確に示します。
メリット1:コア業務への集中
IT業界では、製品開発や運用サポートといったコア業務が売上を左右する大きなポイントです。営業代行を導入すれば、エンジニアやプロダクトマネージャーが営業対応に追われることなく、本来の業務に注力できるようになります。
メリット2:専門ノウハウの活用
IT商材は、顧客にメリットを正しく理解してもらうために高度な知識や事例紹介が必要です。IT特化の営業代行会社は、SaaSやクラウドサービス、セキュリティソリューションなどの技術的背景とビジネス活用事例に精通しているため、リード獲得からクロージングまでのプロセスを効果的に進められます。
メリット3:営業コストの変動費化
社員を雇用すると給与や社会保険、教育コストがかかり、固定費として企業の財務を圧迫します。一方、営業代行であれば必要な期間だけの契約や成果ベースの報酬設定が可能で、コストを抑えやすくなります。
メリット4:短期間での市場開拓が可能
新たな市場や新規事業へ挑戦する場合、自前の営業チームを構築していると時間がかかるだけでなく、ノウハウがないために手探り状態が続きがちです。営業代行を活用すれば、すでにその市場にノウハウを持ったプロフェッショナルの力を借りて、短期間で足がかりを作ることができます。
デメリット1:自社営業ノウハウが蓄積しにくい
営業代行会社が活動している間は問題ないとしても、将来的に自社で営業組織を強化しようと考えたときに、ノウハウや人脈が社内に残らないというリスクが生じます。
デメリット2:品質や実績にばらつきがある
営業代行会社にはさまざまな規模・得意分野があるため、一概にどこもIT商材を完璧に扱えるとは限りません。下調べが不十分なまま委託すると、期待値とのギャップが大きく、費用倒れに終わる可能性もあります。
デメリット3:自社商材理解が浅いと効果が出にくい
代行会社に任せれば自動的に売れるというわけではありません。IT商材は機能面や導入効果が複雑な場合も多く、代行スタッフに正しく理解してもらうためのトレーニングや情報提供が必要です。これを省略すると、的外れな提案になり商談化が進まない恐れがあります。
デメリット4:コミュニケーションコスト
定期的な進捗確認やフィードバックが欠かせないため、担当者が増えたり社内外での連携が複雑化したりする場合があります。社内に営業責任者が存在しないと、さらに管理が難しくなるケースもあります。
営業代行会社を選ぶ際に押さえておきたいポイント
営業代行を活用するメリットを最大化し、デメリットを最小化するためには、導入前の選定が極めて重要です。IT業界に特化した営業代行会社を選ぶにあたって、特に押さえておくべきポイントをいくつか挙げます。
IT商材に関する過去の実績やナレッジ
代行会社のサイトや資料、ヒアリングを通じて、自社と類似の商材やターゲット業界での実績があるかを確認しましょう。SaaS型サービスなのか、オンプレミスのソリューションなのか、あるいはAIやIoTなど先端技術を扱う商材なのかによっても営業アプローチは異なります。できるだけ近しい領域で成功事例を持っている会社だと安心です。
料金体系やKPIの明確化
固定報酬なのか、成果報酬型なのか、ハイブリッドなのかを確認し、成果の定義を明確に設定しましょう。たとえば「アポ獲得数」「商談数」「成約数」など、どの段階を成果とみなすのか、あらかじめ共通認識を得ることが大切です。
対応範囲と連携体制の把握
リード獲得だけでなく、商談の同席や提案書の作成補助、あるいは契約後のフォローまでを一貫して対応してもらえるのか。実際にどの程度のリソースを使ってくれるのか。社内担当との連携方法やコミュニケーションツール(メール、チャット、CRMなど)も含めて詳細を確認しておくとスムーズです。
チーム体制と担当者のスキル
営業代行会社といっても、実際にはアカウントマネージャーやインサイドセールス担当、テレアポ専門スタッフ、マーケティング支援スタッフなど、さまざまな専門家がいます。誰が自社の案件を担当し、どのようなスキルセットを持っているのかを確認しておきましょう。
レポーティング・進捗管理の仕組み
営業状況をどの頻度で、どんな内容をレポートしてもらえるのかは非常に重要です。数字がどのように変化しているのか、目標に対してどのくらい達成しているのかを把握することで、迅速な軌道修正や施策変更が可能になります。
営業代行導入前に知っておくべき注意点と社内準備
営業代行を利用する際、代行会社の選定だけでなく、社内体制の整備も非常に重要です。ここを疎かにすると、いくら優秀な営業代行会社を選んでも成果が十分に発揮されないケースが多々あります。以下に代表的な注意点と社内準備を解説します。
注意点1:社内情報の整理・共有
IT商材は機能や導入メリットが複雑になりがちです。代行会社が顧客に正しいアプローチをするためには、製品・サービスの特長、価格体系、導入実績、競合優位性などをわかりやすくまとめた資料が必要です。複数の資料がバラバラに存在している場合は、営業マニュアル的な形でまとめ、常に最新情報を共有できるようにしておきましょう。
注意点2:責任者と連絡フローの明確化
社内で「誰が代行会社と窓口になるのか」が曖昧だと、コミュニケーションロスが生じやすくなります。責任者が明確になっている場合でも、万が一の不在時に対応できる代理の担当者を決めておくなど、ストレスなくやり取りができる体制づくりが必要です。
注意点3:目標KPIと評価指標の設定
営業代行を利用する目的をハッキリさせ、たとえば「1カ月に○件の商談を獲得する」「成約率を○%以上にする」といった具体的な目標をKPIとして定義しましょう。KPIが明確であれば、代行会社との間で「どうすれば目標達成できるか」を建設的に議論しやすくなります。逆に目標が曖昧だと、ゴールがどこかわからず、営業代行に費用をかけても成果が見えづらい状況に陥ります。
注意点4:CRMやMAツールなどの整備
リード獲得から契約、アフターフォローまで一連の流れを一元管理できるシステムを導入している場合は、営業代行側にも適切な権限を付与してデータを共有する必要があります。これにより、リアルタイムに進捗を見たり、顧客情報を円滑に更新したりすることができます。一方、システムが未導入の場合でも、Excelやスプレッドシートなど最低限の管理方法を確立し、共有するルールをあらかじめ決めておくことが大切です。
注意点5:長期視点での評価
営業代行は魔法の杖ではありません。特にIT商材は商談化までにリードの検討期間が長い場合もあるため、短期間で大きな成果が出るものではないケースがあります。数カ月スパンで施策を検証し、適宜改善を重ねていくプロセスが必要です。もし短期的な成果だけにこだわりすぎると、本来の価値を引き出しきれないまま契約終了となる恐れがあります。
まとめ:営業代行を活用し、効率的な営業体制を目指す
IT業界では、技術革新のスピードや競合の激化が目覚ましく、新規開拓や顧客獲得の手法も多様化しています。自社内で営業組織を構築することが理想的なケースもありますが、ノウハウや人材確保の観点から難易度が高い企業も少なくありません。そこで、IT商材の専門知識を備えた営業代行会社を活用することで、短期間に成果を上げられる可能性が高まります。
ただし、営業代行はあくまで「外部のパートナー」であるため、社内の情報共有やコミュニケーションの設計が欠かせません。また、費用対効果を最大化するためには、料金体系や成果指標の設定、導入目的の明確化が重要です。固定報酬・成果報酬・ハイブリッド型のいずれを選ぶにしても、一足飛びに成果が出るわけではなく、代行会社とともに検証を重ねながら戦略を調整していくプロセスが必要になります。
営業代行を上手に活用すれば、経営者やエンジニアが本来の業務に集中し、プロフェッショナルによる新規開拓・顧客フォローが同時並行で進みます。これにより、ビジネスの成長スピードを加速させるだけでなく、社内で培ったナレッジを今後の自社営業強化にも活かすことが可能となります。
本記事で紹介した基礎知識や注意点を踏まえ、ぜひ自社の状況に合ったIT業界向け営業代行サービスを選定し、持続的な売上拡大へとつなげていただければ幸いです。営業代行は、単なる「外注」ではなく「一緒に事業を伸ばしてくれるパートナー」です。どのように上手く協働し、どのようにノウハウを取り込むかが、今後のビジネス成長を左右する大きな鍵となるでしょう。
- 免責事項
- 本記事は、2025年2月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。