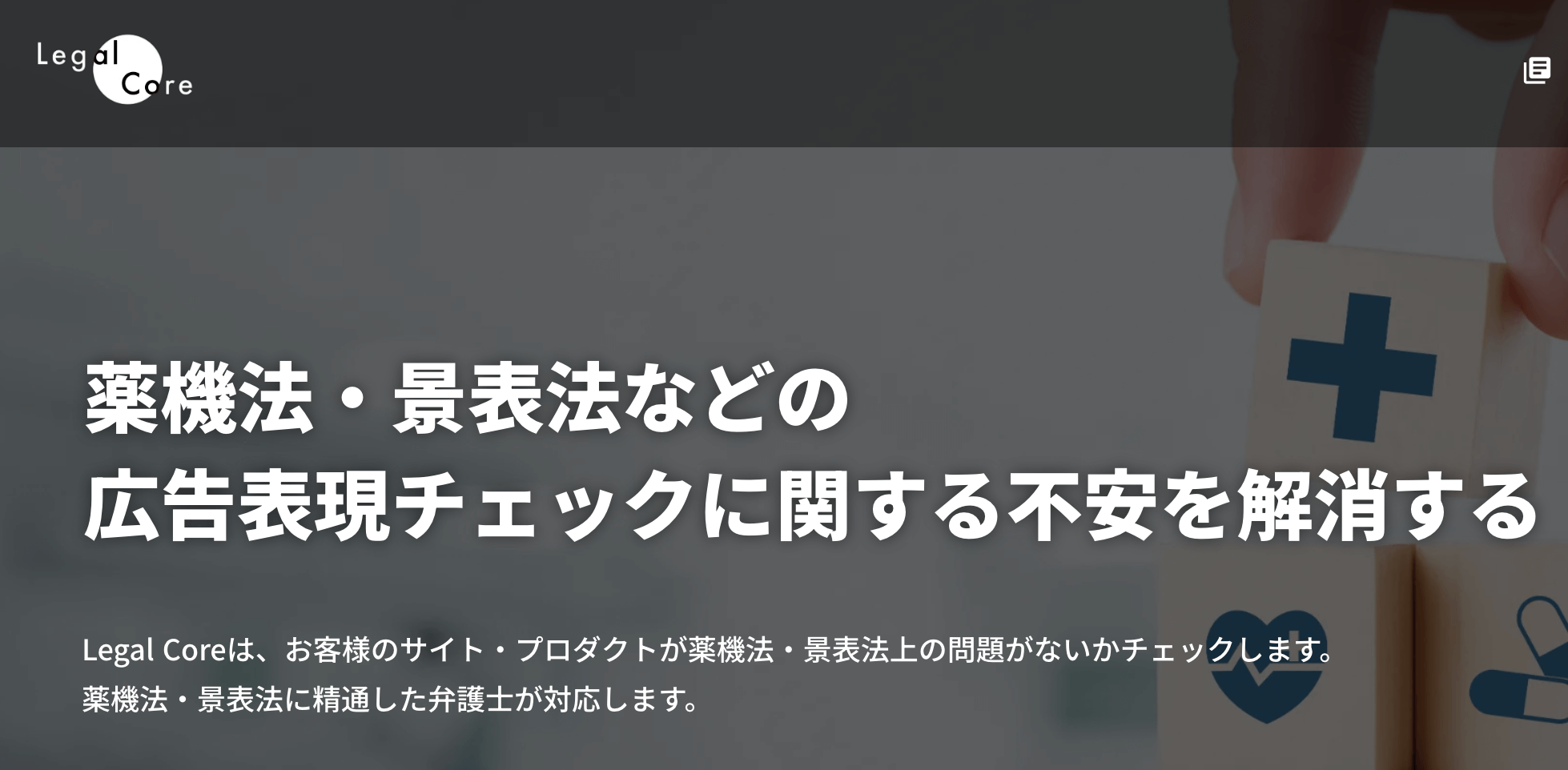地域医療連携システムは、医療機関間の情報共有を円滑にし、患者の診療情報を一元管理することで診療の質を向上させる重要なシステムです。地域医療連携システムを利用することにより、情報共有漏れによるミスのリスクを防ぎ、迅速な対応が可能となります。また、業務の効率化やコスト削減にも役立ちます。
この記事では、各社が提供する地域医療連携システムの特徴を一覧で比較し、病院のニーズに最適なシステム選びをお手伝いします。導入のメリットやシステムの選び方についても詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
地域医療連携システムおすすめ一覧表
ここでは、各社が提供する地域医療連携システムの特徴などを一覧で紹介しています。医療連携システムはそれぞれの病院に合ったものを選ぶことが大切なので、各社のサービスをしっかりと比較・検討することがおすすめです。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
medigle |
基幹病院での圧倒的シェア率!月額0円~、地域医療連携の強化を総合的にサポート |
HAPPY netty |
患者情報の共有などでシームレスな地域連携を実現 |
メディマップ |
16万件以上の医療機関情報を一元管理 |
MIO Karte |
複数の医療機関間での診療情報の共有を実現 |
ありあけネット |
電子カルテ情報を安全に共有 |
PrimeArch (プライムアーチ) |
クラウド型もオンプレミス(導入型)も対応 |
LOOKREC |
クラウド型DICOMデータプラットフォームを提供 |
foro CRM |
データの一元管理と効率的な分析をサポート |
CAREBOOK |
分析機能で利用者ごとのサービス利用・提供状況がわかる |
firstpass |
4つのシステム群構成でさまざまな連携業務を支援 |
Karte window |
セキュアなネットワークと高い柔軟性を提供 |
ケアミル |
多機能オプションで地域事業を包括的にサポート |
Comlavie-aL |
簡単な操作でオンライン予約等の管理を実現 |
地域医療連携システムとは?
地域医療連携システムとは、地域内の医療機関情報や患者の診療情報を一元的に管理するためのシステムです。
地域医療連携システムの定義
病院間の情報共有をスムーズにし、入転院調整や救急搬送、専門外の医師への相談などを円滑に行えるようにします。診療情報や受け入れ先情報が分散していると、迅速かつ的確な医療サポートや引き継ぎが困難になりますが、地域医療連携システムの導入により、必要な情報を迅速に共有でき、地域の医療機関が緊密に連携できます。医療サービス全体の質が向上し、患者の安心感が増すのが大きな特徴です。
地域医療連携システムの重要性と役割
地域医療連携システムの重要性は、患者の診療情報を複数の医療機関で共有することで、多角的かつ効率的な医療提供を実現する点にあります。
地域医療連携システムを導入することで、各医療機関が患者情報をリアルタイムで閲覧・更新できるため、重複する検査や投薬を防ぎ、診療の質を高めます。また、急性期病院から地域のクリニックや訪問看護へとスムーズに患者を引き継ぐことができ、地域全体で患者を支える体制を構築することが可能です。これにより、医療機関間の連携が強化され、地域医療の持続可能性が向上します。
地域医療連携の課題
人員不足
地方や過疎地では医師の減少が深刻であり、地域医療連携の業務に従事する事務方や営業を行う人も不足しています。このような人員不足の状況では円滑な地域医療連携が難しく、適切な医療提供が困難です。大都市圏でも医師の偏在により、地方では医師不足が顕著です。医療従事者の確保と地域医療連携の推進が急務となっています。
医療機関の機能が不明瞭
各医療機関の機能が不明瞭であり、他の病院からは評価しにくい状況があります。例えば、普段多くの患者を受け入れている病院も離職者が出れば受け入れ余裕がなくなりますが、その内情は他の病院からは見えません。専門性の高い手技や治療を行う医師が一人いなくなるだけで、その病院の専門性が失われる可能性もあります。これにより、患者の紹介や転院がスムーズに進まないことがあります。
情報共有システムの遅れ
日本の医療界ではアナログな情報管理が多く、情報共有システムの遅れが課題となっています。患者情報が紙カルテに保存され、他院に転送する際も紙媒体やCDにコピーして手渡すという現状です。最近では電子カルテが普及してきましたが、他施設間での共有はほとんど進んでいません。患者が意識障害で急性期病院に搬送された場合、かかりつけ医療機関に問い合わせるしかなく、連絡がつかないと検査や投薬を一から行う必要があります。
少子高齢化と人口動態の影響
日本では少子高齢化と人口減少が進み、2025年には団塊の世代が75歳以上となります。これにより、医療や介護、看護や福祉の需給が逼迫し、医療を必要とする高齢者の割合が増加します。高齢者の増加に伴い、医療費の自己負担率が低い高齢者が増加し、医療費の捻出も難しくなります。効率の良い医療提供が困難になり、本当に治療を必要とする患者に適切な医療を提供できなくなる可能性があります。地域医療連携の推進・強化が急務です。
地域医療連携システムを導入するメリット
紹介・逆紹介業務の効率化
地域医療連携システムの導入により、紹介・逆紹介業務が効率化されます。システムにより、地域の医療機関情報や患者の診療情報が一元化され、最適な医療機関への案内がスムーズになります。
紹介状や診療情報提供書などの必要書類も迅速に準備でき、ミスのない効率的な予約手続きが可能です。これにより、医療機関間のコミュニケーションが改善され、患者の移動もスムーズに進みます。
集患の強化
地域医療連携システムに登録することで、自院のPR効果が高まり、集患が強化されます。待合室に設置したサイネージやタッチパネルで地域の医療機関情報を公開するなど、連携医療機関(登録医)となることで、かかりつけ医としての認知度が上がります。
紹介件数の増減推移や紹介件数、紹介科の特徴などのデータを分析し、ピンポイントで情報発信することで、病院経営が改善された事例もあります。
診療の最適化
地域医療連携システムを利用すると、投薬、注射、検査、画像検査などの情報が共有できるため、検査や薬剤の重複や併用禁止薬剤の投与を防げます。複数の医療機関を受診する場合も、無駄な診療や検査が省け、効率的な医療提供が実現します。また、患者の診療情報が常に最新の状態で共有されるため、安全性も向上します。
患者の負担軽減
地域医療連携システムの導入により、患者の負担が軽減されます。転院時に二重投薬や二重検査が発生することを防ぎ、再度同じ説明を行う必要がなくなります。これにより、患者は安心して医療を受けられ、治療に専念できる環境が整います。また、診療情報が共有されることで、患者の治療経過を追いやすくなり、最適な治療方針を迅速に決定できるようになります。
業務の効率化
地域医療連携システムを活用することで、医療機関の業務が効率化されます。転院や他院への紹介時に詳細な状況を記載する紹介状の作成が不要となり、書類作成にかかる時間と手間が省けます。これにより、医療スタッフは患者の診療に集中でき、業務の効率化が図られます。また、情報の一元管理により、必要な情報へのアクセスが迅速かつ容易になり、業務全体の生産性が向上します。
スムーズに転院先の紹介可能
地域医療連携システムの活用により、患者の診療情報が共有されるため、対応可能な医療機関を迅速に探し、スムーズに紹介できます。これにより、急な転院が必要な場合でも、患者に適切な医療機関を紹介することが可能です。また、システム上で転院先の医療機関の状況を把握できるため、患者に最適な医療提供が実現します。
地域医療連携システムの選び方
地域医療連携システムの導入を検討する際には、各システムの特徴や機能を理解し、目的に合った最適なシステムを選ぶことが重要です。以下に、主なシステムの種類と選び方のコツを紹介します。
地域医療連携システムの種類
前方支援から後方支援を含め対応するタイプ
このタイプは、病診連携や地域連携だけでなく、退院後の在宅へのスムーズな移行を支援します。診療所や訪問看護、介護事業所などとの連携支援まで包括的に行えるため、アナログ業務の工数や人的ミスを削減し、サービスの質を向上させたい場合に最適です。主な機能には紹介受付、各種文書作成、紹介情報管理、返書管理、逆紹介管理、退院支援・調整状況照会、退院支援計画書作成、病棟・退院支援部門情報共有などがあります。
診察・検査情報を共有するタイプ
このタイプは、診療情報全般の共有に対応し、紹介先医療機関での患者の投薬、注射、検査、画像検査などの情報を共有できます。無駄なく安全な診療をスピーディーに行いたい場合に適しています。主な機能にはカルテ情報、地域の医療リソース活用のための機能、CTやMRIの検査予約、受付や依頼状況の確認などがあります。医師自身が手元のPC端末で患者の投薬履歴、検査結果、検査画像を確認できるため、紙文書の所見や検査結果を参照したり、患者にヒアリングする必要がなくなります。
検査画像の共有に特化したタイプ
検査画像の共有に機能を絞ったタイプです。検査画像の保存先として導入しやすく、患者の満足度や診断力の向上を図りたい場合に適しています。主な機能にはCT車連携、遠隔読影、コンサル機能、AI診断、症例データベースなどがあります。検査画像をクラウド上に保存し、電子カルテと連携させることで、カルテからワンクリックで患者の検査画像を呼び出せるため、その場で画像を見せながら患者への説明が可能です。
CRMタイプ
連携医療機関の情報を一元管理し、紹介・逆紹介の強化を図るタイプです。より多くの患者を紹介してくれる病院を可視化して関係性を強化したり、紹介の少ない病院にアプローチしたりすることで、患者数を増やしたい場合に適しています。主な機能には連携先管理機能、連携先マップ機能、アラート機能、分析機能、効果検証機能などがあります。診察後に看護師やクラークが適切な医療機関の候補を選定し紹介することで、患者に「かかりつけ医」への周知ができ、患者数の増加を図れます。
後方支援(退院・転院調整)に特化したタイプ
退院・転院調整に特化したタイプで、中核病院の地域連携室などに導入されることが多いです。地域連携室の業務を効率化・標準化したい場合に適しています。主な機能には入退院調整、各患者の退院調整の状況把握、タスク管理、集計やレポートの自動出力、一括キャンセル、書類添付機能、予約票や礼書の自動FAXなどがあります。これにより、電話やFAXで行っていた退院調整がオンライン化され、業務効率化が実現します。
予約管理に特化したタイプ
紹介予約の受付業務効率化に特化したタイプです。医療機関からの紹介がFAXや電話などのアナログな手段に限られている場合に、Web予約を導入したい場合に適しています。主な機能には予約情報の検索、タイムテーブル設定、予約票・診療情報提供書の作成、医療施設の登録・検索などがあります。Web予約画面から紹介先病院の予約を完了し、その場で予約票・紹介状をプリントアウトできるため、患者の手を煩わせることなく、迅速な対応が可能です。
地域医療連携システムを選ぶコツ
費用対効果を高める
地域医療連携システムを選ぶ際、費用対効果の高さを重視することが重要です。導入費用が高い場合でも、そのシステムが持つ機能が実際の業務効率化や患者満足度の向上に繋がるかどうかを慎重に評価する必要があります。例えば、システムによって業務効率が向上し、ミスが減少することで、結果的にコスト削減が見込める場合、そのシステムは費用対効果が高いと言えます。
求めている機能の搭載
システムが求める機能を十分に搭載しているかを確認することが大切です。自院が必要とする機能を明確にし、それに基づいて製品を選定します。例えば、紹介状の作成や予約管理が主なニーズであれば、それらの機能が優れたシステムを選ぶことが必要です。製品の種類やメーカーによって、提供される機能や特徴は異なるため、自院のニーズに最適なシステムを選ぶことが求められます。
操作性の優れたシステム
操作性の良いシステムを選ぶことも重要です。業務効率化を図るためにシステムを導入しても、操作が難しく使いこなせなければ意味がありません。特に頻繁に使用する操作が簡単かどうかを確認し、スタッフがスムーズに利用できるシステムを選びましょう。例えば、直感的に操作できるユーザーインターフェースや、迅速なサポート体制が整っているシステムが理想的です。
地域医療連携システムのまとめ
地域医療連携システムは、地域内の医療機関が患者情報を一元的に管理し、スムーズな情報共有を実現するシステムです。これにより、紹介・逆紹介業務の効率化や集患の強化、診療の最適化、患者の負担軽減、業務効率化、迅速な転院先の紹介が可能となります。
システムを選ぶ際には費用対効果、求める機能の搭載、操作性を重視することが重要です。自社にとって必要な機能などを見極めて、導入するシステムを選定することをおすすめします。
- 免責事項
- 本記事は、2024年7月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。