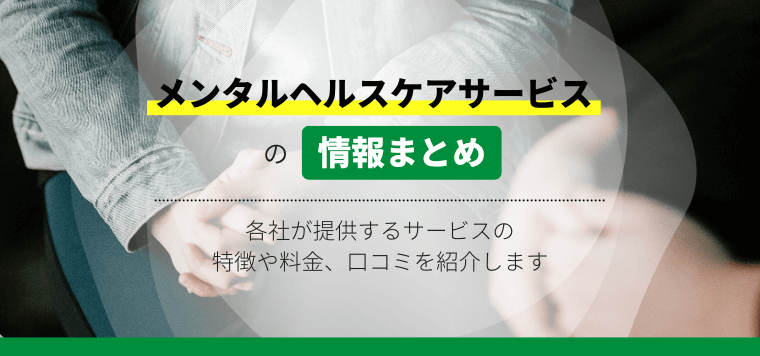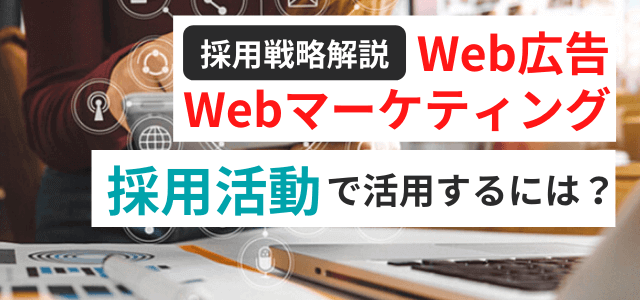離職防止ツールとは、アンケートに回答するなどによって一人ひとりのやる気や心の状態を把握し、離職を防止するだけでなく、定着率を向上させることにもつなげられるツールです。離職防止ツールを導入すれば、コミュニケーションを活性化させ、人事担当者の負担を軽減できます。
この記事では、離職防止ツールを取り扱う企業の特徴や選ぶべき理由、導入事例などと併せて、メリット・デメリット、選び方などについても解説しています。離職防止ツール導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
離職防止ツールの一覧表
一口に離職防止ツールといっても、機能やオプションサービスはシステムによってさまざまです。導入する前に費用対効果の計算・検討を十分行った上で、大切な人材を守るためにも、使いやすい離職防止ツールを導入してください。
| 会社名 | サービスの特徴 |
|---|---|
コンケア |
従業員のコンディションを継続的にトラッキングできる導入しやすいツールなら
|
Geppo |
個人のパルスサーベイと組織サーベイの両方の課題を見える化してPDCAを支える |
Motify HR |
多彩な機能で従業員同士の相互コミュニケーション向上にもつながる |
Willysm |
3つの中から選んで今の気分を入力することができるスマートフォンアプリ |
Kakeai |
従業員視点での個別・支援型マネジメントツールで細かくチューニング可能 |
Wistant |
外部ツールと連携させることもできるマネジメントの実行支援ツール |
いっと |
外部の専門のインタビュアーが従業員の本音を調査 |
なやさぽ |
質問に一つ一つ回答して悩みの解消をサポートして離職を防止するツール |
タレントパレット |
データを活用した人事で組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステム |
SOLANOWA |
一人40円という低価格で利用できるWeb社内報アプリ |
TUNAG |
多彩な業務DX機能と高いカスタマイズ性を備えるオールインワンツール |
ミツカリ |
10分でできる適性検査で相性を可視化してさまざまな人事課題を解決 |
PULSE AI |
本音を調査して課題をスコア化、わかりやすくグラフで表示 |
Wevox |
心理状態を見える化して人材や組織における課題を明確化、改善サイクルをサポート |
OH!KIMOCHI |
簡単かつ低コストのオンラインサンクスカード |
SmartHR |
労務手続きをシームレスに完結して新しい人事データを簡単に把握できる |
メンタルヘルスさくらさん |
一人ひとりの心をケアして悩みを解決し、従業員と組織の生産性を向上 |
GRATICA |
人とのつながりを深められるクラウドサンクスカード |
RECOG |
レター機能で感謝や称賛を伝えてポジティブな効果を生み出す |
離職防止ツールとは?
離職防止ツールとは、離職を防止して定着率を向上させるため、従業員の心の状態やモチベーションを、アンケートに回答することなどによって把握するシステムのこと。離職原因を分析したり、エンゲージメントを見える化したり、モチベーションを向上させるための仕組みづくりなどを行ったりするために活用されます。
従業員の定着率を向上させることは、企業にとって非常に大事な課題といえます。離職防止ツールを導入すれば、大切な人材をさまざまな面で守り、できるだけ少ないコストで離職を防止することができます。
離職防止ツールを導入するメリット
エンゲージメントを可視化できる
従業員が、自発的に貢献意欲をもって業務に取り組んでいるかを表す指標であるエンゲージメントを可視化することで、離職を防止することができます。
「今の仕事に満足していますか?」「適切に評価されていると思いますか?」などのアンケートを定期的に実施し、従業員の満足度を把握します。
人事担当者の負担を軽減できる
離職防止ツールのメリットは、人事担当者の負担を軽減できる点も挙げられます。規模が大きい企業の場合、人事担当者が個別に一人ひとりをフォローする体制はとりにくく、どうしても漏れが出てしまい、離職者が発生します。
離職防止ツールを導入すれば、離職の傾向がある従業員をピックアップ可能。誰に注力すればいいのかがわかりやすくなりますので、手間や時間を大幅に削減可能です。
コミュニケーションを活性化できる
不満を抱える従業員は、相談できる場がなければ悩みを解消できず、結果的に離職してしまう場合があります。そういったことを防止するためには、上司と部下はもちろん、従業員同士のコミュニケーションを活性化させる必要があります。
不満が積もり積もって爆発してしまう前に、密なコミュニケーションをとっていれば、どんな悩みや不満があるかを早い段階で察知でき、改善策を考えられます。
交流会を開催したり、上司と部下で定期的に1on1ミーティングを行ったりするなど、コミュニケーションをオープンにし、話しやすい職場環境を作り出しましょう。
離職防止ツールを利用するデメリット
効果を実感できるまで時間がかかる
離職防止ツールを導入後、それぞれの社員の業務内容やモチベーションを把握し、データを収集するところから始めなければいけないため、効果を感じるまでに、時間がかかることがデメリットです。
そのため、長期的な運用を考慮し、定期的に結果を振り返ることも大切。せっかく導入しても、しっかり機能していなければ意味がありません。社員が運用において協力する姿勢でいるかどうかも、確認しておく必要があります。
運用コストがかかる
離職防止ツールを導入する場合は初期費用・月額利用料がかかり、料金設定は、一か月で数百円~数万円と幅が広いことを注意しておいてください。また、ツールによって、搭載されている機能や利用制限人数が違ってきますので、しっかり確認しておきましょう。
しかし、コストがかかっても、優秀な社員を失うことの方が、会社にとってデメリットといえますので、ある程度のコストや時間は必要不可欠だといえます。
離職防止ツールに関するよくある質問
Q1. 離職防止ツールの費用相場は?
具体的な費用相場は、どのツールを使うかや、会社の規模などによって異なりますが、まず初期費用・月額利用料がかかります。また、一か月で数百円~数万円の料金設定があり、従業員が100人いる場合では、毎月約数万円〜数百万円以上の費用がかかるケースも出てきます。
Q2. 離職防止ツールを選ぶときの注意点は?
まずは、事前にツールのデザインや扱いやすさを確認し、誰でも簡単に使えるかを確認してください。パソコンだけでなく、スマホやタブレットでも使用可能なマルチデバイスツールを選ぶことをおすすめします。
導入する前に、費用対効果の計算・検討を行うことも大事。ある程度のランニングコストが必要不可欠ですので、時間的なコストも考慮して検討する必要があります。
また、具体的な離職防止の施策についてもツールに任せたいという場合、フォローまで代行できる制度や、コンサルティング機能を備えた離職防止ツールがおすすめ。フォロースキルを獲得できる研修を提供しているツールもありますので、自社のフォロー体制と照らし合わせながら、検討を進めてください。
離職防止ツールの導入を考えている方は、本ページに掲載している「離職防止ツールの早見表」をご覧ください。
離職防止ツールのまとめ
離職防止ツールとは、アンケートに回答することなどによって、一人ひとりの従業員の心の状態やモチベーションなどを把握し、離職を防止して定着率を向上させるためのツールです。離職防止ツールを導入することで、エンゲージメントを可視化してコミュニケーションを活性化させ、人事担当者の負担を軽減できるメリットがあります。大切な人材を守るためにも、ぜひ離職防止ツールを導入することをおすすめします。 一方、離職防止ツール導入のデメリットには、効果を実感できるまで時間がかかることや、運用コストがかかる点が挙げられます。しかし、時間やコストがかかっても、優秀な社員を失うことの方が、会社にとってはデメリット。導入する前には費用対効果の計算・検討を十分行い、ツールのデザインなどにも注目し、使いやすいツールを選びましょう。
自社のフォロー体制に不安がある場合は、離職防止の具体的な施策についても任せられるツールもあります。離職防止ツールを導入する際は、メリット・デメリットをしっかりと確認するとともに、選び方についても理解しておいてください。
- 免責事項
- 本記事は、2023年12月時点の情報をもとに作成しています。掲載各社の情報・事例をはじめコンテンツ内容は、現時点で削除および変更されている可能性があります。あらかじめご了承ください。